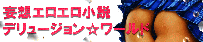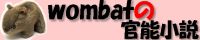スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
妄想商会(22)~ポチの首輪〈第6話〉~*特殊アイテム
極度の羞恥心に煽られながらも、一通りの脱衣ショーを披露した奈緒に対し、晋吾は立て続けの羞恥攻撃を仕掛けた。
「奈緒、いい子だね。じゃあ、次はこの家に住みつく前の身体検査をしよう。両脚を大きく開いてごらん」
「…はいぃ」
既に消え入るような返事ではあるが、ご主人様の指示である。
奈緒は未だ股間に手を当てながらも、自分の肩幅よりも広く両脚を開いて立った。
「よし。そのまま上半身を前に倒して、手で足首を掴むんだよ」
「…えっ!?…そ、そんなことしたら…」
「ん?したら…どうだって言うの?」
「恥ずかしいところが…見られてしまいますぅ…」
そこだけは…というような懇願の眼差しで晋吾を見つめながら、何とか許しを乞いたい奈緒であるが、今の晋吾がそんなことを許すはずも無い。
「その恥ずかしいところを検査するのが、主人の役目だろ! もし奈緒のそこに病気があって、同じヒトである香織にでも移したらどうするんだ? 香織も怖いだろ?」
「はい。怖いです。奈緒、恥ずかしくないよ!私もいつもご主人様に見てもらってるんだから、頑張ろっ!」
傍でこれまでのやり取りを傍観していた香織が、既に先輩ペットの自覚をもたげて奈緒を励ました。
「…わ、分かりましたぁ…」
奈緒は恐る恐るといった様子で股間から手を離し、ゆっくりと上体を前傾させ、遂に腰と頭の位置を上下逆転させた体勢で、両足首を手で握った。
当然のごとく、大きく開かれた脚と今や頂点にある腰とで、恥ずかしい三角形が出来上がり、その頂上周辺には未成熟の少女には誰にも見せたくはないであろう生殖器と排泄器が、とうとう晋吾の眼前に晒されてしまった。
お風呂を共にした幼少の頃には、全く気にも留めていなかったその下半身は、今では晋吾の背徳心を強烈に刺激するほどの変貌を遂げていた。
比較的濃い目と思われる陰毛は、まだ誰にも犯されていないピンク色の秘所の周りを縁取り、そのまま細々とアナル周囲まで達している。
「ん~~、見た目には病気などは無さそうだが、中の方も確認しないと分からないからな。奈緒、何をされてもそのままじっとして動くんじゃないぞ」
「…は、はいぃ…」
恥ずかしさからなのか、逆さまになっている頭に血が上り始めているからなのか、奈緒は顔をすっかり赤らめながら、相変わらずの消え入りそうな声で、じっとその恥ずかしすぎる体勢を維持している。
そんな奈緒の様子などお構いもせず、晋吾はその秘所に鼻を押し付けるかのごとく近づけて、クンクンと匂いを嗅ぎ始めた。
まだうら若き乙女の大事な部分の匂いを堂々と嗅ぐ…その甘い刺激臭と強烈な支配感に、脱衣ショーの時から既に屹立していた晋吾の一物は、更にその膨張の度合いを高めていく。
既に入浴を済ませた後の股間は、生々しい女性器の匂いこそ放ってはいないが、多分入浴後にオシッコはしたのであろう…わずかなアンモニア臭は残っていた。
「香織、ちょっと中も調べたいので、滑りやすくなるようにここをよーく舐めてあげてよ」
「はい。わかりました」
奈緒は、晋吾と香織のそんなやりとりに驚いたらしく、逆さまの顔を赤らめたまま、
「…え!?、えぇーっ!?」
「奈緒はそのまま動かないこと。いいね?飼い主の言いつけだぞ」
そう言っている傍から、横に控えていた香織は、自分の顔の目の前に奈緒の股間が迫る位置に座り込み、小ぶりではあるがピチピチとした瑞々しい桃を連想させるお尻を両手で押さえると、自分の顔を押し付けんばかりにして、奈緒の恥ずかしい部分を舐め始めた。
「ひゃぅっ!あっ、だ、だめぇっ!…あはぁぁぅぅ…あっ、あぅぅ…」
晋吾の眼前で、真っ裸の元美人人妻と、これまた真っ裸の元アイドル級女子高生のレズプレイが展開され始めた…。
(執筆継続中…)
「奈緒、いい子だね。じゃあ、次はこの家に住みつく前の身体検査をしよう。両脚を大きく開いてごらん」
「…はいぃ」
既に消え入るような返事ではあるが、ご主人様の指示である。
奈緒は未だ股間に手を当てながらも、自分の肩幅よりも広く両脚を開いて立った。
「よし。そのまま上半身を前に倒して、手で足首を掴むんだよ」
「…えっ!?…そ、そんなことしたら…」
「ん?したら…どうだって言うの?」
「恥ずかしいところが…見られてしまいますぅ…」
そこだけは…というような懇願の眼差しで晋吾を見つめながら、何とか許しを乞いたい奈緒であるが、今の晋吾がそんなことを許すはずも無い。
「その恥ずかしいところを検査するのが、主人の役目だろ! もし奈緒のそこに病気があって、同じヒトである香織にでも移したらどうするんだ? 香織も怖いだろ?」
「はい。怖いです。奈緒、恥ずかしくないよ!私もいつもご主人様に見てもらってるんだから、頑張ろっ!」
傍でこれまでのやり取りを傍観していた香織が、既に先輩ペットの自覚をもたげて奈緒を励ました。
「…わ、分かりましたぁ…」
奈緒は恐る恐るといった様子で股間から手を離し、ゆっくりと上体を前傾させ、遂に腰と頭の位置を上下逆転させた体勢で、両足首を手で握った。
当然のごとく、大きく開かれた脚と今や頂点にある腰とで、恥ずかしい三角形が出来上がり、その頂上周辺には未成熟の少女には誰にも見せたくはないであろう生殖器と排泄器が、とうとう晋吾の眼前に晒されてしまった。
お風呂を共にした幼少の頃には、全く気にも留めていなかったその下半身は、今では晋吾の背徳心を強烈に刺激するほどの変貌を遂げていた。
比較的濃い目と思われる陰毛は、まだ誰にも犯されていないピンク色の秘所の周りを縁取り、そのまま細々とアナル周囲まで達している。
「ん~~、見た目には病気などは無さそうだが、中の方も確認しないと分からないからな。奈緒、何をされてもそのままじっとして動くんじゃないぞ」
「…は、はいぃ…」
恥ずかしさからなのか、逆さまになっている頭に血が上り始めているからなのか、奈緒は顔をすっかり赤らめながら、相変わらずの消え入りそうな声で、じっとその恥ずかしすぎる体勢を維持している。
そんな奈緒の様子などお構いもせず、晋吾はその秘所に鼻を押し付けるかのごとく近づけて、クンクンと匂いを嗅ぎ始めた。
まだうら若き乙女の大事な部分の匂いを堂々と嗅ぐ…その甘い刺激臭と強烈な支配感に、脱衣ショーの時から既に屹立していた晋吾の一物は、更にその膨張の度合いを高めていく。
既に入浴を済ませた後の股間は、生々しい女性器の匂いこそ放ってはいないが、多分入浴後にオシッコはしたのであろう…わずかなアンモニア臭は残っていた。
「香織、ちょっと中も調べたいので、滑りやすくなるようにここをよーく舐めてあげてよ」
「はい。わかりました」
奈緒は、晋吾と香織のそんなやりとりに驚いたらしく、逆さまの顔を赤らめたまま、
「…え!?、えぇーっ!?」
「奈緒はそのまま動かないこと。いいね?飼い主の言いつけだぞ」
そう言っている傍から、横に控えていた香織は、自分の顔の目の前に奈緒の股間が迫る位置に座り込み、小ぶりではあるがピチピチとした瑞々しい桃を連想させるお尻を両手で押さえると、自分の顔を押し付けんばかりにして、奈緒の恥ずかしい部分を舐め始めた。
「ひゃぅっ!あっ、だ、だめぇっ!…あはぁぁぅぅ…あっ、あぅぅ…」
晋吾の眼前で、真っ裸の元美人人妻と、これまた真っ裸の元アイドル級女子高生のレズプレイが展開され始めた…。
(執筆継続中…)
妄想商会(21)~ポチの首輪〈第5話〉~*特殊アイテム
母親同士が友人関係ということから、晋吾とは小さい頃からの幼馴染であり、高校3年生の浅井奈緒を、朝の久々の偶発的な再会から、僅かその日の内に親元から引き離しペットとするという一大イベントを終え、今ようやく自宅に戻ってきた。
その手に握られた手綱の先には、首輪で繋がれた奈緒がいることは、言うまでもない。
「ただいまー。香織ー、いい子にしてたかー?」
「はーい♪ご主人様、お帰りなさい♪」
奥から待ちに待ち焦がれたという様子で、香織が元気よく出迎えに出てきた。
「あら?その“ヒト”は…?」
「ああ、今日からうちで飼うことになった“奈緒”だよ。これで香織のお留守番も寂しくなくなるだろ。仲良くするんだぞ」
「はい♪ご主人様、ありがとうございます♪…奈緒、よろしくね」
晋吾は彼の後ろに隠れるように立っていた奈緒を、香織の前に押し出して、
「ほらっ、奈緒もきちんと先輩にご挨拶…だろ」
「香織…よろしくお願いしますぅ…」
初めての環境にまだ順応し切れずに、少し不安げな様子で挨拶を交わした。
奈緒にとっては、まさに激動の一日だった。
彼女の人生に関わるなどというような、生易しいものではない。それまでの“人生”が終了し、新に取って付けの造語ではあるが“ヒト生”なるものがスタートする日になったのだから…。
須藤奈緒という名前も人間社会からは消え失せ、“奈緒”というペット名だけが残り、高校3年生という立場からの、進学または就職などという目先の将来の憂いや希望を持つ必要も無い。
ただ純粋に“新井晋吾の飼いヒト”という、可愛らしいペットの役目を果たしていけばいいのである。
もし飼い主に飽きられたり、見放されたりすれば、“野良ヒト”となるしかない運命を、新に授けられてしまったのである。
その新たな生き方を強制享受させられることとなった奈緒からは、つい数時間前の威勢のいい生意気娘の影は消え失せ、今はただオドオドするしかないというよな素振りである。
今後、彼女の記憶、性格、習性などは、全て晋吾による支配及び改定が施されることになるし、既に今もその改定が行われつつあった。
「じゃあ、奈緒、これでお前は我が家のペットとして仲間入りすることになったのだから、香織と同じように、俺のことはご主人様と呼ぶこと。いいね?それと返事はきちんと“はい”とか“いいえ”の丁寧な言い方にするように。いいね?」
「…はい、…ご主人様、わかりました」
「(おやおや、さっきまでのオタク扱いの呼び捨て口調が、随分としおらしくなったねー、奈緒。念願のペットの気持ちは、どんなだい?)」
黒い征服感を感じ、晋吾は“してやったり”という笑みを浮かべながら、
「では奈緒、早速だけど、我が家のペットとしては邪魔な、その着ているものを全部脱ぎなさい」
「えっ…で、でもぉ…」
「脱ぎなさい。香織も何も着てないだろ」
「い、嫌だよぉ…」
「何でだい?」
「…恥ずかしいから…」
この感覚は、香織には見られなかったものである。
それもそのはずで、香織には元から“羞恥心”というものは排除してあったのに対して、今回晋吾は奈緒にはその“羞恥心”だけは残しておくことに決めていたからである。
これは、それまでの自分に対する非礼の数々を行ってきた“生意気娘”への、ささやかな報復でもあった。
「脱ぎなさいっ!飼い主の言うことが聞けないなら、外に放り出して、野良ヒトにするぞ!」
晋吾は“わざと”語気を荒げた。
「ふぇっ…ふぇーん…」
果たして、奈緒は両手で顔を覆って泣き出してしまった。
しかし、この反応の中には、理不尽なことを強要されたことによる恐怖心や憎しみなどの感情は含まれていない。ただ純粋に“恥ずかしい”だけなのだ。
なので、これは“教育”や“躾”という方法で、矯正させる必要があり、また奈緒もいずれそれを享受出来るはずである。
「ほら、脱ぎなさいっ!」
「奈緒、頑張って」
香織もこれが躾であることは十分に理解できているので、奈緒を庇うよりも、励ますように彼女の肩を抱いている。
「ふぇーん…ふぇっ、ふぇっ…ひっく…」
18歳の乙女が、その若さ溢れる可愛らしい顔を涙で濡らしながら、ようやく観念したのか、Tシャツに手をかけ、スルスルと脱ぎ始めた。
Tシャツの下には淡い色の薄手の綿キャミソールを着ており、それすらも脱ぎ去ると、香織のそれよりも若さの分だけ若干の固さが見受けられる、ツンと上向きの乳房が顕わになった。それは乳輪も小さめで桜色の乳首を持ち、まだ完全成熟はしていないまでも、美乳と言われる部類のものであろう。
こんな恥ずかしい行為は早く済ませてしまいたいのか、奈緒はそのまま多少慌てるような素振りで、ショートパンツに手をかけ、一気に下ろしていくと、可愛い縁取りで飾られたピンク色の綿ショーツが晋吾の目に飛び込んできた。
あれほどさっきまでの言動が気に障っていた奈緒だが、こうして恥らいながらの脱衣ショーを見せ付けられると、当然のことながら、彼の一物は素直に反応し、熱く固い肉棒へ変貌している。
奈緒は立て続けにその綿ショーツも脱ぎ去り、完全な裸体少女となってしまった。
彼女の下半身のデルタ地帯は、ギュッと固く両脚を閉じられているので、その中心部分こそまだ未知の領域ではあるが、今視界に広がるそこは、上のまだ未成熟の美乳とは打って変わっての成熟した陰毛地帯を呈しており、統計比較こそしたことはないが、晋吾が知っている範囲の平均値で言えば、“毛深い”という評価を与えられるものであった。
「(へー、子どもの頃に一緒にお風呂に入っていた時には何も生えていなかったアソコは、こんなにもいやらしい成長をしていたのかぁ。奈緒、卑猥な毛深さだよー。それにしても、あのムカツク女だったのが、今やこんなになっちゃって…)」
そんな感慨に耽りながら一連の脱衣ショーを見物した晋吾の目を避けるかのように、
「…ふぇっ、ふぇっ…ひっく…」
奈緒はまだベソをかきながら、両手で胸と下半身全部のデルタ地帯を覆い隠し、両脚をきつく閉めて、出来るだけ自身の裸体露出面積を狭くしようと、懸命になっている。
(ポチの首輪<第6話>に続く…)
その手に握られた手綱の先には、首輪で繋がれた奈緒がいることは、言うまでもない。
「ただいまー。香織ー、いい子にしてたかー?」
「はーい♪ご主人様、お帰りなさい♪」
奥から待ちに待ち焦がれたという様子で、香織が元気よく出迎えに出てきた。
「あら?その“ヒト”は…?」
「ああ、今日からうちで飼うことになった“奈緒”だよ。これで香織のお留守番も寂しくなくなるだろ。仲良くするんだぞ」
「はい♪ご主人様、ありがとうございます♪…奈緒、よろしくね」
晋吾は彼の後ろに隠れるように立っていた奈緒を、香織の前に押し出して、
「ほらっ、奈緒もきちんと先輩にご挨拶…だろ」
「香織…よろしくお願いしますぅ…」
初めての環境にまだ順応し切れずに、少し不安げな様子で挨拶を交わした。
奈緒にとっては、まさに激動の一日だった。
彼女の人生に関わるなどというような、生易しいものではない。それまでの“人生”が終了し、新に取って付けの造語ではあるが“ヒト生”なるものがスタートする日になったのだから…。
須藤奈緒という名前も人間社会からは消え失せ、“奈緒”というペット名だけが残り、高校3年生という立場からの、進学または就職などという目先の将来の憂いや希望を持つ必要も無い。
ただ純粋に“新井晋吾の飼いヒト”という、可愛らしいペットの役目を果たしていけばいいのである。
もし飼い主に飽きられたり、見放されたりすれば、“野良ヒト”となるしかない運命を、新に授けられてしまったのである。
その新たな生き方を強制享受させられることとなった奈緒からは、つい数時間前の威勢のいい生意気娘の影は消え失せ、今はただオドオドするしかないというよな素振りである。
今後、彼女の記憶、性格、習性などは、全て晋吾による支配及び改定が施されることになるし、既に今もその改定が行われつつあった。
「じゃあ、奈緒、これでお前は我が家のペットとして仲間入りすることになったのだから、香織と同じように、俺のことはご主人様と呼ぶこと。いいね?それと返事はきちんと“はい”とか“いいえ”の丁寧な言い方にするように。いいね?」
「…はい、…ご主人様、わかりました」
「(おやおや、さっきまでのオタク扱いの呼び捨て口調が、随分としおらしくなったねー、奈緒。念願のペットの気持ちは、どんなだい?)」
黒い征服感を感じ、晋吾は“してやったり”という笑みを浮かべながら、
「では奈緒、早速だけど、我が家のペットとしては邪魔な、その着ているものを全部脱ぎなさい」
「えっ…で、でもぉ…」
「脱ぎなさい。香織も何も着てないだろ」
「い、嫌だよぉ…」
「何でだい?」
「…恥ずかしいから…」
この感覚は、香織には見られなかったものである。
それもそのはずで、香織には元から“羞恥心”というものは排除してあったのに対して、今回晋吾は奈緒にはその“羞恥心”だけは残しておくことに決めていたからである。
これは、それまでの自分に対する非礼の数々を行ってきた“生意気娘”への、ささやかな報復でもあった。
「脱ぎなさいっ!飼い主の言うことが聞けないなら、外に放り出して、野良ヒトにするぞ!」
晋吾は“わざと”語気を荒げた。
「ふぇっ…ふぇーん…」
果たして、奈緒は両手で顔を覆って泣き出してしまった。
しかし、この反応の中には、理不尽なことを強要されたことによる恐怖心や憎しみなどの感情は含まれていない。ただ純粋に“恥ずかしい”だけなのだ。
なので、これは“教育”や“躾”という方法で、矯正させる必要があり、また奈緒もいずれそれを享受出来るはずである。
「ほら、脱ぎなさいっ!」
「奈緒、頑張って」
香織もこれが躾であることは十分に理解できているので、奈緒を庇うよりも、励ますように彼女の肩を抱いている。
「ふぇーん…ふぇっ、ふぇっ…ひっく…」
18歳の乙女が、その若さ溢れる可愛らしい顔を涙で濡らしながら、ようやく観念したのか、Tシャツに手をかけ、スルスルと脱ぎ始めた。
Tシャツの下には淡い色の薄手の綿キャミソールを着ており、それすらも脱ぎ去ると、香織のそれよりも若さの分だけ若干の固さが見受けられる、ツンと上向きの乳房が顕わになった。それは乳輪も小さめで桜色の乳首を持ち、まだ完全成熟はしていないまでも、美乳と言われる部類のものであろう。
こんな恥ずかしい行為は早く済ませてしまいたいのか、奈緒はそのまま多少慌てるような素振りで、ショートパンツに手をかけ、一気に下ろしていくと、可愛い縁取りで飾られたピンク色の綿ショーツが晋吾の目に飛び込んできた。
あれほどさっきまでの言動が気に障っていた奈緒だが、こうして恥らいながらの脱衣ショーを見せ付けられると、当然のことながら、彼の一物は素直に反応し、熱く固い肉棒へ変貌している。
奈緒は立て続けにその綿ショーツも脱ぎ去り、完全な裸体少女となってしまった。
彼女の下半身のデルタ地帯は、ギュッと固く両脚を閉じられているので、その中心部分こそまだ未知の領域ではあるが、今視界に広がるそこは、上のまだ未成熟の美乳とは打って変わっての成熟した陰毛地帯を呈しており、統計比較こそしたことはないが、晋吾が知っている範囲の平均値で言えば、“毛深い”という評価を与えられるものであった。
「(へー、子どもの頃に一緒にお風呂に入っていた時には何も生えていなかったアソコは、こんなにもいやらしい成長をしていたのかぁ。奈緒、卑猥な毛深さだよー。それにしても、あのムカツク女だったのが、今やこんなになっちゃって…)」
そんな感慨に耽りながら一連の脱衣ショーを見物した晋吾の目を避けるかのように、
「…ふぇっ、ふぇっ…ひっく…」
奈緒はまだベソをかきながら、両手で胸と下半身全部のデルタ地帯を覆い隠し、両脚をきつく閉めて、出来るだけ自身の裸体露出面積を狭くしようと、懸命になっている。
(ポチの首輪<第6話>に続く…)
妄想商会(20)~ポチの首輪〈第4話〉~*特殊アイテム
翌朝、晋吾はまだ眠い目をこすりながら、新しく日課になった香織の排泄用の散歩に出かけた。
今度はキチンと排泄物をすくうスコップと、それを入れるビニール袋を忘れずに持ってである。
目的の公園にたどり着くと、香織はすでに便意を堪えていたらしく、
「あの…ご主人様、早くしたいです」
と、苦しそうな顔で訴えかけてきた。
「じゃあ、ここでしなさい」
そう言って、園内の歩道沿いの木陰を指差した。
「はい」
言うなり、香織はしゃがみ込み、何の憂いも無く息み始めた。
程なくして、プスッ!ブーッ!プリプリ…とうら若き美女には恥極まりない排泄音を高鳴らせ、心地よさそうな顔で用を足し始める。
朝の公園は、通勤通学の人々や、ジョギングや犬の散歩の人々など、それなりに人がいる。
当然香織が用を足しているすぐ脇を、何人もの人が往来していく。
その片隅で、誰が見ても美女の部類に入る香織が、真っ裸でいながらも、バッチリとヘアースタイルとメイクを整えて、尚且つ臭い排泄を行っている様は、誰がどう見ても異様で破廉恥な光景だが、今は事情が違う。何度も言うが、これはペットを飼育する上での絶対条件なのだ。周囲もそれを当たり前と認知しているので、別にどうと言うことはない世界なのである。
顔と身体の割には立派な排泄物を吐き出し、それを晋吾に処理させた香織は、本当にスッキリした顔で帰りの散歩を楽しもうとしているようだ。
しかし、彼女の肛門の周りは、まだ汚れたままなのだが、これはペットなのだからご丁寧に拭いてやる必要無し…との晋吾の判断である。
帰宅後に、玄関先で水洗いしてやることにしているので、帰り道は汚いオシリのまま歩き回されることになる。
そんな香織を連れて帰途に着いた道すがら、
「あれ、晋吾じゃん」
家の近くの交差点で、聞き覚えのある声で呼び止められた。
「こんな朝早くから晋吾に会うなんて、めずらしいねー。オタクは朝苦手なんじゃないの?」
朝から小生意気な挨拶を投げかけてくる相手は、つい最近まで近所に住んでいた家族の一人娘で、現在高校3年生のはずの“浅井奈緒(あさい なお)”だった。
現在は、以前住んでいた所から程遠くないところに建った新築マンションを購入し、そっちに引っ越したのだ。
幼馴染み…ということもあってか、気兼ね無くは話し掛けてくるのだが、何かと話題が欲しい女子高生にとっては“オタク系”という種族は、面白おかしいネタ部門では役に立つらしく、最近では晋吾を見ると、からかう対象でしかなく、その反応を「ねーねー、ウチの近所に前から知ってるオタクがいてさー」などと、友達との会話のネタにしているらしかった。
「なんだ、奈緒か。おはよ」
「何連れてんの?ペット?まさか飼ったの?」
「ああ、悪いか?」
「アハハハッ、可愛そうなペットちゃん。晋吾に飼われるなんてねー、ちゃんと世話できるの?」
「うるさいな、今だってこうやってちゃんと散歩してるだろ」
「あんたって前から飽きっぽかったじゃない。そのうち捨てられなきゃいいけどねー」
「えっ!?捨てられるって…私がですか?」
「きゃっ!このペット話しが出来るの??」
「あ、あぁ、一応ヒト科のヒトだからな。日常会話くらいはできるよ」
「へー、めずらしい生き物飼ったね。名前は?」
「香織です」
「これ、メスでしょ?まぁ、前からモテない晋吾だったから、メスのペットで慰めてもらってるわけね」
「奈緒、いい加減早く学校行けよ」
「はいはい、っじゃあね。香織、晋吾はちょっとキモイしウザイけど、我慢して飼ってもらってねー」
「あ、…あのぉ…」
「ほら、香織だって返事に困ってるじゃんか。お前朝からうるさいよ。早く行けよ」
半ば追い払うようにして奈緒を遠ざけ、急ぎ早に再び帰途に着いた。
ショートヘアが似合う可愛い顔立ちのくせして、中身は小悪魔的な残忍さを持ち合わせてるんじゃないのか…と、胸の中で恨み言を繰り返しているうちに、
「(でも少し見ないうちに奈緒もそれなりに女になってたな… ………そうか…)」
胸の中でニヤリとする自分がいることに、晋吾も気付いていた。
「(モテないオタクに飼われるペットが可哀相?…ふーん…じゃあ、その気分を実際に味わってみる?…フフフ…)」
黒い企みが、晋吾の胸の中で急速に膨れ上がっていった。
その日の夕方…。
日中に授業そっちのけであれやこれやと考えた策を、実行に移すべく、晋吾は奈緒の自宅マンションへと向かった。
何しろ、この便利な首輪にも弱点があった。
それは“どのようにして首輪を巻かせるか”である。
香織の時は、シルクがその魔力で救ってくれたが、今回はどうやら自力で実行しなければならないようだ。
何度もシルクを呼び出そうと試みたが、どうやらそのコミュニケーションは、一方通行限定なようで、こちらから彼を呼び出す術は無かった。
初期投資はするが、後は自分で開拓せよ…の方針なのか。何やらベンチャー事業に投資する投資家のようである。
さて、奈緒の自宅マンション前まで辿り着いた時には、既に辺りは初夏の日が長い夕方とは言え、薄暗くなってきていた。
奈緒は既に帰宅しているはずの時間なのだが、晋吾は入口付近でひたすら誰かを待っているようである。
しばらくして、そのお目当ての人物が向こうから歩いてきた。
奈緒の母親である。
奈緒の家は晋吾の親と同じく共働き家庭で、父親の帰宅はいつも深夜近くということは、長年の近所付き合いで承知していることである。
「あ、おばさん。こんばんは。お久しぶりです」
「あらー、晋ちゃんじゃない。ひさしぶりねー、元気してた?洋子ちゃんはまだ帰ってないんでしょ?」
“洋子”というのは、晋吾の母親の名前であり、奈緒の母親と晋吾の母親とは、単なるご近所さんという間柄ではなく、実はこれまた学生時代からの幼馴染みだったのである。
なので、晋吾と奈緒も幼少の頃から一緒に遊ばされる事も多く、海外出張が多い晋吾の家庭を気遣ってか、幾度となく奈緒の家に寝泊りさせてもらったこともあった。
「ええ、両親はまだ帰国してません。でも、うちの母親からおばさん宛に、現地からおみやげが届いていたのを渡すのを忘れてしまっていて…」
「あら、そうだったのー。それなら電話してくれればいいのに。ずっとここで待ってたんでしょ?…ははぁ、奈緒が電話に出るのが嫌なのねー。あの子、最近特に生意気なことばかり口にするから」
「ははは…ま、まぁ、そんなとこです…」
少し恐縮気味に返事をしたが、確かにそれも本音の一つではあるが、一番の本音は彼女の次の言葉を待つためであった。果たして、
「でも、わざわざありがとね。あ、晋ちゃん、もう夜ご飯食べたの?まだだったら、うちで食べて行きなさいよ。いつも一人きりで寂しいでしょう」
「あ、は、はい…実はまだなんです。でも、ご迷惑じゃないですか?」
「何言ってるのよ。ちょっと前まではいつもそうしていたでしょう。うるさい娘がいるのは我慢してね。それにどうせうちの人は帰り遅いし」
「じゃあ、お言葉に甘えて…」
そう、これである。このタイミングを待つために、こんな薄暗い時間を選んで、ここに来たのだ。
こうなることは、これまでの経験でよく分かっていた。
このおばさんが、夕食時間に訪れた晋吾を、そのまま帰すわけがなく、これが一番自然に奈緒に近づく手段であったからだ。
「ただいまー。奈緒、帰ってるんでしょー?」
「おかえりー」
奥の方から返事はするが、母親の帰宅に出迎えもしない、生意気娘である。
まぁ、年頃の子供を持つ家庭では、ごく当たり前の風景だろう。
「さ、遠慮せず上がって」
「はい、お邪魔します」
母親に連れ立って家の中を進むと、キッチンの奥のリビングで、奈緒がソファに座ってテレビを見ていた。
ついさっきお風呂から上がった様子の洗い流しのままの髪に、首にはまだタオルをかけたままで、Tシャツにショートパンツといった、完全な部屋着スタイルに、思わずドキッとする色気を感じてしまったのは、奈緒の身体の成長によるものなのか、それともこれから起こそうといている、黒い欲望のせいなのか…。
「げっ!何で晋吾が一緒なわけ!?やぁー、もぉー、最低!」
「奈緒!、もう、久しぶりに来てくれた晋ちゃんに向かって、そんなこと言うものじゃないわよっ」
「今日の朝だって会っちゃったもん。はぁ…二度も晋吾に会うなんて…今日はツイてない日だわぁ…」
このクソ生意気な物言いに、晋吾は張り倒してやりたい衝動に駆られたが、ぐっと堪えた。
この後の計画のこともあるが、何よりも奈緒は幼い頃から合気道を習っているので、幼少時もよく泣かされたのに、成長した現段階で、格闘においての晋吾の勝ち目など、万に一つもないであろう。
「あら、今朝、奈緒と会ったの?」
「はい、朝、外でばったり会ったんですよ」
「で、何で晋吾がこんな時間にうちに来るのよー」
思い切り不満そうな顔で、奈緒は母親に噛み付いている。
「ほら、これ。洋子さんがお土産送ってくれたのを、わざわざ届けてくれたのよ」
「ふーん…って、これ、送付の日付が一ヶ月も前じゃん。どーせ晋吾のことだから、部屋に置きっ放しで忘れてたんでしょ」
図星である。
きっとこんな展開にならなければ、このまま忘れ続けていたかもしれないくらいに、晋吾にとっては面倒でどうでもいい代物だったのだが、思案の挙句、今は目的のための大変貴重な“コミュニケーション・アイテム”になっていた。
「晋ちゃんだって、毎日学校とか家のこととかで一人で大変なのよ。でも、思い出して届けてくれただけ偉いじゃない」
「ふーん、で、こんな晩ご飯時間に一人で来るなんて、“愛しの香織ちゃん”のお世話は大丈夫なわけ?」
皮肉たっぷりの口調で、奈緒が口を挟む。
「香織…ちゃん?えっ!?もしかして晋ちゃん、ガールフレンドできたのー!?」
「ちっ、違いますよ!ペットですよ!ペットを飼い始めたんです。つい最近ですけど」
「へー、香織って言う名前なの?何か人の名前みたいねー。メスのワンちゃん?」
「え、えーっと、…ヒト科のヒトなんです」
「ヒト??えっ、…あ、あぁ、“ヒト”ねー。まためずらしいものを飼ったのねー。お世話って大変なの?」
「いえいえ、言葉もある程度話せますし、飼うのはすごく楽ですよ」
ペットの種類を聞かれて、晋吾は些か動揺したが、やはりシルクの環境変化能力は大したものである。
ここまで来ると、もう誰に話しても“ヒト科のヒト”という、人間社会とは別の種の“ヒト”がこの世界には存在していることが当然なのだと、図々しく認識できた。
いずれ、テレビの動物番組などでも取り上げられる日も、そう遠くないかもしれないと、少し馬鹿げた発想が頭を過ぎった瞬間に、再び奈緒が生意気な口を挟んできた。
「世話が楽って、ズボラな晋吾にはピッタリのペットだよねー。それも、メスのヒトなんて、まるで“僕はいつも寂しいので、慰めて欲しいよー”って言ってるようなものだよね」
「奈緒、お前なー…」
あまりにも図星の部分を突かれて、さすがに腹が立つ。
まぁ、いいさ、もうすぐお前にも慰めてもらうんだから…と、自分に言い聞かせることにした。
「ほらほら、久しぶりに会って言い争いはしないの!ご飯にするわよ」
おばさんの仲裁で、ようやく3人での食事となった。
3人での食事をしながら、晋吾は内心で「こんな親子の関係を“無”にするのは、ちょっと気の毒な気もするけど…まぁ、変化があったからといっても、悲しみが伴うわけではないし…こんないいおばさんには悪いけど、奈緒のことはちゃんと世話するから許してね」などと、すっかりダークな思想が板に付いたようなことを考えながら、“その瞬間”のタイミングを待っていた。
果たして、食事も終わり、食後のお茶を頂いていると、
「で、晋吾、アンタいつまでうちにいるつもり?」
と、奈緒があからさまに“早く帰れコール”を浴びせてきた。
「奈緒、久しぶりに来てくれたんだから、ゆっくりしてもらったっていいじゃない。あなただって、以前はよく遊んでもらったでしょう」
「えー、だってぇー、晋吾って何かキモイんだもん。どーせ連れてくるなら、もっとイケメンでも連れてきてよ」
「キモくて悪かったな!」
ホントに腹が立つ小娘である。
まぁまぁ…と、自分をなだめる心の操作にも、幾分疲れてきた。
「そりゃあ、イケメンの方がいいだろうけどさ、奈緒、お前彼氏の一人でもいないわけ?」
「彼氏?…アハハハ、特定の男なんて面倒くさいじゃん。そ・れ・にぃー、私くらいのレベルだったら、その気になればいつでも作れるから、別にまだいらなーい。適当に遊べる相手だけでいいのっ」
「お前…完全に世の中舐めてるな」
「いいでしょ。アンタと違って器量的には恵まれた者の特権よー」
そんな性格だから、誰も本気で付き合ってくれないんだよ!と、心の中で悔し紛れの文句を叫びながら、表面では穏やかに、
「ハハハ…。確かに俺よりかは苦労は無さそうだもんな。そうそう、これやる?」
そう言って、鞄から一つのゲームソフトを取り出した。
「あ、これって、最近出たばかりのやつじゃんっ!もう買ったんだー、さすがオタクよねーっ」
「一言余計だよ。ちょっとやってみる?」
「やるっやるぅっ!」
言うなり、奈緒は部屋からゲーム機を持ってきて、早速ゲームに浸り始めた。
奈緒のゲーム好きは、今も昔も変わりないようである。
「ねーねー、ここはどうするの?」
「ん?あぁ、そこはね…」
「まぁ、こう言う時だけ仲がいいのねー、晋ちゃん、ゆっくりしていってね。おばさん、ちょっとお風呂頂くわ」
「あ、すみません、適当に帰りますので。どうもごちそうさまでした」
これも都合よく、おばさんがこの場から離れてくれた。
後は、“その時”を待つばかりである。
それから少しの間ゲームに没頭してた奈緒であるが、急に目がうつろになり、頭をカクンカクンとさせはじめた。
「ふわぁぁ…何かすごく眠くなってきちゃったぁ…。晋吾、私、もう寝るわ。おやすみー」
少しフラフラフワフワした足どりで、別れの挨拶も適当に、奈緒は自分の部屋に入っていった。
ついに“その時”が訪れたのである。
それも、おばさんが入浴中というナイスなタイミングで…。
実は先程の食後のティータイムで、食後のせめてものお礼に…ということで、晋吾がお茶を入れに行ったのだが、その際、奈緒のお茶にだけ、砕いて粉にしておいた睡眠薬を混入させておいたのだ。
睡眠薬は、晋吾の両親が長旅でのストレスによる不眠症対策でいつも常備していたのを、知っていたので、思案の末思いついた方法が、それの使用であった。
奈緒が部屋に入ってから数分後、そーっと彼女の部屋を覗いてみると、思惑通りに奈緒は既にベッドで眠りについていた。
ニヤリ…晋吾の目が怪しく光り、寝ている奈緒に近づいていった。当然のことながら、その手にはしっかりと“首輪”が握られている。
奈緒の枕元に立つと、そーっと数回彼女の肩を揺すってみた。…反応無し。
いよいよである。
改めて奈緒を上から見下ろし、
「(奈緒、これからお前の人生は“ヒト生”に変るんだよ。もう俺の前ではさっきみたいな生意気な態度は出来ないし、俺から離れたら、単なる“野良ヒト”になってしまうんだよ。この家やこの部屋、このベッドで寝るのも、これが最後だ。朝、あれだけ惨めだと罵った“ヒト科のヒト”のペットになる時がきたんだよ…)」
と、心の中でつぶやきながら、彼女の首に首輪を巻きつけ、そして金具を止めた。
次の瞬間…。
ブンッ!と一瞬、めまいと言うか、時空の歪みみたいな現象が起きたかと思うと、すぐに止んだ。
香織をペットにした瞬間と同じ現象だったので、晋吾にはもう動揺などなく、その後の変化も“予想通り”という態で周囲を見渡していた。
そこは…。
先程の奈緒の部屋ではない。単なる何も無い空き部屋になっていた。部屋の片隅には、おばさんとおじさんの物であろうと思われるゴルフバッグが二つ置かれていたり、何が入っているのか分からないダンボール箱が数箱積まれているだけ…という殺風景な部屋である。
どうやら、荷物置き場という役割だけの部屋のようだ。
首輪を巻かれた奈緒はというと、その部屋の床に、ただ転がって寝ていた。
後は状況整理である。
もうこの家に奈緒という娘がいた事実は“無”になっているので、このまま奈緒がここに寝ていては、状況の辻褄が合わなくなる。
“ペットを無断で家の中に連れ込んだ”という、この家の主に対して非常に失礼な既成事実が出来上がってしまうからだ。
なので、寝ていることでかなり重くなっている奈緒の身体を、音を立てないように玄関の外まで運び出し、首輪に付けた引き綱と、通路に面している窓の柵とを繋いで、そこに寝かせた。
マンションの建物内にペットを連れ込んだということだけが、マンションのルールに少し抵触するかもしれないが、まぁ、その辺は家の中に入れなかったことだけでも、大目に見て欲しいところである。
再び家の中に今度は晋吾だけが戻り、リビングで待つことにして程なく、おばさんがお風呂から上がってきた。
「あら、晋ちゃん、一人で待たせちゃってごめんなさいねー。もう眠くなっちゃったんじゃない?」
「あ、いえいえ、大丈夫です。ご飯までご馳走になって、何も言わずに帰ることもできないので…。今夜は本当にご馳走様でした。おいしかったです」
「こちらこそ、お粗末様でした。またいつでも遠慮なく食べに来てね。ほら、どーせおばさんはいつも“一人で”食事だし…。あの人ったら、まーだ帰って来ないのよねー」
「おじさん、いつも遅いですもんね。…では帰ります」
「あら、そう。じゃあ、玄関まで送っていくわ」
そう言って、彼女が晋吾を送り出しに玄関外まで出てみると、そこには奈緒が今だ寝ており、
「あらっ!あ、これが晋ちゃんのペットなの?食事の間、ずっとここにいたの?」
「ハハハ…、すみません。ペットですから、家の中に入れるわけにもいかないし、一階の入口に置いておくのも心配だったので、ここまで連れてきちゃいました。ごめんなさい」
「いえいえ、それはいいのだけれど…これがさっき話していた“香織ちゃん”?」
「違います。これはもう一人の“奈緒”という名前の方です。二人飼っているので」
「そうなのー。へー、ヒト科のヒトなんて初めて見たわ。けっこう可愛いのねー」
「ありがとうございます」
礼を述べながら、少し乱暴に奈緒を揺り動かし、
「ほらっ、奈緒!起きなさい!帰るぞ!」
「んっ、うっ、うぅーん…」
まだ薬の効果で朦朧としながらも、それでも健気に立ち上がり、
「ん!?…帰るの?」
と、寝ぼけ眼で反応してきた。
「あぁ、帰るよ。ほら、おばさんにご挨拶は?」
「ふぁーぃ…おばさま、おやすみなしゃい…」
「あら、上手におしゃべりできるのねー。ヒトだったら、今度は家の中に入れてもいいから、また連れてきていいわよ」
「はい。ありがとうございます。では、おやすみなさい」
別れの挨拶を済ませ、まだ少し千鳥足の奈緒の手綱を引きながら、晋吾の家への家路についた。
おばさんと奈緒…これまでの親子関係は、今のやりとりでも明白なように、それまでの全てが“無”になっていた。
首輪に繋がれた“元愛娘”を、今は笑顔で手を振りながら送り出している彼女の姿を背中に感じながら、晋吾と新ペットの奈緒は、エレベーターの中に消えていった。
(ポチの首輪<第5話>に続く…)
今度はキチンと排泄物をすくうスコップと、それを入れるビニール袋を忘れずに持ってである。
目的の公園にたどり着くと、香織はすでに便意を堪えていたらしく、
「あの…ご主人様、早くしたいです」
と、苦しそうな顔で訴えかけてきた。
「じゃあ、ここでしなさい」
そう言って、園内の歩道沿いの木陰を指差した。
「はい」
言うなり、香織はしゃがみ込み、何の憂いも無く息み始めた。
程なくして、プスッ!ブーッ!プリプリ…とうら若き美女には恥極まりない排泄音を高鳴らせ、心地よさそうな顔で用を足し始める。
朝の公園は、通勤通学の人々や、ジョギングや犬の散歩の人々など、それなりに人がいる。
当然香織が用を足しているすぐ脇を、何人もの人が往来していく。
その片隅で、誰が見ても美女の部類に入る香織が、真っ裸でいながらも、バッチリとヘアースタイルとメイクを整えて、尚且つ臭い排泄を行っている様は、誰がどう見ても異様で破廉恥な光景だが、今は事情が違う。何度も言うが、これはペットを飼育する上での絶対条件なのだ。周囲もそれを当たり前と認知しているので、別にどうと言うことはない世界なのである。
顔と身体の割には立派な排泄物を吐き出し、それを晋吾に処理させた香織は、本当にスッキリした顔で帰りの散歩を楽しもうとしているようだ。
しかし、彼女の肛門の周りは、まだ汚れたままなのだが、これはペットなのだからご丁寧に拭いてやる必要無し…との晋吾の判断である。
帰宅後に、玄関先で水洗いしてやることにしているので、帰り道は汚いオシリのまま歩き回されることになる。
そんな香織を連れて帰途に着いた道すがら、
「あれ、晋吾じゃん」
家の近くの交差点で、聞き覚えのある声で呼び止められた。
「こんな朝早くから晋吾に会うなんて、めずらしいねー。オタクは朝苦手なんじゃないの?」
朝から小生意気な挨拶を投げかけてくる相手は、つい最近まで近所に住んでいた家族の一人娘で、現在高校3年生のはずの“浅井奈緒(あさい なお)”だった。
現在は、以前住んでいた所から程遠くないところに建った新築マンションを購入し、そっちに引っ越したのだ。
幼馴染み…ということもあってか、気兼ね無くは話し掛けてくるのだが、何かと話題が欲しい女子高生にとっては“オタク系”という種族は、面白おかしいネタ部門では役に立つらしく、最近では晋吾を見ると、からかう対象でしかなく、その反応を「ねーねー、ウチの近所に前から知ってるオタクがいてさー」などと、友達との会話のネタにしているらしかった。
「なんだ、奈緒か。おはよ」
「何連れてんの?ペット?まさか飼ったの?」
「ああ、悪いか?」
「アハハハッ、可愛そうなペットちゃん。晋吾に飼われるなんてねー、ちゃんと世話できるの?」
「うるさいな、今だってこうやってちゃんと散歩してるだろ」
「あんたって前から飽きっぽかったじゃない。そのうち捨てられなきゃいいけどねー」
「えっ!?捨てられるって…私がですか?」
「きゃっ!このペット話しが出来るの??」
「あ、あぁ、一応ヒト科のヒトだからな。日常会話くらいはできるよ」
「へー、めずらしい生き物飼ったね。名前は?」
「香織です」
「これ、メスでしょ?まぁ、前からモテない晋吾だったから、メスのペットで慰めてもらってるわけね」
「奈緒、いい加減早く学校行けよ」
「はいはい、っじゃあね。香織、晋吾はちょっとキモイしウザイけど、我慢して飼ってもらってねー」
「あ、…あのぉ…」
「ほら、香織だって返事に困ってるじゃんか。お前朝からうるさいよ。早く行けよ」
半ば追い払うようにして奈緒を遠ざけ、急ぎ早に再び帰途に着いた。
ショートヘアが似合う可愛い顔立ちのくせして、中身は小悪魔的な残忍さを持ち合わせてるんじゃないのか…と、胸の中で恨み言を繰り返しているうちに、
「(でも少し見ないうちに奈緒もそれなりに女になってたな… ………そうか…)」
胸の中でニヤリとする自分がいることに、晋吾も気付いていた。
「(モテないオタクに飼われるペットが可哀相?…ふーん…じゃあ、その気分を実際に味わってみる?…フフフ…)」
黒い企みが、晋吾の胸の中で急速に膨れ上がっていった。
その日の夕方…。
日中に授業そっちのけであれやこれやと考えた策を、実行に移すべく、晋吾は奈緒の自宅マンションへと向かった。
何しろ、この便利な首輪にも弱点があった。
それは“どのようにして首輪を巻かせるか”である。
香織の時は、シルクがその魔力で救ってくれたが、今回はどうやら自力で実行しなければならないようだ。
何度もシルクを呼び出そうと試みたが、どうやらそのコミュニケーションは、一方通行限定なようで、こちらから彼を呼び出す術は無かった。
初期投資はするが、後は自分で開拓せよ…の方針なのか。何やらベンチャー事業に投資する投資家のようである。
さて、奈緒の自宅マンション前まで辿り着いた時には、既に辺りは初夏の日が長い夕方とは言え、薄暗くなってきていた。
奈緒は既に帰宅しているはずの時間なのだが、晋吾は入口付近でひたすら誰かを待っているようである。
しばらくして、そのお目当ての人物が向こうから歩いてきた。
奈緒の母親である。
奈緒の家は晋吾の親と同じく共働き家庭で、父親の帰宅はいつも深夜近くということは、長年の近所付き合いで承知していることである。
「あ、おばさん。こんばんは。お久しぶりです」
「あらー、晋ちゃんじゃない。ひさしぶりねー、元気してた?洋子ちゃんはまだ帰ってないんでしょ?」
“洋子”というのは、晋吾の母親の名前であり、奈緒の母親と晋吾の母親とは、単なるご近所さんという間柄ではなく、実はこれまた学生時代からの幼馴染みだったのである。
なので、晋吾と奈緒も幼少の頃から一緒に遊ばされる事も多く、海外出張が多い晋吾の家庭を気遣ってか、幾度となく奈緒の家に寝泊りさせてもらったこともあった。
「ええ、両親はまだ帰国してません。でも、うちの母親からおばさん宛に、現地からおみやげが届いていたのを渡すのを忘れてしまっていて…」
「あら、そうだったのー。それなら電話してくれればいいのに。ずっとここで待ってたんでしょ?…ははぁ、奈緒が電話に出るのが嫌なのねー。あの子、最近特に生意気なことばかり口にするから」
「ははは…ま、まぁ、そんなとこです…」
少し恐縮気味に返事をしたが、確かにそれも本音の一つではあるが、一番の本音は彼女の次の言葉を待つためであった。果たして、
「でも、わざわざありがとね。あ、晋ちゃん、もう夜ご飯食べたの?まだだったら、うちで食べて行きなさいよ。いつも一人きりで寂しいでしょう」
「あ、は、はい…実はまだなんです。でも、ご迷惑じゃないですか?」
「何言ってるのよ。ちょっと前まではいつもそうしていたでしょう。うるさい娘がいるのは我慢してね。それにどうせうちの人は帰り遅いし」
「じゃあ、お言葉に甘えて…」
そう、これである。このタイミングを待つために、こんな薄暗い時間を選んで、ここに来たのだ。
こうなることは、これまでの経験でよく分かっていた。
このおばさんが、夕食時間に訪れた晋吾を、そのまま帰すわけがなく、これが一番自然に奈緒に近づく手段であったからだ。
「ただいまー。奈緒、帰ってるんでしょー?」
「おかえりー」
奥の方から返事はするが、母親の帰宅に出迎えもしない、生意気娘である。
まぁ、年頃の子供を持つ家庭では、ごく当たり前の風景だろう。
「さ、遠慮せず上がって」
「はい、お邪魔します」
母親に連れ立って家の中を進むと、キッチンの奥のリビングで、奈緒がソファに座ってテレビを見ていた。
ついさっきお風呂から上がった様子の洗い流しのままの髪に、首にはまだタオルをかけたままで、Tシャツにショートパンツといった、完全な部屋着スタイルに、思わずドキッとする色気を感じてしまったのは、奈緒の身体の成長によるものなのか、それともこれから起こそうといている、黒い欲望のせいなのか…。
「げっ!何で晋吾が一緒なわけ!?やぁー、もぉー、最低!」
「奈緒!、もう、久しぶりに来てくれた晋ちゃんに向かって、そんなこと言うものじゃないわよっ」
「今日の朝だって会っちゃったもん。はぁ…二度も晋吾に会うなんて…今日はツイてない日だわぁ…」
このクソ生意気な物言いに、晋吾は張り倒してやりたい衝動に駆られたが、ぐっと堪えた。
この後の計画のこともあるが、何よりも奈緒は幼い頃から合気道を習っているので、幼少時もよく泣かされたのに、成長した現段階で、格闘においての晋吾の勝ち目など、万に一つもないであろう。
「あら、今朝、奈緒と会ったの?」
「はい、朝、外でばったり会ったんですよ」
「で、何で晋吾がこんな時間にうちに来るのよー」
思い切り不満そうな顔で、奈緒は母親に噛み付いている。
「ほら、これ。洋子さんがお土産送ってくれたのを、わざわざ届けてくれたのよ」
「ふーん…って、これ、送付の日付が一ヶ月も前じゃん。どーせ晋吾のことだから、部屋に置きっ放しで忘れてたんでしょ」
図星である。
きっとこんな展開にならなければ、このまま忘れ続けていたかもしれないくらいに、晋吾にとっては面倒でどうでもいい代物だったのだが、思案の挙句、今は目的のための大変貴重な“コミュニケーション・アイテム”になっていた。
「晋ちゃんだって、毎日学校とか家のこととかで一人で大変なのよ。でも、思い出して届けてくれただけ偉いじゃない」
「ふーん、で、こんな晩ご飯時間に一人で来るなんて、“愛しの香織ちゃん”のお世話は大丈夫なわけ?」
皮肉たっぷりの口調で、奈緒が口を挟む。
「香織…ちゃん?えっ!?もしかして晋ちゃん、ガールフレンドできたのー!?」
「ちっ、違いますよ!ペットですよ!ペットを飼い始めたんです。つい最近ですけど」
「へー、香織って言う名前なの?何か人の名前みたいねー。メスのワンちゃん?」
「え、えーっと、…ヒト科のヒトなんです」
「ヒト??えっ、…あ、あぁ、“ヒト”ねー。まためずらしいものを飼ったのねー。お世話って大変なの?」
「いえいえ、言葉もある程度話せますし、飼うのはすごく楽ですよ」
ペットの種類を聞かれて、晋吾は些か動揺したが、やはりシルクの環境変化能力は大したものである。
ここまで来ると、もう誰に話しても“ヒト科のヒト”という、人間社会とは別の種の“ヒト”がこの世界には存在していることが当然なのだと、図々しく認識できた。
いずれ、テレビの動物番組などでも取り上げられる日も、そう遠くないかもしれないと、少し馬鹿げた発想が頭を過ぎった瞬間に、再び奈緒が生意気な口を挟んできた。
「世話が楽って、ズボラな晋吾にはピッタリのペットだよねー。それも、メスのヒトなんて、まるで“僕はいつも寂しいので、慰めて欲しいよー”って言ってるようなものだよね」
「奈緒、お前なー…」
あまりにも図星の部分を突かれて、さすがに腹が立つ。
まぁ、いいさ、もうすぐお前にも慰めてもらうんだから…と、自分に言い聞かせることにした。
「ほらほら、久しぶりに会って言い争いはしないの!ご飯にするわよ」
おばさんの仲裁で、ようやく3人での食事となった。
3人での食事をしながら、晋吾は内心で「こんな親子の関係を“無”にするのは、ちょっと気の毒な気もするけど…まぁ、変化があったからといっても、悲しみが伴うわけではないし…こんないいおばさんには悪いけど、奈緒のことはちゃんと世話するから許してね」などと、すっかりダークな思想が板に付いたようなことを考えながら、“その瞬間”のタイミングを待っていた。
果たして、食事も終わり、食後のお茶を頂いていると、
「で、晋吾、アンタいつまでうちにいるつもり?」
と、奈緒があからさまに“早く帰れコール”を浴びせてきた。
「奈緒、久しぶりに来てくれたんだから、ゆっくりしてもらったっていいじゃない。あなただって、以前はよく遊んでもらったでしょう」
「えー、だってぇー、晋吾って何かキモイんだもん。どーせ連れてくるなら、もっとイケメンでも連れてきてよ」
「キモくて悪かったな!」
ホントに腹が立つ小娘である。
まぁまぁ…と、自分をなだめる心の操作にも、幾分疲れてきた。
「そりゃあ、イケメンの方がいいだろうけどさ、奈緒、お前彼氏の一人でもいないわけ?」
「彼氏?…アハハハ、特定の男なんて面倒くさいじゃん。そ・れ・にぃー、私くらいのレベルだったら、その気になればいつでも作れるから、別にまだいらなーい。適当に遊べる相手だけでいいのっ」
「お前…完全に世の中舐めてるな」
「いいでしょ。アンタと違って器量的には恵まれた者の特権よー」
そんな性格だから、誰も本気で付き合ってくれないんだよ!と、心の中で悔し紛れの文句を叫びながら、表面では穏やかに、
「ハハハ…。確かに俺よりかは苦労は無さそうだもんな。そうそう、これやる?」
そう言って、鞄から一つのゲームソフトを取り出した。
「あ、これって、最近出たばかりのやつじゃんっ!もう買ったんだー、さすがオタクよねーっ」
「一言余計だよ。ちょっとやってみる?」
「やるっやるぅっ!」
言うなり、奈緒は部屋からゲーム機を持ってきて、早速ゲームに浸り始めた。
奈緒のゲーム好きは、今も昔も変わりないようである。
「ねーねー、ここはどうするの?」
「ん?あぁ、そこはね…」
「まぁ、こう言う時だけ仲がいいのねー、晋ちゃん、ゆっくりしていってね。おばさん、ちょっとお風呂頂くわ」
「あ、すみません、適当に帰りますので。どうもごちそうさまでした」
これも都合よく、おばさんがこの場から離れてくれた。
後は、“その時”を待つばかりである。
それから少しの間ゲームに没頭してた奈緒であるが、急に目がうつろになり、頭をカクンカクンとさせはじめた。
「ふわぁぁ…何かすごく眠くなってきちゃったぁ…。晋吾、私、もう寝るわ。おやすみー」
少しフラフラフワフワした足どりで、別れの挨拶も適当に、奈緒は自分の部屋に入っていった。
ついに“その時”が訪れたのである。
それも、おばさんが入浴中というナイスなタイミングで…。
実は先程の食後のティータイムで、食後のせめてものお礼に…ということで、晋吾がお茶を入れに行ったのだが、その際、奈緒のお茶にだけ、砕いて粉にしておいた睡眠薬を混入させておいたのだ。
睡眠薬は、晋吾の両親が長旅でのストレスによる不眠症対策でいつも常備していたのを、知っていたので、思案の末思いついた方法が、それの使用であった。
奈緒が部屋に入ってから数分後、そーっと彼女の部屋を覗いてみると、思惑通りに奈緒は既にベッドで眠りについていた。
ニヤリ…晋吾の目が怪しく光り、寝ている奈緒に近づいていった。当然のことながら、その手にはしっかりと“首輪”が握られている。
奈緒の枕元に立つと、そーっと数回彼女の肩を揺すってみた。…反応無し。
いよいよである。
改めて奈緒を上から見下ろし、
「(奈緒、これからお前の人生は“ヒト生”に変るんだよ。もう俺の前ではさっきみたいな生意気な態度は出来ないし、俺から離れたら、単なる“野良ヒト”になってしまうんだよ。この家やこの部屋、このベッドで寝るのも、これが最後だ。朝、あれだけ惨めだと罵った“ヒト科のヒト”のペットになる時がきたんだよ…)」
と、心の中でつぶやきながら、彼女の首に首輪を巻きつけ、そして金具を止めた。
次の瞬間…。
ブンッ!と一瞬、めまいと言うか、時空の歪みみたいな現象が起きたかと思うと、すぐに止んだ。
香織をペットにした瞬間と同じ現象だったので、晋吾にはもう動揺などなく、その後の変化も“予想通り”という態で周囲を見渡していた。
そこは…。
先程の奈緒の部屋ではない。単なる何も無い空き部屋になっていた。部屋の片隅には、おばさんとおじさんの物であろうと思われるゴルフバッグが二つ置かれていたり、何が入っているのか分からないダンボール箱が数箱積まれているだけ…という殺風景な部屋である。
どうやら、荷物置き場という役割だけの部屋のようだ。
首輪を巻かれた奈緒はというと、その部屋の床に、ただ転がって寝ていた。
後は状況整理である。
もうこの家に奈緒という娘がいた事実は“無”になっているので、このまま奈緒がここに寝ていては、状況の辻褄が合わなくなる。
“ペットを無断で家の中に連れ込んだ”という、この家の主に対して非常に失礼な既成事実が出来上がってしまうからだ。
なので、寝ていることでかなり重くなっている奈緒の身体を、音を立てないように玄関の外まで運び出し、首輪に付けた引き綱と、通路に面している窓の柵とを繋いで、そこに寝かせた。
マンションの建物内にペットを連れ込んだということだけが、マンションのルールに少し抵触するかもしれないが、まぁ、その辺は家の中に入れなかったことだけでも、大目に見て欲しいところである。
再び家の中に今度は晋吾だけが戻り、リビングで待つことにして程なく、おばさんがお風呂から上がってきた。
「あら、晋ちゃん、一人で待たせちゃってごめんなさいねー。もう眠くなっちゃったんじゃない?」
「あ、いえいえ、大丈夫です。ご飯までご馳走になって、何も言わずに帰ることもできないので…。今夜は本当にご馳走様でした。おいしかったです」
「こちらこそ、お粗末様でした。またいつでも遠慮なく食べに来てね。ほら、どーせおばさんはいつも“一人で”食事だし…。あの人ったら、まーだ帰って来ないのよねー」
「おじさん、いつも遅いですもんね。…では帰ります」
「あら、そう。じゃあ、玄関まで送っていくわ」
そう言って、彼女が晋吾を送り出しに玄関外まで出てみると、そこには奈緒が今だ寝ており、
「あらっ!あ、これが晋ちゃんのペットなの?食事の間、ずっとここにいたの?」
「ハハハ…、すみません。ペットですから、家の中に入れるわけにもいかないし、一階の入口に置いておくのも心配だったので、ここまで連れてきちゃいました。ごめんなさい」
「いえいえ、それはいいのだけれど…これがさっき話していた“香織ちゃん”?」
「違います。これはもう一人の“奈緒”という名前の方です。二人飼っているので」
「そうなのー。へー、ヒト科のヒトなんて初めて見たわ。けっこう可愛いのねー」
「ありがとうございます」
礼を述べながら、少し乱暴に奈緒を揺り動かし、
「ほらっ、奈緒!起きなさい!帰るぞ!」
「んっ、うっ、うぅーん…」
まだ薬の効果で朦朧としながらも、それでも健気に立ち上がり、
「ん!?…帰るの?」
と、寝ぼけ眼で反応してきた。
「あぁ、帰るよ。ほら、おばさんにご挨拶は?」
「ふぁーぃ…おばさま、おやすみなしゃい…」
「あら、上手におしゃべりできるのねー。ヒトだったら、今度は家の中に入れてもいいから、また連れてきていいわよ」
「はい。ありがとうございます。では、おやすみなさい」
別れの挨拶を済ませ、まだ少し千鳥足の奈緒の手綱を引きながら、晋吾の家への家路についた。
おばさんと奈緒…これまでの親子関係は、今のやりとりでも明白なように、それまでの全てが“無”になっていた。
首輪に繋がれた“元愛娘”を、今は笑顔で手を振りながら送り出している彼女の姿を背中に感じながら、晋吾と新ペットの奈緒は、エレベーターの中に消えていった。
(ポチの首輪<第5話>に続く…)
妄想商会(19)~ポチの首輪〈第3話〉~*特殊アイテム
翌朝、晋吾が目覚めると、彼の隣では首輪をしたままの香織が、まだ可愛らしい寝息を立てていた。
「(よかった…)」
昨日の衝撃的な出来事が、夢ではなく現実であったことを今改めて実感し、晋吾は心底からの喜びを感じていた。
部屋の隅のペット用トイレに目をやると、どうやら彼が寝ている間に用を足したらしく、小さな砂山が出来上がっていた。言いつけ通り、オシッコの後に上から砂を盛った証である。
程なくして、香織も目を覚まし、
「…あ、ご主人様。おはようございます」
まだ眠気眼で健気に朝の挨拶をしてきた。
「おはよう。俺が寝ている間に、きちんとオシッコ出来たみたいだね。えらいぞ」
そう言って香織の頭を撫でてやると、
「はい♪褒めてもらえて、嬉しいです」
本当に嬉しそうに、可愛らしい笑顔で答えてきた。
一夜明けて、香織も昨日のぎこちなさが徐々に消えてきているようで、ペットとしての自覚と共に、本来の彼女らしい清潔感のある明るさが蘇ってきているようである。
そんな香織の態度に、苦しいくらいの愛しさが込み上げてきて、思わず抱きしめてしまう晋吾である。
「よし、初めてちゃんとトイレが出来たご褒美をあげよう。そのままベッドに仰向けに寝てごらん」
半身を起こしていた香織を再び寝かせると、晋吾は彼女の両脚を大きく開き、その股間に顔を埋め、中央の秘所を舌で愛撫し始めた。
「…あっ、はぁん…あっ、あぅぅ…」
徐々に襲ってくる快感に呼応するかのように、香織は朝の嬌声を上げ始めた。
それと比例するかのように、彼女の秘所からは愛液が溢れ始め、晋吾の唾液と絡み合って、ピチャピチャと卑猥な音を、股間から発し始めている。
「あぁぁっ…あっ、あっ…」
かなりの量の愛液が溢れ出してきたところで、晋吾はようやくにその股間から顔を離し、今度は指を挿入し始めた。
唾液と愛液が溢れ、朝の光を浴びてキラキラと輝いているかのようなその秘所は、熱くなった体温でまるで湯気でも立ち上るのではないかと思うほどに、生々しいいやらしさを醸し出しているので、晋吾の指など一本、二本と容易に受け入れた。
晋吾はその二本指の手の平を上向きにして、激しくピストン運動をさせはじめた。
「はぁうぅ…あぅっ、あぁああっ…」
香織の喘ぎ声も、さらに勢いを増してくる。
この指使いは、晋吾は見飽きるくらいに見続けてきたアダルトビデオをお手本にしているので、まるで香織の膀胱を底の方からリズミカルに圧迫しているかのような激しさで責めまくっている。
「あぁぁああああっ!…ごっ、ご主人さまぁっ…だ、だめです…あぁぁっ!!…あっ!だめぇぇぇっ!!」
一際大きな喘ぎと共に、彼女の尿道から、勢いよく潮が噴出された。
同時に身体がビクビクと小刻みに痙攣を起こし始めた。どうやら絶頂を迎えたようである。
「香織、ずいぶん気持ちよさそうだったねー。あーぁ、せっかくの“トイレよくできました”のご褒美だったのに、またお漏らししちゃったね」
「…だ、だって…ご主人様が…」
「ん?俺が何?」
「…ご主人様が…気持ちいいことするから…」
「あはは、そっか、まぁ、犬も気持ち良過ぎるとお漏らししちゃうもんね。ヒトも同じか。香織、またして欲しいか?」
「はいっ♪」
この辺りの感覚は、通常の人間のややこしい理性が邪魔することの無いので、純粋な欲求を表に出しやすいのだろう。
本来、気持ちがいいことを嫌がる動物の方が少ないわけなので、現にものすごくして欲しそうに、目を輝かしている。
「残念でした。ご褒美だからねー。何も無しにあげるわけにはいかないね。但し、気持ちがいい事をして欲しい時に、俺にアピールすることくらいは許してあげるよ。その時は、立ったまま舌を出して、両手は軽くグーを作って胸の前で左右くっつけて、腰を前後に小刻みに揺さぶること。いいね?ほら、練習、練習。やってごらん」
香織は言われるままの体制を、ぎこちないながらも真似て見せ、
「はっ、はっ、はっ、はっ…」
小刻みに腰を前後に揺すりながら、舌を出したまま、まるで犬のように口からの吐息音を奏で始めた。
見事なくらい、人間にとっては“マヌケ”な行動である。
それをこの“元・清楚で貞淑な美人若妻”が何のてらいもなく、ただ純粋に“性欲を満たしてもらうためのおねだり”を一生懸命に行っている…という事実が、晋吾の背徳心を大いに刺激してくれるのだ。
晋吾は更に自分の背徳心を煽るかのように、朝食前に香織を散歩に連れ出すことにした。
もちろん、香織は全裸での初お散歩になるのだ。
香織に簡単なメイクとヘアースタイルのセットを終えさせ、裸足で怪我をさせては可哀相なので、昨日履いていた、ヒールが低めのカジュアルなパンプスだけ履かせて、手綱を引きながら外に出た。
家の前の通りは、早めに通勤通学をする人達が、急ぎ早に駅へと向かっていた。
この中に、いくら周囲の環境が“ヒト科のペット”を容認する環境になっているとはいえ、やはり美貌とプロポーションに恵まれた香織が、全裸で首輪に繋がれた手綱に引かれて歩かされている様は、異様な光景としか言い様が無い。
二人が隣の家(ここは昨日まで水谷香織とその夫の誠二の愛の巣だった家である)の前を通りかかった時、不意に勢いよくその家から出てきた人物とぶつかりそうになった。
「おっと!失礼!…あ、君はお隣の…えーっと晋吾君だったね。急いでたので、ごめんね」
なんと、その人物こそ、香織の“元”夫である誠二だった。
「いえいえ、大丈夫です。水谷さんこそ、“独身生活”だから何かと大変なんでしょうね」
「おいおい、朝からキツイこと言ってくれるなよ。ん?ペット飼ったの?朝の散歩かい?」
「あ、ええ、そうなんですよ。香織っていうヒト科のメスです。話すこともできるので、飼うのは楽なんですよ」
「へー、ヒト科のメスなんてめずらしいもの飼ったねー。初めて見たよ。話せるんだっけ?…えーっと…香織、おはよう」
「水谷さん、おはようございます♪」
「おお、上手に話すんだねー。可愛い可愛い」
「でしょう、昨日から飼い始めたばかりなので、トイレの躾とかの最中なんです」
「ははは、勉強の傍らで大変なことだ。香織は何歳なのかな?」
「えっと、人間と同じ数え方ですから、今26歳ですね」
「そっかぁ、人間の女性で26歳だったら、一番魅力的な年頃なんだけどねー。俺好みの年代だよ。ははは、まぁ、ヒトのメスじゃ、彼女にするってわけにもいかないしね。それにしてもけっこう可愛いね」
言いながら、誠二は香織の頭を撫でている。
「香織、可愛いって言ってもらえたお礼に、ペットとして水谷さんの足元に膝まづいて、足にキスしなさい。ほらっ」
手綱を下に向けて軽く引くと、香織は従順に誠二の足元に膝を付き、垂れる髪の毛を片手で上げながら、彼の靴に軽くキスをした。
これが、昨日まで仲睦まじかった新婚夫婦の姿であろうか。そんな面影など、今や微塵も無い。
「おっと!いけね!急いでたんだった!じゃ、晋吾君、また今度香織とでも遊ばせてね!」
誠二はそう言いながら手を振って、駅へと向かって走り去っていった。
誠二との思わぬ遭遇は、晋吾の背徳心を大いに興奮させるものではあったが、さすがに少し申し訳ない気もしたので、いずれ彼への救済措置でも考えてあげなきゃならないかもしれない。
そんなハプニングの後、朝の散歩コースとして予め決めていた、家から10分くらいの距離にある自然公園まで辿り着いた。
その間、様々な人々とすれ違ったが、誰も違和感を覚える様子などなかったし、犬の散歩をしている人などからは、笑顔で挨拶までされてしまった。
もうこの世界では、ヒト科のペットは当たり前のように受け入れられているようで、最初家を出た時のドキドキ感などは、霧散してしまっており、今や堂々たる態で公園まで入ってきた。
一人ではまず朝からこんな健康的なことはしないだろう…と思うくらいの心地よい朝の陽気を浴び、軽いジョギングをしたり、ベンチで寛いだりしていたら、突如香織がモジモジし始め、下腹部を手で押さえ始めたので、ピンときた。
「どうした香織?さてはもしかしてウ○チがしたくなったのか?」
「…はい」
少し辛そうな顔で、香織がコクリと頷いた。
想定外ではあったが、考えてみれば自然なことだ。しかし想定外故に、よく犬を連れている人が持っているような、回収用の袋やスコップなどの装備も無い。
無いけれど、公園内のいたるところに“ペットのフンは飼い主が回収”という看板が立てられている。
困ってはみたものの、香織もかなり余裕が無さそうだし、通常の人としての理性レベルをかなり下げているので、このままだと今この状態で“ソレ”をしてしまうだろう。
仕方ないので、近くの植え込みの中でさせることにした。
「香織、仕方ないけど、ここにしゃがんでしなさい」
「…はい」
言われるままに香織はその場にしゃがみ込み、
「ふぅん…んっ、ぅんっ…」
と、いきみ始めた。
程なくして、
ブーッ、ブシュッ…
という恥ずかしい破裂音とともに、彼女の股間から彼女の体型としては見事なサイズの茶褐色の練り羊羹のような物体が、地面に落下していった。
とたんに起ちこめる何とも言えない異臭…はっきり言って臭い。
こんな美女でも、お腹の中にこんな臭いものを溜めていたのかという、淡いカルチャーショックを覚える程である。
通常の女性であれば、何よりも他人に見せたくない光景であろう。
昨日午前中までの香織であれば、絶対にそうである。
しかし、今は晋吾の前でこんなにも堂々と、排泄だけに集中して一生懸命になっている香織なのだ。
晋吾はその異臭に耐えながら、強烈な征服感を感じていた。
ここまでの香織の醜態を見届けたのは、絶対に自分一人だけなのだ…と。元夫の誠二でさえ、こんな醜態は見たことがないはずである。
と同時に、
「(これは部屋の中のトイレでされては、さすがに美女の出したものとは言え、ちょっとキツイな…。やれやれ、毎朝の散歩は日課だな…)」
などという、現実的なことも考えていた。
朝の散歩からの帰宅後、晋吾は大学へ行く準備を終え、
「香織、じゃあ、俺は学校に行って来るから、帰ってくるまでいい子で留守番してるんだぞ。餌はキッチンの床に置いてあるから、自分でちゃんと食べるように。いいね?」
「はい、ご主人様。いってらっしゃいませ」
“いってらっしゃい”という愛情がこもった言葉で見送られるなど、何年振りのことであろう。
人間の妻であった香織と、ペットと化した香織…どちらが幸せなのかは不明であるが、彼女の人生を大きく転換させたのは、紛れもなく自分自身である。
ペットとして、自分にこんなにも献身的な愛情を注いでくれる彼女を、改めてずっと大切にしていこうと思いながらの登校となった。
大学の講義中も香織のことが頭にあり、つまらぬ講義などほぼ上の空で終えて帰宅した晋吾は、イタズラ心で香織を驚かせてやろうと、玄関からではなく、キッチン横の勝手口からそーっと侵入してやろうと思い立ち、出来る限りの音を消して、彼女に気付かれないように屋内に入った。すると…
「ぁはん…ぁんっ…はぅ…あぁん…」
リビングの方から艶かしい喘ぎ声が聞こえてくる。明らかに昨夜から散々聞いている香織の喘ぎ声だ。
「??」
どうしたんだろう…という思いと、まさか誰かが家に侵入して…等という不安感が混ざり合って、音を消している晋吾の足を、速めさせた。
物陰からそーっとリビングを覗いてみると、なんと香織が一人でソファの前のローテーブルの角に自分の股間を押し当て、腰を微妙な可動範囲で小刻みに動かしながら、目を閉じて恍惚となった顔を天井に向けて喘いでいた。
この光景に驚きつつも、そのあまりにも艶かしい痴態に、晋吾の一物は途端にいきり立ち、ズボンを押し上げようとしている。
元人間であったころの、この部分の理性は失っているはずであるので、昨日から今朝にかけての性行為で覚えた快感が病みつきになり、本能的に考え出した行動であろう。
この辺りは、有名な逸話である“サルにオナニーを教えたらずっとやり続ける”のと同じ感覚なのかもしれない。
淫乱になった…というよりは、ただ単に“気持ちいいからしているだけ”のようだ。
「はぁあ…あっ、あぅぅ…あっ、あっ…」
徐々に腰を動かす速度と、押し付ける強度が高まっていっているようであり、それに比例して喘ぎも大きくなってきた。
「あぁぁぁぁっ…あぅっ、んぁああああっ!」
一際甲高い喘ぎと共に、まるで全身の力が抜けたかのように、ローテーブルの上に上半身をうな垂れさせ、全身を軽く痙攣させている。
自分一人でも昇りつめてしまったのだ。
「香織、ただいまー」
「あっ!ご主人様…おかえりなさい」
物陰からいきなり現れた晋吾に、多少びっくりした素振りの香織は、まだ力が戻りきっていない身体を懸命に起こして、大切なご主人様を迎えようとしている。
「香織、気持ちいことを覚えちゃったねぇ。俺が留守にしている間に、何回くらい気持ちいいことしてたんだい?」
「はい、5回くらいです♪」
通常の女性であれば恥らうような質問にも、何と誇らしげにまるで「頑張りました」を主張するかのような、にこやかでハッキリした答えが返ってきた。
そして、待ち焦がれていた“もっと気持ちいいことを与えてくれる存在”が帰ってきたことを喜ぶ証に、舌を出して、胸の前で両拳を丸めた体勢での“おねだりポーズ”で、一生懸命にご褒美をねだっている。
まさに完全な“ヒト型ペット”に堕ちた香織である。
「うーん…そんなにご褒美が欲しいのか。じゃあ、ちゃんとチンチンが出来てからだな」
そう言うなり、晋吾はおもむろにズボンとパンツを彼女の目の前で一気に下ろし、まだ洗浄もしていない匂い立つような一物を、香織の目の前に突き出した。
突き出された一物は、先程の香織の痴態見物の効果で、当然のことながら既にいきり立っていたが、香織はそんな一物の勢いや一日の生活で汚れた異臭などお構いなしに、嬉々としてしゃぶりついていった。
晋吾は、もう幾度となく訪れた下半身への至福の刺激に喜びを感じながら、次なる妄想実現へと、胸を膨らませていた。
(ポチの首輪<第4話>に続く…)
「(よかった…)」
昨日の衝撃的な出来事が、夢ではなく現実であったことを今改めて実感し、晋吾は心底からの喜びを感じていた。
部屋の隅のペット用トイレに目をやると、どうやら彼が寝ている間に用を足したらしく、小さな砂山が出来上がっていた。言いつけ通り、オシッコの後に上から砂を盛った証である。
程なくして、香織も目を覚まし、
「…あ、ご主人様。おはようございます」
まだ眠気眼で健気に朝の挨拶をしてきた。
「おはよう。俺が寝ている間に、きちんとオシッコ出来たみたいだね。えらいぞ」
そう言って香織の頭を撫でてやると、
「はい♪褒めてもらえて、嬉しいです」
本当に嬉しそうに、可愛らしい笑顔で答えてきた。
一夜明けて、香織も昨日のぎこちなさが徐々に消えてきているようで、ペットとしての自覚と共に、本来の彼女らしい清潔感のある明るさが蘇ってきているようである。
そんな香織の態度に、苦しいくらいの愛しさが込み上げてきて、思わず抱きしめてしまう晋吾である。
「よし、初めてちゃんとトイレが出来たご褒美をあげよう。そのままベッドに仰向けに寝てごらん」
半身を起こしていた香織を再び寝かせると、晋吾は彼女の両脚を大きく開き、その股間に顔を埋め、中央の秘所を舌で愛撫し始めた。
「…あっ、はぁん…あっ、あぅぅ…」
徐々に襲ってくる快感に呼応するかのように、香織は朝の嬌声を上げ始めた。
それと比例するかのように、彼女の秘所からは愛液が溢れ始め、晋吾の唾液と絡み合って、ピチャピチャと卑猥な音を、股間から発し始めている。
「あぁぁっ…あっ、あっ…」
かなりの量の愛液が溢れ出してきたところで、晋吾はようやくにその股間から顔を離し、今度は指を挿入し始めた。
唾液と愛液が溢れ、朝の光を浴びてキラキラと輝いているかのようなその秘所は、熱くなった体温でまるで湯気でも立ち上るのではないかと思うほどに、生々しいいやらしさを醸し出しているので、晋吾の指など一本、二本と容易に受け入れた。
晋吾はその二本指の手の平を上向きにして、激しくピストン運動をさせはじめた。
「はぁうぅ…あぅっ、あぁああっ…」
香織の喘ぎ声も、さらに勢いを増してくる。
この指使いは、晋吾は見飽きるくらいに見続けてきたアダルトビデオをお手本にしているので、まるで香織の膀胱を底の方からリズミカルに圧迫しているかのような激しさで責めまくっている。
「あぁぁああああっ!…ごっ、ご主人さまぁっ…だ、だめです…あぁぁっ!!…あっ!だめぇぇぇっ!!」
一際大きな喘ぎと共に、彼女の尿道から、勢いよく潮が噴出された。
同時に身体がビクビクと小刻みに痙攣を起こし始めた。どうやら絶頂を迎えたようである。
「香織、ずいぶん気持ちよさそうだったねー。あーぁ、せっかくの“トイレよくできました”のご褒美だったのに、またお漏らししちゃったね」
「…だ、だって…ご主人様が…」
「ん?俺が何?」
「…ご主人様が…気持ちいいことするから…」
「あはは、そっか、まぁ、犬も気持ち良過ぎるとお漏らししちゃうもんね。ヒトも同じか。香織、またして欲しいか?」
「はいっ♪」
この辺りの感覚は、通常の人間のややこしい理性が邪魔することの無いので、純粋な欲求を表に出しやすいのだろう。
本来、気持ちがいいことを嫌がる動物の方が少ないわけなので、現にものすごくして欲しそうに、目を輝かしている。
「残念でした。ご褒美だからねー。何も無しにあげるわけにはいかないね。但し、気持ちがいい事をして欲しい時に、俺にアピールすることくらいは許してあげるよ。その時は、立ったまま舌を出して、両手は軽くグーを作って胸の前で左右くっつけて、腰を前後に小刻みに揺さぶること。いいね?ほら、練習、練習。やってごらん」
香織は言われるままの体制を、ぎこちないながらも真似て見せ、
「はっ、はっ、はっ、はっ…」
小刻みに腰を前後に揺すりながら、舌を出したまま、まるで犬のように口からの吐息音を奏で始めた。
見事なくらい、人間にとっては“マヌケ”な行動である。
それをこの“元・清楚で貞淑な美人若妻”が何のてらいもなく、ただ純粋に“性欲を満たしてもらうためのおねだり”を一生懸命に行っている…という事実が、晋吾の背徳心を大いに刺激してくれるのだ。
晋吾は更に自分の背徳心を煽るかのように、朝食前に香織を散歩に連れ出すことにした。
もちろん、香織は全裸での初お散歩になるのだ。
香織に簡単なメイクとヘアースタイルのセットを終えさせ、裸足で怪我をさせては可哀相なので、昨日履いていた、ヒールが低めのカジュアルなパンプスだけ履かせて、手綱を引きながら外に出た。
家の前の通りは、早めに通勤通学をする人達が、急ぎ早に駅へと向かっていた。
この中に、いくら周囲の環境が“ヒト科のペット”を容認する環境になっているとはいえ、やはり美貌とプロポーションに恵まれた香織が、全裸で首輪に繋がれた手綱に引かれて歩かされている様は、異様な光景としか言い様が無い。
二人が隣の家(ここは昨日まで水谷香織とその夫の誠二の愛の巣だった家である)の前を通りかかった時、不意に勢いよくその家から出てきた人物とぶつかりそうになった。
「おっと!失礼!…あ、君はお隣の…えーっと晋吾君だったね。急いでたので、ごめんね」
なんと、その人物こそ、香織の“元”夫である誠二だった。
「いえいえ、大丈夫です。水谷さんこそ、“独身生活”だから何かと大変なんでしょうね」
「おいおい、朝からキツイこと言ってくれるなよ。ん?ペット飼ったの?朝の散歩かい?」
「あ、ええ、そうなんですよ。香織っていうヒト科のメスです。話すこともできるので、飼うのは楽なんですよ」
「へー、ヒト科のメスなんてめずらしいもの飼ったねー。初めて見たよ。話せるんだっけ?…えーっと…香織、おはよう」
「水谷さん、おはようございます♪」
「おお、上手に話すんだねー。可愛い可愛い」
「でしょう、昨日から飼い始めたばかりなので、トイレの躾とかの最中なんです」
「ははは、勉強の傍らで大変なことだ。香織は何歳なのかな?」
「えっと、人間と同じ数え方ですから、今26歳ですね」
「そっかぁ、人間の女性で26歳だったら、一番魅力的な年頃なんだけどねー。俺好みの年代だよ。ははは、まぁ、ヒトのメスじゃ、彼女にするってわけにもいかないしね。それにしてもけっこう可愛いね」
言いながら、誠二は香織の頭を撫でている。
「香織、可愛いって言ってもらえたお礼に、ペットとして水谷さんの足元に膝まづいて、足にキスしなさい。ほらっ」
手綱を下に向けて軽く引くと、香織は従順に誠二の足元に膝を付き、垂れる髪の毛を片手で上げながら、彼の靴に軽くキスをした。
これが、昨日まで仲睦まじかった新婚夫婦の姿であろうか。そんな面影など、今や微塵も無い。
「おっと!いけね!急いでたんだった!じゃ、晋吾君、また今度香織とでも遊ばせてね!」
誠二はそう言いながら手を振って、駅へと向かって走り去っていった。
誠二との思わぬ遭遇は、晋吾の背徳心を大いに興奮させるものではあったが、さすがに少し申し訳ない気もしたので、いずれ彼への救済措置でも考えてあげなきゃならないかもしれない。
そんなハプニングの後、朝の散歩コースとして予め決めていた、家から10分くらいの距離にある自然公園まで辿り着いた。
その間、様々な人々とすれ違ったが、誰も違和感を覚える様子などなかったし、犬の散歩をしている人などからは、笑顔で挨拶までされてしまった。
もうこの世界では、ヒト科のペットは当たり前のように受け入れられているようで、最初家を出た時のドキドキ感などは、霧散してしまっており、今や堂々たる態で公園まで入ってきた。
一人ではまず朝からこんな健康的なことはしないだろう…と思うくらいの心地よい朝の陽気を浴び、軽いジョギングをしたり、ベンチで寛いだりしていたら、突如香織がモジモジし始め、下腹部を手で押さえ始めたので、ピンときた。
「どうした香織?さてはもしかしてウ○チがしたくなったのか?」
「…はい」
少し辛そうな顔で、香織がコクリと頷いた。
想定外ではあったが、考えてみれば自然なことだ。しかし想定外故に、よく犬を連れている人が持っているような、回収用の袋やスコップなどの装備も無い。
無いけれど、公園内のいたるところに“ペットのフンは飼い主が回収”という看板が立てられている。
困ってはみたものの、香織もかなり余裕が無さそうだし、通常の人としての理性レベルをかなり下げているので、このままだと今この状態で“ソレ”をしてしまうだろう。
仕方ないので、近くの植え込みの中でさせることにした。
「香織、仕方ないけど、ここにしゃがんでしなさい」
「…はい」
言われるままに香織はその場にしゃがみ込み、
「ふぅん…んっ、ぅんっ…」
と、いきみ始めた。
程なくして、
ブーッ、ブシュッ…
という恥ずかしい破裂音とともに、彼女の股間から彼女の体型としては見事なサイズの茶褐色の練り羊羹のような物体が、地面に落下していった。
とたんに起ちこめる何とも言えない異臭…はっきり言って臭い。
こんな美女でも、お腹の中にこんな臭いものを溜めていたのかという、淡いカルチャーショックを覚える程である。
通常の女性であれば、何よりも他人に見せたくない光景であろう。
昨日午前中までの香織であれば、絶対にそうである。
しかし、今は晋吾の前でこんなにも堂々と、排泄だけに集中して一生懸命になっている香織なのだ。
晋吾はその異臭に耐えながら、強烈な征服感を感じていた。
ここまでの香織の醜態を見届けたのは、絶対に自分一人だけなのだ…と。元夫の誠二でさえ、こんな醜態は見たことがないはずである。
と同時に、
「(これは部屋の中のトイレでされては、さすがに美女の出したものとは言え、ちょっとキツイな…。やれやれ、毎朝の散歩は日課だな…)」
などという、現実的なことも考えていた。
朝の散歩からの帰宅後、晋吾は大学へ行く準備を終え、
「香織、じゃあ、俺は学校に行って来るから、帰ってくるまでいい子で留守番してるんだぞ。餌はキッチンの床に置いてあるから、自分でちゃんと食べるように。いいね?」
「はい、ご主人様。いってらっしゃいませ」
“いってらっしゃい”という愛情がこもった言葉で見送られるなど、何年振りのことであろう。
人間の妻であった香織と、ペットと化した香織…どちらが幸せなのかは不明であるが、彼女の人生を大きく転換させたのは、紛れもなく自分自身である。
ペットとして、自分にこんなにも献身的な愛情を注いでくれる彼女を、改めてずっと大切にしていこうと思いながらの登校となった。
大学の講義中も香織のことが頭にあり、つまらぬ講義などほぼ上の空で終えて帰宅した晋吾は、イタズラ心で香織を驚かせてやろうと、玄関からではなく、キッチン横の勝手口からそーっと侵入してやろうと思い立ち、出来る限りの音を消して、彼女に気付かれないように屋内に入った。すると…
「ぁはん…ぁんっ…はぅ…あぁん…」
リビングの方から艶かしい喘ぎ声が聞こえてくる。明らかに昨夜から散々聞いている香織の喘ぎ声だ。
「??」
どうしたんだろう…という思いと、まさか誰かが家に侵入して…等という不安感が混ざり合って、音を消している晋吾の足を、速めさせた。
物陰からそーっとリビングを覗いてみると、なんと香織が一人でソファの前のローテーブルの角に自分の股間を押し当て、腰を微妙な可動範囲で小刻みに動かしながら、目を閉じて恍惚となった顔を天井に向けて喘いでいた。
この光景に驚きつつも、そのあまりにも艶かしい痴態に、晋吾の一物は途端にいきり立ち、ズボンを押し上げようとしている。
元人間であったころの、この部分の理性は失っているはずであるので、昨日から今朝にかけての性行為で覚えた快感が病みつきになり、本能的に考え出した行動であろう。
この辺りは、有名な逸話である“サルにオナニーを教えたらずっとやり続ける”のと同じ感覚なのかもしれない。
淫乱になった…というよりは、ただ単に“気持ちいいからしているだけ”のようだ。
「はぁあ…あっ、あぅぅ…あっ、あっ…」
徐々に腰を動かす速度と、押し付ける強度が高まっていっているようであり、それに比例して喘ぎも大きくなってきた。
「あぁぁぁぁっ…あぅっ、んぁああああっ!」
一際甲高い喘ぎと共に、まるで全身の力が抜けたかのように、ローテーブルの上に上半身をうな垂れさせ、全身を軽く痙攣させている。
自分一人でも昇りつめてしまったのだ。
「香織、ただいまー」
「あっ!ご主人様…おかえりなさい」
物陰からいきなり現れた晋吾に、多少びっくりした素振りの香織は、まだ力が戻りきっていない身体を懸命に起こして、大切なご主人様を迎えようとしている。
「香織、気持ちいことを覚えちゃったねぇ。俺が留守にしている間に、何回くらい気持ちいいことしてたんだい?」
「はい、5回くらいです♪」
通常の女性であれば恥らうような質問にも、何と誇らしげにまるで「頑張りました」を主張するかのような、にこやかでハッキリした答えが返ってきた。
そして、待ち焦がれていた“もっと気持ちいいことを与えてくれる存在”が帰ってきたことを喜ぶ証に、舌を出して、胸の前で両拳を丸めた体勢での“おねだりポーズ”で、一生懸命にご褒美をねだっている。
まさに完全な“ヒト型ペット”に堕ちた香織である。
「うーん…そんなにご褒美が欲しいのか。じゃあ、ちゃんとチンチンが出来てからだな」
そう言うなり、晋吾はおもむろにズボンとパンツを彼女の目の前で一気に下ろし、まだ洗浄もしていない匂い立つような一物を、香織の目の前に突き出した。
突き出された一物は、先程の香織の痴態見物の効果で、当然のことながら既にいきり立っていたが、香織はそんな一物の勢いや一日の生活で汚れた異臭などお構いなしに、嬉々としてしゃぶりついていった。
晋吾は、もう幾度となく訪れた下半身への至福の刺激に喜びを感じながら、次なる妄想実現へと、胸を膨らませていた。
(ポチの首輪<第4話>に続く…)
妄想商会(18)~ポチの首輪〈第2話〉~*特殊アイテム
周囲の環境が、甘い夫婦生活の面影に包まれていた光景から、男の一人暮らし所帯の殺風景なインテリアに一変してしまった中で、晋吾と香織が立ち尽くしている…。
しかし二人の思惑は全く別のもので、晋吾はこれからの香織の扱いに興奮を覚えつつも戸惑い、香織はただ単純に呆然としてるようであった。
「か、香織…、どうやらここは人様の家のようだね。香織も覚えはないんだよね?」
「はい、晋吾様。ここには初めて来ました」
どうやら、シルクが用意してくれた環境変化は、本物のようである。
「じゃ、じゃあ、長居は無用だね。早く家に帰ろう」
そう言って、晋吾は手に持っている手綱を引っ張ると、一瞬の突っ張り感を残して、香織が引かれるままに、従順に付いてくる。
侵入してきた窓ではなく、玄関から外に出るにあたり、晋吾はそれなりの緊張を覚えた。
閑静な住宅街とは言え、天気の良い昼下がりである。それなりの人の往来はあるし、ご近所にも顔見知りはたくさんいる。
何しろ、両親が海外へ旅立ってしまった状態での、大学生一人暮らしの晋吾であるので、ご近所もそれなりに気にしてくれ、時折は差し入れも持ってきてくれるし、外で会えば近況を聞いてくれたりもする間柄なのだ。
意を決して、香織を繋いだ手綱を引いたまま道路に出ると、
「あら、晋吾ちゃん、お昼食べたの?」
向いの庭先で庭の手入れをしていたおばさんが、いつも通りに声をかけてきた。
一瞬、ドキッとした晋吾だが、
「あら?晋吾ちゃん、何を連れているの?首輪で繋いでいるところを見ると、ペットでも飼うことにしたのかしら?それとも迷い人?」
「(迷い人!?)」
おばさんからのこの問いかけに、多少の安堵感を覚えた。
このおばさんは、今確かに“迷い犬”などの動物呼称ではなく“迷い人”という、人間呼称を使ったのだ。彼女の目には、どうやら香織は人権を持った人間とは捉えられておらず、ペットか野良としての人間がこの世に存在すると言う認識を持っていることになる。どうやらそういう世界になったのだろう。
「う、うん。さすがに一人が寂しくてね。今度この“ヒト科のメス”をペットとして飼うことにしたんですよ。名前は“香織”っていいます」
「あら、そうなのー。まぁ、そうよね、一人ぼっちじゃ寂しいもんねー。香織さんは喋れるのかしら?」
「おばさま、初めまして。香織です。よろしくお願いします」
ワンピースを着たままで首輪に繋がれているという、異様な出で立ちのままで、香織は持ち前の行儀良さで返事をした。
「まぁ、上手に喋れるのねー。これなら躾も楽そうね。ハイハイ、香織さん、こちらこそよろしくね。晋吾ちゃん、後で香織さんの餌でも差し入れしてあげるわね。…それにしても、ペットに服を着せるなんて、晋吾ちゃんも凝ったことするのねー」
この言葉には、晋吾も正直驚かされつつも、大いなる喜びが同時に込み上げてきた。
先ほどから、彼の妄想の中で、香織の出で立ちの始末をどうつけようかと、想像を巡らせていたのだが、周囲の反応が不安で、イマイチ決心をつけかねていたのだが、その周囲の人から見ても、ペットに服…というのは、飼犬と同じく“凝った趣向”として写っているようなのだ。
「あ、いえいえ、実はさっき引き取ってきたばかりで、以前の飼い主が凝った人だったんだけど、僕はどうもそこまで凝れそうにないので、後で脱がしちゃおうかと思ってるんですよ」
「そうよねー、手間が増えるだけですもんね。この近所じゃ…ほら、お隣も犬を飼ってらっしゃるけど、この辺じゃ、そんな飼い主はいないから、かえって目立っちゃうわよね。ペットの服なんかいらない!いらない!」
持ち前の“おばちゃんノリ”で、顔をしかめながら手を大きく左右に振るおばさんに、二人で笑顔で挨拶をして、少し急ぎ足で自宅に帰った。
自宅に帰ると、リビングのソファにさっき消えたばかりのシルクが、腰を下ろしていた。
「晋吾さん、この環境変化、なかなか楽しいでしょう」
「う、うん。凄いもんだね」
「一つ言い忘れたので、再びお邪魔しましたよ。この環境変化は、晋吾さん、あなたの思いと非常に深くリンクしてます。なので、あなたの想像世界で都合がいいように変化していく訳ですね。例えば、香織さんは、あなたが忘れて欲しいと思うことは忘れるし、これは覚えたままの方がいいと思うことは、そのまま残りますし…そんな感じですかね」
「…ますます凄いね」
「ということで、今後はしばらくの間、私が現れることはないと思いますが、商談の件、よろしくお願いしますね。…おっと、これ、予備の首輪と手綱です。いくつか置いていきますよ。まぁ、犬猫と違って、言葉が通じる分、飼い易いと思いますので、複数飼いもよろしいかと思いましてね。しばらくの間は慣れるまで、香織さんで十分かもしれませんけどね」
「ど、どうも…」
それだけ言い残すと、シルクは先程と同じように、スーッと背景に溶け込むように消えていった。
「(なるほど、簡単に考えれば、俺が思った通りの展開になるってことか。嬉しい限りだねー)」
心の中でにんまりしながら、
「香織、さっきのおばさんと話してた通り、俺は面倒なことが嫌いだから、服着せなくてもいいよね?」
「あ、はい」
「よし、じゃあ、脱がせてあげよう」
そう言って、喜び勇んで香織の背後に回り、ワンピースのジッパーを一気に引き下ろし、腕を抜かせて、脱がせてしまった。
清楚な白のブラジャーとショーツだけの姿になった香織だが、かと言って恥らう様子もない。当たり前のように、晋吾の行為を受け入れている。
興奮の極地に達しているのは、晋吾だけなのだ。
何しろ、毎昼毎夜のごとく、彼の妄想世界の中で“オナペット”として活躍してくれていた香織が、今現実に目の前で艶かしい姿で立っているのだから、仕方ない。
晋吾は高鳴る鼓動の振動で震える呼吸と手を、必死に抑えながら、ブラジャーとショーツも脱がしてしまった。
想像通りの見事なプロポーションである…。
大き過ぎず、小さからずの程よいツンと上向きの乳房から、これも程よく脂肪と筋肉が絡んでいるくびれたウエスト…そして、後部には張りのある質感たっぷりの臀部、前部にはキレイな逆三角を描いている、漆黒の繁みを備えた、形のいい骨盤から、しなやかな長い脚…。
まるでグラビアから飛び出したモデルのような、香織の肢体である。
晋吾はズボン中ではちきれんばかりに緊張した一物を隠しながら、
「これでよし…っと。香織は基本的に屋内で飼うから、これでいいよね」
「はい」
「(よーし。ここからは、益々都合のいいようにしていくか…)」
そう考え、以下のようなことを頭の中で設定してみた。
○日常会話レベル以上のことは、基本的に忘れる。
○化粧の仕方くらいは覚えている。(いつも綺麗でいてもらうように)
○性行為全般はしっかり覚えているし、基本的に大好きである。
自分の考えがまとまり、落ち着いたところで、既に自分の欲求が抑えきれなくなってきた。
おもむろに晋吾自身も、服を脱ぎ始め、全裸になってしまった。
これが通常の香織であるならば、晋吾もさすがに恥じらいを禁じ得ないであろうが、目の前にいるのは、自分が全裸でも恥らうことのない“ヒト科のペット”なのである。ペットの前で裸になることを恥らう飼い主などいないだろう。
現に、香織は、目の前で先程まで赤の他人だった晋吾が全裸になっても、動揺など微塵も無い様子である。
晋吾は、全裸状態で、今や隠すものもなく屹立した一物を天に向けながら、
「香織…。香織はペットなんだから、飼い主に気に入られなくちゃいけないね。なので、まず習慣にしなきゃいけないことを教えるよ。俺が“チンチン!”って言ったら、フェラチオすること。分かるね?」
「はい。分かります」
「じゃあ、“チンチン!”」
「はい」
返事と共に、香織は仁王立ちの晋吾の前で膝まづき、両手で目の前の屹立した一物を、大事そうに覆い持つかのように手を添えながら、晋吾の分身をその可愛らしい口の中いっぱいに咥え込んでいった。
「(ピチャピチャ…ングッ…チュバチュバ…)」
淫靡な音を部屋の中に響かせながら、飼い主に喜んでもらおうと、操作された記憶の片隅に残っている性技をいかんなく発揮しようと努めている。
「うわぁ…最高に気持ちいいよ…香織…」
既に香織の頭を両手で押さえつけ、グイグイと自分の下半身を香織の顔に押し付け始めている。
「ングッ!…ンンッ…グェ…ング…」
喉の奥まで一物が達したのか、襲ってくる嘔吐感を必死に抑えながら、それでもひたむきに晋吾の欲求に応えようとする様は、まさに“愛くるしいペット”さながらであった。
「か、香織…このまま喉の中に出すからね…全部飲み干せよ…うぅっ!!」
次の瞬間、白濁の飛沫が、香織の喉奥深くに一気に放出された。
「!!…ングッ!!…ングッ…ゲボッ…ゲホッ!ゲホッ!」
さすがにむせる香織。
それでも、しっかりと飼い主が放出した液体全てを、その体内に落とし込んでいた。
憧れの香織のフェラによる、至福の瞬間を迎えた後も、晋吾の一物は萎えることを知らなかった。さすがに血気盛んな20歳の身体である。
「うーん…気持ちよかったなぁ…。そうだ、よく出来た香織に、ご褒美をあげなきゃね。これから香織が一番喜ぶご褒美だよ。後を向いて、床に手を付いてごらん」
「あ…はい、こうでしょうか」
膝を伸ばした形で、床に手を付いた体勢をとると、晋吾の眼下には、高々と突き上げられたオシリの真ん中に、パックリと割れたもう一つの谷間が顕わになっている。当然アナルも露呈されているわけで、ついさっきまでの貞淑そうな美しき新妻の姿は、もうそこには無く、ただの“盛りのついたメス犬”のような香織になっていた。
その証拠に、フェラの最中に自身もある程度は感じてしまっていたと思われる形跡が、真ん中の谷間から溢れ出ている、光り輝く分泌液として見て取れるのだから…。
「よし、じゃあ、そのまま動かないようにね」
言うなり、晋吾は香織の尻タブを両手で鷲掴みにし、その濡れ輝く中央の割れ目に、いまだ勢いを衰えさせていない一物を、一気に鎮めていく。
「あぅっ!あぁ…あっ、あぁぁぁ…」
何とも可愛らしく艶かしい嬌声を上げる香織に、晋吾の興奮度は頂点に達し、本能的に腰のピストン速度を速めていく。
「あぁぁっ!!あっ、あっ、あっ…」
香織の体内で、素晴らしい包容力で包み込まれている一物は、彼女の愛液と絡み合い、さらにその緊張度を高めていき、
「あぁ、香織、もうダメだ…このまま…いく…あぁっ!」
ドピュッ!ドピュッ!ドピュッ!
先程のフェラで放出し切れなかった白濁の飛沫が、今度は下腹部から香織の体内に注ぎ込まれていった。
「香織、どう?ご褒美は嬉しかった?」
「はい…ご主人様、とても気持ちよくて、嬉しかったです」
「それは良かった。これからも、ご褒美をたくさんもらえるように、しっかりとペットとして頑張るんだよ。いいね?」
「はい、分かりました」
晋吾は満足であった。当然であろう、憧れだった“お隣の新妻”を、ペットと飼い主という、何とも背徳的で官能的な関係で征服したのだから…。
中で射精してしまったことには、妊娠に対して多少の不安はあったが、まぁ、その時はその時である。
只一つ…獣医に任せるべきか、産婦人科に任せるべきかの迷いはあるが…。
「俺はちょっとシャワーを浴びてくるから、香織はそこで立って待っていなね。ペットなんだから」
「はい…分かりました」
さすがにペットと飼い主の立場の違いは、しっかりと認識させないといけない…香織の身体は、庭先でのホース洗いで十分…そう決めたので、晋吾は一人シャワーを浴びに、バスルームに入って行った。
シャワーから出てみると、香織はうつむき加減で下半身をモジモジさせて、申し訳無さそうに立っていた。
どうしたんだろう…と思ってはみたが、同時に視界に入ってきた彼女の足元の床に溜まっている液体で、状況が飲み込めた。そう、“お漏らし”をしてしまったのだ。
考えてみれば、通常の人間としての行動は、日常会話レベル以外のことを全て忘れさせてしまっている状態なので、当然通常の人間としての排泄の仕方も忘れてしまっていることになっていたのだ。
「あーぁ、香織、ダメじゃないか、そんなとこでお漏らしなんかしちゃ!」
パシンッ!
叱りながら、ある程度の痛さを感じる強度で、彼女のオシリを叩いた。
これも躾である。仕方ない仕打ちであろう。
「ご、ごめんなさい…」
「後でペット用のトイレを買ってきてあげるから、今度からそこですること!いいね?」
「はい…わかりました」
晋吾は再び平手打ちを喰らわすような素振りで、手を頭上にかざしながら、
「もしまた違うところでしたら…これだぞ!」
「はい!もうしません!」
香織はやや身をすくめるような体勢で、反省の色を全身に表していた。
香織の粗相の始末を終え、一段落すると、空腹を覚えた。それもそのはずである。思い出せば、昼食をまだ取っていなかった。
元新妻の香織に何か作らせようかとも考えたが、調理の仕方なども忘れさせてしまったことに気付き、また飼い主がペットに料理をしてもらう…という本末転倒な関係にも戸惑いを感じたので、やはり食事の支度はこれまで一人でやってきたのと同じようにすることに決めた。
ただ、これからはペット用の食事も用意しなくてはならないが…。
まぁ、いずれ機を見て、家事専用のペットを飼ってもいいのである。
晋吾は簡単な調理を済ませ、料理とはお世辞にも言えないものを食卓に並べ、席につく前に自分の足元に食べ物を盛った皿を一枚置いた。
当然のことながら、香織用の食料である。
「香織、ご飯だよ。こっちにおいで」
「あ、はい」
呼び付けて、床を指差し、
「こぼさないように上手に食べるんだよ。ペットなんだから、四つん這いで、手なんか使うような“はしたない食べ方”なんてしちゃダメだよ」
「わかりました」
香織は晋吾の足元に両手両脚を折り畳むように腹這いになり、慣れない口さばきで、皿の上の“餌”を食べ始めた。
「(これがちょっと前までは、あの美しい奥様だったとは…)」
今やその美貌こそそのままではあるが、清楚で貞淑そうな若奥様…といった面影など影を潜め、淫靡なメス犬と化した香織が自分の足元に這いつくばっている…。
晋吾はそんな彼女の食事風景を眺め、その劇的な変貌に驚きと満足を再認識していた。
夕方になり、初夏の日差しも傾きかけてきたところで、香織を玄関前に連れ出して、身体を洗ってあげることにした。
玄関前で四つん這いの格好にさせ、ホースの水を頭からかけながら、全身くまなくの手洗いである。
この日まで、ここまで女体を触り尽くした日などなかっただけに、感動と興奮のあまり、かなり執拗な手洗いになってしまうことは、仕方の無いことであろう。
四つん這いの為、重力でやや垂れ下がり気味のオッパイなどは、その何とも言えない柔らかな感触を存分に楽しみながら、揉みしだくように念入りなマッサージを繰り返し、股間に至っては、一枚一枚のヒダまで洗い尽くすかのような懲りようである。
「あぁ…あぅん…」
香織は敏感な部分に触れられる度に、小さく切ない鳴き声を上げている。
帰宅時間帯の夕暮れ時なので、閑静な住宅街にも帰宅を急ぐ人の往来が増え始めている。当然晋吾宅の家の前も、それなりの人の往来があるわけだが、全裸の女性が庭先で四つん這いになり、艶かしい嬌声を上げながら、その全身を水洗いされているという、通常であれば“異常”な光景にも、全く気を止める様子など無い。
誰しもが、よく見かける“ペットの身体洗い”としか認識していないのだから、当然のことである。
その後、晋吾は家からさほど遠くない駅前のホームセンターまで父親が置いていった車を走らせ、大型ペット用のトイレと、そこに敷き詰める砂を購入し、薬局ではいくつかの薬剤と、香織から聞きだした彼女の愛用のメイク道具を、店員に手伝ってもらいながら購入した。
その間に香織は、晋吾の母親の鏡台とメイク道具で、自分で化粧を落とさせ(メイクに関することは記憶に留めさせておいてあるので)、夜に備えさせたわけだが、元々薄いメイクしか施していない香織なので、メイクを落とした後の顔も、昼の美貌と比べて全く遜色は無かった。
夕食は昼と同様のスタイルで食し、就寝前にもう一度“チンチン”をさせ、そしてさらに“ご褒美”もたっぷりと味合わせてあげて、この日は早々に寝ることにした。
何しろ、この日は劇的なことが多すぎた。そして興奮に継ぐ興奮の連続だった為、さすがに強い疲労感にも襲われていた。
この日は結局、昼からの大学の講義もサボってしまった訳だが、そんなことはどうでもいい程に、充実した一日だった。
「いいか、香織、今度オシッコがしたくなったら、俺が寝ている時でも、ちゃんと部屋の隅に置いてあるトイレの中でするんだぞ。し終わってそのままにしておくと臭くなるんだから、上から砂もかけておくように。わかったね?」
「はい、ご主人様。わかりました」
この辺りは言葉の通じるペットなので、躾も楽である。ヒト科のメスをペットに出来る喜びの一つだ…と、今さらながらに感じていた。
寝るときは一緒のベッドに入れてあげることにした。
ペットと一緒に寝る光景は、今時は不自然でもないであろう。
晋吾は久々に味わう“生きた温もり”に存分に甘えながら、何とも言えない安らかさで、深い眠りに落ちていった。
願わくば、これが長い夢だった…などということが無いように祈りながら…。
(ポチの首輪<第3話>に続く…)
しかし二人の思惑は全く別のもので、晋吾はこれからの香織の扱いに興奮を覚えつつも戸惑い、香織はただ単純に呆然としてるようであった。
「か、香織…、どうやらここは人様の家のようだね。香織も覚えはないんだよね?」
「はい、晋吾様。ここには初めて来ました」
どうやら、シルクが用意してくれた環境変化は、本物のようである。
「じゃ、じゃあ、長居は無用だね。早く家に帰ろう」
そう言って、晋吾は手に持っている手綱を引っ張ると、一瞬の突っ張り感を残して、香織が引かれるままに、従順に付いてくる。
侵入してきた窓ではなく、玄関から外に出るにあたり、晋吾はそれなりの緊張を覚えた。
閑静な住宅街とは言え、天気の良い昼下がりである。それなりの人の往来はあるし、ご近所にも顔見知りはたくさんいる。
何しろ、両親が海外へ旅立ってしまった状態での、大学生一人暮らしの晋吾であるので、ご近所もそれなりに気にしてくれ、時折は差し入れも持ってきてくれるし、外で会えば近況を聞いてくれたりもする間柄なのだ。
意を決して、香織を繋いだ手綱を引いたまま道路に出ると、
「あら、晋吾ちゃん、お昼食べたの?」
向いの庭先で庭の手入れをしていたおばさんが、いつも通りに声をかけてきた。
一瞬、ドキッとした晋吾だが、
「あら?晋吾ちゃん、何を連れているの?首輪で繋いでいるところを見ると、ペットでも飼うことにしたのかしら?それとも迷い人?」
「(迷い人!?)」
おばさんからのこの問いかけに、多少の安堵感を覚えた。
このおばさんは、今確かに“迷い犬”などの動物呼称ではなく“迷い人”という、人間呼称を使ったのだ。彼女の目には、どうやら香織は人権を持った人間とは捉えられておらず、ペットか野良としての人間がこの世に存在すると言う認識を持っていることになる。どうやらそういう世界になったのだろう。
「う、うん。さすがに一人が寂しくてね。今度この“ヒト科のメス”をペットとして飼うことにしたんですよ。名前は“香織”っていいます」
「あら、そうなのー。まぁ、そうよね、一人ぼっちじゃ寂しいもんねー。香織さんは喋れるのかしら?」
「おばさま、初めまして。香織です。よろしくお願いします」
ワンピースを着たままで首輪に繋がれているという、異様な出で立ちのままで、香織は持ち前の行儀良さで返事をした。
「まぁ、上手に喋れるのねー。これなら躾も楽そうね。ハイハイ、香織さん、こちらこそよろしくね。晋吾ちゃん、後で香織さんの餌でも差し入れしてあげるわね。…それにしても、ペットに服を着せるなんて、晋吾ちゃんも凝ったことするのねー」
この言葉には、晋吾も正直驚かされつつも、大いなる喜びが同時に込み上げてきた。
先ほどから、彼の妄想の中で、香織の出で立ちの始末をどうつけようかと、想像を巡らせていたのだが、周囲の反応が不安で、イマイチ決心をつけかねていたのだが、その周囲の人から見ても、ペットに服…というのは、飼犬と同じく“凝った趣向”として写っているようなのだ。
「あ、いえいえ、実はさっき引き取ってきたばかりで、以前の飼い主が凝った人だったんだけど、僕はどうもそこまで凝れそうにないので、後で脱がしちゃおうかと思ってるんですよ」
「そうよねー、手間が増えるだけですもんね。この近所じゃ…ほら、お隣も犬を飼ってらっしゃるけど、この辺じゃ、そんな飼い主はいないから、かえって目立っちゃうわよね。ペットの服なんかいらない!いらない!」
持ち前の“おばちゃんノリ”で、顔をしかめながら手を大きく左右に振るおばさんに、二人で笑顔で挨拶をして、少し急ぎ足で自宅に帰った。
自宅に帰ると、リビングのソファにさっき消えたばかりのシルクが、腰を下ろしていた。
「晋吾さん、この環境変化、なかなか楽しいでしょう」
「う、うん。凄いもんだね」
「一つ言い忘れたので、再びお邪魔しましたよ。この環境変化は、晋吾さん、あなたの思いと非常に深くリンクしてます。なので、あなたの想像世界で都合がいいように変化していく訳ですね。例えば、香織さんは、あなたが忘れて欲しいと思うことは忘れるし、これは覚えたままの方がいいと思うことは、そのまま残りますし…そんな感じですかね」
「…ますます凄いね」
「ということで、今後はしばらくの間、私が現れることはないと思いますが、商談の件、よろしくお願いしますね。…おっと、これ、予備の首輪と手綱です。いくつか置いていきますよ。まぁ、犬猫と違って、言葉が通じる分、飼い易いと思いますので、複数飼いもよろしいかと思いましてね。しばらくの間は慣れるまで、香織さんで十分かもしれませんけどね」
「ど、どうも…」
それだけ言い残すと、シルクは先程と同じように、スーッと背景に溶け込むように消えていった。
「(なるほど、簡単に考えれば、俺が思った通りの展開になるってことか。嬉しい限りだねー)」
心の中でにんまりしながら、
「香織、さっきのおばさんと話してた通り、俺は面倒なことが嫌いだから、服着せなくてもいいよね?」
「あ、はい」
「よし、じゃあ、脱がせてあげよう」
そう言って、喜び勇んで香織の背後に回り、ワンピースのジッパーを一気に引き下ろし、腕を抜かせて、脱がせてしまった。
清楚な白のブラジャーとショーツだけの姿になった香織だが、かと言って恥らう様子もない。当たり前のように、晋吾の行為を受け入れている。
興奮の極地に達しているのは、晋吾だけなのだ。
何しろ、毎昼毎夜のごとく、彼の妄想世界の中で“オナペット”として活躍してくれていた香織が、今現実に目の前で艶かしい姿で立っているのだから、仕方ない。
晋吾は高鳴る鼓動の振動で震える呼吸と手を、必死に抑えながら、ブラジャーとショーツも脱がしてしまった。
想像通りの見事なプロポーションである…。
大き過ぎず、小さからずの程よいツンと上向きの乳房から、これも程よく脂肪と筋肉が絡んでいるくびれたウエスト…そして、後部には張りのある質感たっぷりの臀部、前部にはキレイな逆三角を描いている、漆黒の繁みを備えた、形のいい骨盤から、しなやかな長い脚…。
まるでグラビアから飛び出したモデルのような、香織の肢体である。
晋吾はズボン中ではちきれんばかりに緊張した一物を隠しながら、
「これでよし…っと。香織は基本的に屋内で飼うから、これでいいよね」
「はい」
「(よーし。ここからは、益々都合のいいようにしていくか…)」
そう考え、以下のようなことを頭の中で設定してみた。
○日常会話レベル以上のことは、基本的に忘れる。
○化粧の仕方くらいは覚えている。(いつも綺麗でいてもらうように)
○性行為全般はしっかり覚えているし、基本的に大好きである。
自分の考えがまとまり、落ち着いたところで、既に自分の欲求が抑えきれなくなってきた。
おもむろに晋吾自身も、服を脱ぎ始め、全裸になってしまった。
これが通常の香織であるならば、晋吾もさすがに恥じらいを禁じ得ないであろうが、目の前にいるのは、自分が全裸でも恥らうことのない“ヒト科のペット”なのである。ペットの前で裸になることを恥らう飼い主などいないだろう。
現に、香織は、目の前で先程まで赤の他人だった晋吾が全裸になっても、動揺など微塵も無い様子である。
晋吾は、全裸状態で、今や隠すものもなく屹立した一物を天に向けながら、
「香織…。香織はペットなんだから、飼い主に気に入られなくちゃいけないね。なので、まず習慣にしなきゃいけないことを教えるよ。俺が“チンチン!”って言ったら、フェラチオすること。分かるね?」
「はい。分かります」
「じゃあ、“チンチン!”」
「はい」
返事と共に、香織は仁王立ちの晋吾の前で膝まづき、両手で目の前の屹立した一物を、大事そうに覆い持つかのように手を添えながら、晋吾の分身をその可愛らしい口の中いっぱいに咥え込んでいった。
「(ピチャピチャ…ングッ…チュバチュバ…)」
淫靡な音を部屋の中に響かせながら、飼い主に喜んでもらおうと、操作された記憶の片隅に残っている性技をいかんなく発揮しようと努めている。
「うわぁ…最高に気持ちいいよ…香織…」
既に香織の頭を両手で押さえつけ、グイグイと自分の下半身を香織の顔に押し付け始めている。
「ングッ!…ンンッ…グェ…ング…」
喉の奥まで一物が達したのか、襲ってくる嘔吐感を必死に抑えながら、それでもひたむきに晋吾の欲求に応えようとする様は、まさに“愛くるしいペット”さながらであった。
「か、香織…このまま喉の中に出すからね…全部飲み干せよ…うぅっ!!」
次の瞬間、白濁の飛沫が、香織の喉奥深くに一気に放出された。
「!!…ングッ!!…ングッ…ゲボッ…ゲホッ!ゲホッ!」
さすがにむせる香織。
それでも、しっかりと飼い主が放出した液体全てを、その体内に落とし込んでいた。
憧れの香織のフェラによる、至福の瞬間を迎えた後も、晋吾の一物は萎えることを知らなかった。さすがに血気盛んな20歳の身体である。
「うーん…気持ちよかったなぁ…。そうだ、よく出来た香織に、ご褒美をあげなきゃね。これから香織が一番喜ぶご褒美だよ。後を向いて、床に手を付いてごらん」
「あ…はい、こうでしょうか」
膝を伸ばした形で、床に手を付いた体勢をとると、晋吾の眼下には、高々と突き上げられたオシリの真ん中に、パックリと割れたもう一つの谷間が顕わになっている。当然アナルも露呈されているわけで、ついさっきまでの貞淑そうな美しき新妻の姿は、もうそこには無く、ただの“盛りのついたメス犬”のような香織になっていた。
その証拠に、フェラの最中に自身もある程度は感じてしまっていたと思われる形跡が、真ん中の谷間から溢れ出ている、光り輝く分泌液として見て取れるのだから…。
「よし、じゃあ、そのまま動かないようにね」
言うなり、晋吾は香織の尻タブを両手で鷲掴みにし、その濡れ輝く中央の割れ目に、いまだ勢いを衰えさせていない一物を、一気に鎮めていく。
「あぅっ!あぁ…あっ、あぁぁぁ…」
何とも可愛らしく艶かしい嬌声を上げる香織に、晋吾の興奮度は頂点に達し、本能的に腰のピストン速度を速めていく。
「あぁぁっ!!あっ、あっ、あっ…」
香織の体内で、素晴らしい包容力で包み込まれている一物は、彼女の愛液と絡み合い、さらにその緊張度を高めていき、
「あぁ、香織、もうダメだ…このまま…いく…あぁっ!」
ドピュッ!ドピュッ!ドピュッ!
先程のフェラで放出し切れなかった白濁の飛沫が、今度は下腹部から香織の体内に注ぎ込まれていった。
「香織、どう?ご褒美は嬉しかった?」
「はい…ご主人様、とても気持ちよくて、嬉しかったです」
「それは良かった。これからも、ご褒美をたくさんもらえるように、しっかりとペットとして頑張るんだよ。いいね?」
「はい、分かりました」
晋吾は満足であった。当然であろう、憧れだった“お隣の新妻”を、ペットと飼い主という、何とも背徳的で官能的な関係で征服したのだから…。
中で射精してしまったことには、妊娠に対して多少の不安はあったが、まぁ、その時はその時である。
只一つ…獣医に任せるべきか、産婦人科に任せるべきかの迷いはあるが…。
「俺はちょっとシャワーを浴びてくるから、香織はそこで立って待っていなね。ペットなんだから」
「はい…分かりました」
さすがにペットと飼い主の立場の違いは、しっかりと認識させないといけない…香織の身体は、庭先でのホース洗いで十分…そう決めたので、晋吾は一人シャワーを浴びに、バスルームに入って行った。
シャワーから出てみると、香織はうつむき加減で下半身をモジモジさせて、申し訳無さそうに立っていた。
どうしたんだろう…と思ってはみたが、同時に視界に入ってきた彼女の足元の床に溜まっている液体で、状況が飲み込めた。そう、“お漏らし”をしてしまったのだ。
考えてみれば、通常の人間としての行動は、日常会話レベル以外のことを全て忘れさせてしまっている状態なので、当然通常の人間としての排泄の仕方も忘れてしまっていることになっていたのだ。
「あーぁ、香織、ダメじゃないか、そんなとこでお漏らしなんかしちゃ!」
パシンッ!
叱りながら、ある程度の痛さを感じる強度で、彼女のオシリを叩いた。
これも躾である。仕方ない仕打ちであろう。
「ご、ごめんなさい…」
「後でペット用のトイレを買ってきてあげるから、今度からそこですること!いいね?」
「はい…わかりました」
晋吾は再び平手打ちを喰らわすような素振りで、手を頭上にかざしながら、
「もしまた違うところでしたら…これだぞ!」
「はい!もうしません!」
香織はやや身をすくめるような体勢で、反省の色を全身に表していた。
香織の粗相の始末を終え、一段落すると、空腹を覚えた。それもそのはずである。思い出せば、昼食をまだ取っていなかった。
元新妻の香織に何か作らせようかとも考えたが、調理の仕方なども忘れさせてしまったことに気付き、また飼い主がペットに料理をしてもらう…という本末転倒な関係にも戸惑いを感じたので、やはり食事の支度はこれまで一人でやってきたのと同じようにすることに決めた。
ただ、これからはペット用の食事も用意しなくてはならないが…。
まぁ、いずれ機を見て、家事専用のペットを飼ってもいいのである。
晋吾は簡単な調理を済ませ、料理とはお世辞にも言えないものを食卓に並べ、席につく前に自分の足元に食べ物を盛った皿を一枚置いた。
当然のことながら、香織用の食料である。
「香織、ご飯だよ。こっちにおいで」
「あ、はい」
呼び付けて、床を指差し、
「こぼさないように上手に食べるんだよ。ペットなんだから、四つん這いで、手なんか使うような“はしたない食べ方”なんてしちゃダメだよ」
「わかりました」
香織は晋吾の足元に両手両脚を折り畳むように腹這いになり、慣れない口さばきで、皿の上の“餌”を食べ始めた。
「(これがちょっと前までは、あの美しい奥様だったとは…)」
今やその美貌こそそのままではあるが、清楚で貞淑そうな若奥様…といった面影など影を潜め、淫靡なメス犬と化した香織が自分の足元に這いつくばっている…。
晋吾はそんな彼女の食事風景を眺め、その劇的な変貌に驚きと満足を再認識していた。
夕方になり、初夏の日差しも傾きかけてきたところで、香織を玄関前に連れ出して、身体を洗ってあげることにした。
玄関前で四つん這いの格好にさせ、ホースの水を頭からかけながら、全身くまなくの手洗いである。
この日まで、ここまで女体を触り尽くした日などなかっただけに、感動と興奮のあまり、かなり執拗な手洗いになってしまうことは、仕方の無いことであろう。
四つん這いの為、重力でやや垂れ下がり気味のオッパイなどは、その何とも言えない柔らかな感触を存分に楽しみながら、揉みしだくように念入りなマッサージを繰り返し、股間に至っては、一枚一枚のヒダまで洗い尽くすかのような懲りようである。
「あぁ…あぅん…」
香織は敏感な部分に触れられる度に、小さく切ない鳴き声を上げている。
帰宅時間帯の夕暮れ時なので、閑静な住宅街にも帰宅を急ぐ人の往来が増え始めている。当然晋吾宅の家の前も、それなりの人の往来があるわけだが、全裸の女性が庭先で四つん這いになり、艶かしい嬌声を上げながら、その全身を水洗いされているという、通常であれば“異常”な光景にも、全く気を止める様子など無い。
誰しもが、よく見かける“ペットの身体洗い”としか認識していないのだから、当然のことである。
その後、晋吾は家からさほど遠くない駅前のホームセンターまで父親が置いていった車を走らせ、大型ペット用のトイレと、そこに敷き詰める砂を購入し、薬局ではいくつかの薬剤と、香織から聞きだした彼女の愛用のメイク道具を、店員に手伝ってもらいながら購入した。
その間に香織は、晋吾の母親の鏡台とメイク道具で、自分で化粧を落とさせ(メイクに関することは記憶に留めさせておいてあるので)、夜に備えさせたわけだが、元々薄いメイクしか施していない香織なので、メイクを落とした後の顔も、昼の美貌と比べて全く遜色は無かった。
夕食は昼と同様のスタイルで食し、就寝前にもう一度“チンチン”をさせ、そしてさらに“ご褒美”もたっぷりと味合わせてあげて、この日は早々に寝ることにした。
何しろ、この日は劇的なことが多すぎた。そして興奮に継ぐ興奮の連続だった為、さすがに強い疲労感にも襲われていた。
この日は結局、昼からの大学の講義もサボってしまった訳だが、そんなことはどうでもいい程に、充実した一日だった。
「いいか、香織、今度オシッコがしたくなったら、俺が寝ている時でも、ちゃんと部屋の隅に置いてあるトイレの中でするんだぞ。し終わってそのままにしておくと臭くなるんだから、上から砂もかけておくように。わかったね?」
「はい、ご主人様。わかりました」
この辺りは言葉の通じるペットなので、躾も楽である。ヒト科のメスをペットに出来る喜びの一つだ…と、今さらながらに感じていた。
寝るときは一緒のベッドに入れてあげることにした。
ペットと一緒に寝る光景は、今時は不自然でもないであろう。
晋吾は久々に味わう“生きた温もり”に存分に甘えながら、何とも言えない安らかさで、深い眠りに落ちていった。
願わくば、これが長い夢だった…などということが無いように祈りながら…。
(ポチの首輪<第3話>に続く…)
妄想商会(17)~ポチの首輪〈第1話〉~*特殊アイテム
「どうも初めまして。今度隣に引っ越してきた“水谷”と申します。これからお隣同士としてのお付き合いを、どうぞよろしくお願いします。こっちは妻の“香織”です」
「どうぞ、よろしくお願いいたします」
この挨拶が全ての始まりだった。
一週間前の引越しの挨拶…とある閑静な住宅街の一角に新設された新区画の一戸建て住宅に、その“水谷夫妻”が引っ越してきた。
挨拶を受けたのは、水谷夫妻の右隣の一戸建てに独りで住んでいる“新井晋吾 20歳”。
共に某大学の研究機関で働く晋吾の両親は、2年間の契約で、海外の研究チームとの合同プロジェクトのため国外に住んでおり、大学生の晋吾は、必然的に実家での一人暮らし状態になっていた。
どちらかといえば内向的な性格で、対人関係に対してもさほど上手なわけでもなく、女性に至っては、その性格が災いしての、立派な“彼女いない歴20年”である。
そんな晋吾にとって、新婚ホヤホヤの水谷夫妻の姿は、眩しすぎるばかりか、今にも爆発寸前の若き性欲の泉を沸騰させるのに、申し分の無い存在であった。
特に妻である水谷香織は、26歳でセミロングの黒髪がよく似合う、まさに“ご令嬢”タイプであり、華奢ではあるものの胸周りや腰周りの質感は十分に兼ね揃えている抜群のプロポーションなのである。
そんな彼女が、質のいい見るからに高級そうな初夏のワンピースに身を包み、これまた可憐なツバの広い帽子を被って、これから手入れを加えていく庭先の花壇に向かっている姿などは、絵に描いたような“お嬢様スタイル”なのだ。
そんな彼女の存在が、悶々と日々を過ごしている晋吾の邪心に火をつけるのは、当然であろう。
香織の夫である水谷誠二は、30歳の若手ホープの技術系サラリーマンであり、晋吾とは正反対のスポーツマンタイプで、太陽の光の下がよく似合う快活さと逞しさ溢れる、まさに“いい男”なのだ。
男対男の勝負など挑んでは、晋吾などにはまず万に一つの勝ちも期待できないだろうことは明確である。
「(あの奥さんを言いなりにさせたい…)」
いつしか晋吾の中に、まず実現不可能な歪んだ欲望が芽生え始めたのも、自然な成り行きかもしれない。
それからと言うもの、彼のオナニーの妄想世界では必ず香織が淫らな痴態を曝け出すシーンが繰り返され、大学に通う道すがら目に入ってくる洗濯物を干す香織、庭の手入れをする香織を、執着心全開の眼差しで追う日々が続いた。
そんなある日のこと…。
その日は大学の授業も昼からしかないので、昼前に家を出た晋吾は、水谷家の門の前で、香織とばったり鉢合わせをした。
「あ、お隣の…晋吾さんでしたよね。こんにちは」
「ど、どうも…こんにちは」
晋吾の胸は異様に高鳴り、思わずどもってしまう自分にもどかしさを感じつつ、目の前を通り過ぎていく香織を呆然と見送っていた。
彼女の姿が少し離れたところで、ふと水谷家の方に目を向けると、なんと庭先の出入り用の窓ガラスが半分ほど開けられたままで、レースのカーテンが風に揺られて心地よさそうに、窓の外まで棚引いているではないか。
この時間、夫である誠二は、既に出社している時間であり、夫婦二人暮らしの家には誰もいないはずである。
「(なんて無用心な…)」
そんな常識的なことを思いながらも、晋吾の行動は常軌を逸した方向へと向かっていく。
周りに見ている人が誰もいないことを確認すると、さも当たり前のように水谷家の敷地内に入っていった。
日頃内向的でおどおどしている晋吾であるが、己の抑えきれない欲求の為には、こうまで豪胆になれるのかと思うほどの大胆不敵さで、開け放たれた窓から、禁断の新婚夫婦の愛の巣へ足を踏み入れた。
「(ああ…ここが、香織と旦那の部屋なのか…)」
初めて目にした、新婚夫婦の甘い香りが漂うリビングルームに、晋吾の胸の高鳴りは、最高潮へと達していった。
しかし、胸の高鳴りとはある程度のところまで達すると、落ち着きを取り戻すものなのか、彼の行動は何の戸惑いも無く、ある部屋を探す行動へと移っていく。そう、水谷夫婦がその愛を育むベッドルームである。
程なくして2階の一室にそのベッドルームを探し当てた。
高級感ある落ち着いた雰囲気のクイーンサイズのダブルベッド…。
その上に、分かってくださいとでも言うかのように、分かりやすくブルーとピンクのカバーに覆われた枕が横並びに置かれている。
晋吾は当然のように、ピンクの枕に思い切り顔を埋め、そして深呼吸を繰り返した。
「(ああ…これが…香織の匂い…なんて甘い匂いなんだ…)」
これまで、ここまで間近に女性の匂いを感じたことも無い童貞青年には毒とでも言えるような、甘く刺激的な成熟した女性の香りが、晋吾の脳髄を貫いていく。
思う存分、香織の匂いを堪能した晋吾は、ベッドルームの一面の壁に設置されているクローゼットに目を向け、その扉を開いた。
もう何度も目にしている香織の衣装が、窮屈そうに掛けられているクローゼット内の下を見ると、丈の低い3段の引き出しがあることに気付いた途端、彼の鼓動はまたヒートアップしはじめた。
震える手でその一番上の引出しを引くと、彼の目に飛び込んで来たのは、眩いばかりに神々しい光を放つ香織の下着類であった。
単なる布切れに過ぎないパンティやストッキング類が、まさか神々しい光を放つ訳も無いが、今の晋吾には、まさに光り輝く宝石のように思える代物なのだ。
綺麗に折り畳まれた宝石の数々…。
ピンク、白、水色、薄いグリーン、黒、はたまた赤いものまで…決して下品ではなく、上品なレース使いが施されているものが多い宝石の数々を、晋吾は一枚一枚丁寧に開いては、光にかざしてみたり、顔を埋めたりの作業を、ただ黙々と繰り返した。
次に彼が向かうべきところは…当然脱衣場であろうか…。このコースは、こういった侵入ではお決まりの観覧コースなのかもしれない。
一階に戻った彼は、玄関近くにそのお目当ての場所を探し当てた。
風呂場に直結しているそこは、先ほどまできっと香織がシャワーを浴びていたのかもしれないと思われるように、湿気を含む空気に包まれていた。
「(ということは…)」
目論見通り!と叫びたくなるような心の内を誰にでも見透かすことができるような、分かりやすく怪しい笑みをその顔に浮かばせながら、傍らに置いてある脱衣カゴに手を伸ばした。
一番上に置かれている、さっきまで香織が身に付けていたワンピースを取り去ると、その下にはやはり白の上下揃いのブラジャー&パンティが隠されていた。
恐る恐るそのパンティを手にした彼は、今度は一気にその小さな布を裏返す。そして、その目をある一点…そう香織の股間が当っていたクロッチ部分に集中させた。
白い布地に浮かび上がっているややクリーム色の分泌物…これまで何度も妄想の中で溢れるほどに分泌させていた、香織の本当の分泌物が、今目の前にある。
そっと鼻に近づける…生々しい酸っぱさと、アンモニア臭と、香織の体臭が入り混じったなんとも言えない芳しい香りに、脳内全体が溶かされるような感覚…。
自然と彼の空いているほうの手は、自身のズボンのフロント部分を前回にし、既に屹立しまくっている一物を顕わにさせて、扱き始めた。
晋吾は途方も無く幸せであった。
しかし…次の瞬間…。
ガチャガチャ…。
「!?」
晋吾の脳内危険信号が最稼動する音が、玄関のドアから響いてきた。
なんと、香織が帰ってきたのだ。彼女は家の前の通りを少しだけ駅方面に歩いていったところにある、小洒落たパン屋に、自分の昼食用のパンを買いに行っていただけなのである。
下半身を剥き出しにした情けない格好の晋吾にとって、予想もしていなかった最大級のピンチ到来に、咄嗟の状況判断に遅れ、その場から身動きが取れなくなってしまっていた。
このまま一気に香織を襲ってしまおうか…などという破滅的な発想も浮かんできたが、そんな度胸など端から持ち合わせている晋吾ではない。かと言って、玄関と言う最も近い脱出ロは塞がれ、侵入口であった庭先の窓に向かう為には、玄関と直結している廊下を通り、リビングを抜けなければならない。
今やお隣同士という距離で、香織と面識が浅くない晋吾のことを、彼女は瞬時に見抜くであろう。まさに、絶体絶命のピンチだった。
「(どうしよう…ここにいても、すぐに見つかってしまう…見つかった時、俺は…)」
自分の人生にとって、破滅的な将来像しか浮かんで来なかった。絶望を確定された時、人は身動きすらできなくなるのであろうか…。現に、晋吾はその場からどうすることもできなくなっていた。
………………。
おかしい…。
玄関とこの脱衣場はほぼ隣り合わせの距離なのだから、玄関を開けた香織は、本来ならすぐにここを通り過ぎなければならないはずである。しかし、それに必要と思われる時間が経過しても、彼女は通り過ぎることはなかった。
「(玄関先で何かしているのか?)」
そうも思って聴覚に全神経を集中させてみたが、まるで人の気配すら感じないようである。
「(誰かが帰ってきたって、俺が間違えて思い込んだだけなのか?)」
自分に都合がいいような解釈も沸き上がってくるが、それでもまだ晋吾は身動きが取れずにいた。
「晋吾さん、大丈夫ですよ。こちらへどうぞー」
ドキリとした。
いきなりリビングの方から、それも自分を名指しで呼ぶ男性の声が聞こえたからだ。何故自分がここにいることを知っているのか。そもそも、聞いたことも無いような音質の不気味な声なのである。
「そこにいても何も出来ないでしょう。安心してどうぞこちらへ」
再びその声の主が語りかけてきた。
確かに…この場にこのままいても何も始まらず、どうすることもできないのだ。それに、相手が名指しで呼んでいる以上、少なくとも相手は自分のことを知っているようなのだ。今は、その声にすがるしか無いようである。
覚悟を決めて、晋吾が廊下に足を踏み入れた時…「!?」
あまりの驚きに、まさに心臓が止まるかと思った。なんと、自分のすぐ側まで香織が歩み寄ってきている状態で静止していたのだ。
「(見つかった!!)」と思わず目を閉じて、首をすぼめてはみたものの、香織の叫び声も、身じろぎする音も聞こえてこない。恐る恐る目を開けてみると、さっきと全く状態が変っていないではないか…。
よく見ると、その静止している香織は、瞬きすらしていないのである。まるで時間が止まっているかのように…。
「ハハハ…安心していいですよ。ご察しの通り、時間が止まってますから」
再び掛けられた怪しい声の方に目を向けると、これまた、一瞬ドキッとした。
そこにはいかにも怪しい、黒装束黒マントに身を包んだ男が立っていたのである。
「驚かせてスミマセンね。いやー間に合ってよかったですねー。危機一髪でしたね」
「ア、アンタは…誰?」
「申し遅れました。私は妄想商会のシルク…と申します。以後お見知り置きを…」
「妄想…商会?」
「ええ。少し私の話をしましょう。私は魔界と人間界を行き来する商人です。いつも魔界から人間界をリサーチしていて、商品になる素材を探し求めているのです」
「魔界?商品?…何のことだか…」
「先ほども言いましたが、私は魔界と人間界を往来する、貿易商人です。私はあなたに、あなたの欲望満たすことのできる品物を提供します。その代価は、人間界の通貨では意味がありません。そう…あなたの欲望エネルギーです」
「俺の欲望?」
「おや…あなたの鬱屈した性への渇望が、私をここに導いたのですが…ずっと思っていたでしょう。そこにいる香織さんを支配したい…と」
「!!…な、なぜそんなことを…」
「何度も言いますが、私は魔界の住人ですから、あなた方が隠したいと思っていることや、考えていることを見透かすくらいのことは、私にとってはごく簡単なことなのですよ」
しばしの間、晋吾も自分と今の状況を納得させる答えを導き出すかのような問答が続き、ようやくに晋吾にも今の状況が理解できたようである。その証拠に、彼の態度にも、かなり落ち着きが戻ってきていた。
「なるほど、それで俺の欲望エネルギーを得るために、時間を止めて俺を助けたってことなんだね」
「その通りです」
「まぁ、今のこの現状を見れば、シルクさんのパワーを認めざるを得ないし、助けてくれた恩もあるし、協力しますよ」
「フフフ…協力…ではなくて、率先してやりたいのでしょ?私は逆にそうでないと困ってしまうのですよ」
「ハハハ…全部お見通しなんだね」
「私に心の内の隠し事は通用しませんよ」
それから二人は、晋吾の歪んだ欲求を満たすための密談を、少しの間交わし、
「分かりました。では、これを使ってください」
そう言って彼が取り出したのは、何の変哲も無い犬の首輪と手綱であった。
「これは?」
「これは元々、魔界の犬を飼いならす為のアイテムなんです。魔界の犬は多分想像つくでしょうが、それは恐ろしい生き物でしてね。この首輪と手綱には強力な支配力が宿っています。なので、これを香織さんに使えば…どうなるかは分かりますよね」
「香織を…支配…」
「ハイハイ」
「思い通りに…」
「ハイハイ」
「但し、完全に服従させるためには、それなりの躾が必要になる時もあります。まぁ、人間界でペットを飼うのと、さほどの違いはありませんね」
「香織が…ペット…」
「飲み込み早いですねー」
「でも、旦那である誠二さんの立場はどうなる?」
「魔界の力を甘く見てもらっちゃ困りますねー。これを付けたが最後、付けられた方のそれまでの存在は全て無に帰します。香織さんのご両親すら、彼女を生んだ覚えもなくるでしょう」
「えっ!?そんなこと…できるの?」
「出来るか出来ないかは、あなたがそれをやるかやらないかで、分かることです。余計な疑心暗鬼よりも、結果だけ見ていきましょうね」
さすがに商人と自称するだけあり、シルクはかなりシンプル且つスマートな思考回路の持ち主のようである。
「香織さんの一生に関わる問題ですから、強要はしませんよ。とりあえずもうあなたはこの危機的状態からは解放される立場な訳で、このままあなたが立ち去った後に、私が時間を元に戻せば、何事もなかった…で決着しますから。どうするかは自分で決めてください」
「うっ……や、やるよ、もちろん…こんなチャンスは二度とないだろうし」
「そうですか、では、今のうちに首輪を付けて上げてください。その後に時間を戻しますから」
「首輪を付けた後でも、俺はここにいても大丈夫なの?」
「あなたが飼い主ですよ。当たり前でしょう」
「う、うん…」
晋吾は、渡された首輪を持ち、恐る恐る香織に近づいて行った…。
晋吾の至近距離に迫る香織の顔…。自分のスイートホーム内にいるはずも無い男を目の当たりにしても、視線すら変らない香織の状態に、安堵感に包まれたいけない興奮が、晋吾の次の行動を駆り立てていく。
これまで何度も挨拶程度の言葉を交わしてきた間柄ではあるが、これほどまでに香織に接近したことはなかった。
鼻腔をくすぐる甘く上品な香織の体臭に、晋吾の脳はそれだけで痺れまくって、疼く下半身の一物は既にズボンの前を大きく張らして、外への圧力を高めていた。
震える手で香織の首に首輪を巻き終えた。
今だ彼女の時間は止まったままなので、これといった変化は確認できない。
「これでいいの?」
「ええ、それだけです」
「これで、時間を戻せば香織は僕の飼犬…。周りの環境も香織の存在を“無かったもの”にしちゃうんだよね?…でもさ、香織自身の記憶はどうなの?」
「周りの人たちは、彼女のことを<ヒト科のヒト>という生物的な捉え方をしますが、これでは晋吾さんと同じ生き物になってしまいますね。でも、ご安心を。<ヒト科のヒト>でも、<ペット用ヒト>なんていう、本来有り得ないカテゴリーとして、きちんと区分け認識してくれますよ。それに、香織さん自身も、自分はペット用ヒトなんだという認識しかなく、それまでの生い立ちについては忘却され、過去のことには一切の関心が無くなります。なので、名前なども今この時点で付け直すことも可能ですよ」
「じゃあ、通常の<ヒト>の文化感とかは、一切なくなっちゃうわけ?」
「ええ、そういうことですね。服飾文化も、食文化も、全て晋吾さん、あなたの価値観が基準となりますよ」
「うわー、すごい効果だね…」
「言ったでしょ、あなたの妄想を叶えるのが私の投資だって。これくらいのことはさせていただきますよ」
「うん、分かった。じゃあ、その投資に敵う様しっかりと香織を飼うことにするよ」
「では、理解を頂いたところで、そろそろ時間を動かしましょうかね」
次の瞬間…。
それまで全くの無音世界から、周囲の僅かな生活音とともに時間が動き出す。
「…あの…私…」
首輪を付けられた香織が、今の状況を理解できずに戸惑いの表情で立ちすくんでいる。
「さぁ、晋吾さん、手綱を付けてあげてくださいな。それで彼女はあなたを飼い主と認識し始めますよ」
「あ、あぁ、分かった」
晋吾は言われるがままに、首輪の金具と手綱を連結させると、
「(コホンッ)…さ、さぁ…か、香織、今日から僕のペットだよ。分かるか?」
「…か・お・り?」
「そ、そうだったね、名前をまだ覚えてないんだったっけ。君の名前は<香織>だよ。そして僕が飼い主の晋吾。しっかり覚えるようにね」
「…私は香織…そしてあなたは晋吾…」
「おっとっと、ペットと飼い主の立場ははっきりと区分けしないとダメだよ。飼い主に対しては<晋吾様>と呼んでほしいね」
「…晋吾様」
「そうそう、これからはそう呼ぶんだよ。いいね?」
「…はい」
「ハハハ、晋吾さん、中々上手ですねー。この調子であれば、ひとまず私は必要なさそうですね。またいずれ顔を出しますよ。それでは」
シルクはそれだけ言い残すと、スーッと空気に溶け込むように消えていった。
と同時に、それまで香織とのやりとりに夢中で気付かなかった周囲の変化に驚いた。
なんと、家の中の風景が一変してしまっているのだ。
それまでの甘い新婚生活を演出していたインテリアは、青を基調とした男性色っぽいインテリアに一新され、そこ彼処に点在していた香織のものと思われる服や小物類も全て姿を消してしまっている。
これがシルクの言っていた<香織の存在を無かったものとする>という効果なのだとすぐに認識し、魔界の恐るべき力に、またまた驚かされていた。
多分、このインテリアは、今や<かつての旦那>となってしまった水谷誠二の好みなのだろう。
ということは、この家の今の設定は、誠二の一人住まい…とうことにでもなったのだろう。
晋吾は目の前のヒト型ペット香織と、それをとりまく環境の変化に感嘆しつつ、これからの異常な生活への興奮で、胸を高鳴らせていた。
(ポチの首輪<第2話>に続く…)
「どうぞ、よろしくお願いいたします」
この挨拶が全ての始まりだった。
一週間前の引越しの挨拶…とある閑静な住宅街の一角に新設された新区画の一戸建て住宅に、その“水谷夫妻”が引っ越してきた。
挨拶を受けたのは、水谷夫妻の右隣の一戸建てに独りで住んでいる“新井晋吾 20歳”。
共に某大学の研究機関で働く晋吾の両親は、2年間の契約で、海外の研究チームとの合同プロジェクトのため国外に住んでおり、大学生の晋吾は、必然的に実家での一人暮らし状態になっていた。
どちらかといえば内向的な性格で、対人関係に対してもさほど上手なわけでもなく、女性に至っては、その性格が災いしての、立派な“彼女いない歴20年”である。
そんな晋吾にとって、新婚ホヤホヤの水谷夫妻の姿は、眩しすぎるばかりか、今にも爆発寸前の若き性欲の泉を沸騰させるのに、申し分の無い存在であった。
特に妻である水谷香織は、26歳でセミロングの黒髪がよく似合う、まさに“ご令嬢”タイプであり、華奢ではあるものの胸周りや腰周りの質感は十分に兼ね揃えている抜群のプロポーションなのである。
そんな彼女が、質のいい見るからに高級そうな初夏のワンピースに身を包み、これまた可憐なツバの広い帽子を被って、これから手入れを加えていく庭先の花壇に向かっている姿などは、絵に描いたような“お嬢様スタイル”なのだ。
そんな彼女の存在が、悶々と日々を過ごしている晋吾の邪心に火をつけるのは、当然であろう。
香織の夫である水谷誠二は、30歳の若手ホープの技術系サラリーマンであり、晋吾とは正反対のスポーツマンタイプで、太陽の光の下がよく似合う快活さと逞しさ溢れる、まさに“いい男”なのだ。
男対男の勝負など挑んでは、晋吾などにはまず万に一つの勝ちも期待できないだろうことは明確である。
「(あの奥さんを言いなりにさせたい…)」
いつしか晋吾の中に、まず実現不可能な歪んだ欲望が芽生え始めたのも、自然な成り行きかもしれない。
それからと言うもの、彼のオナニーの妄想世界では必ず香織が淫らな痴態を曝け出すシーンが繰り返され、大学に通う道すがら目に入ってくる洗濯物を干す香織、庭の手入れをする香織を、執着心全開の眼差しで追う日々が続いた。
そんなある日のこと…。
その日は大学の授業も昼からしかないので、昼前に家を出た晋吾は、水谷家の門の前で、香織とばったり鉢合わせをした。
「あ、お隣の…晋吾さんでしたよね。こんにちは」
「ど、どうも…こんにちは」
晋吾の胸は異様に高鳴り、思わずどもってしまう自分にもどかしさを感じつつ、目の前を通り過ぎていく香織を呆然と見送っていた。
彼女の姿が少し離れたところで、ふと水谷家の方に目を向けると、なんと庭先の出入り用の窓ガラスが半分ほど開けられたままで、レースのカーテンが風に揺られて心地よさそうに、窓の外まで棚引いているではないか。
この時間、夫である誠二は、既に出社している時間であり、夫婦二人暮らしの家には誰もいないはずである。
「(なんて無用心な…)」
そんな常識的なことを思いながらも、晋吾の行動は常軌を逸した方向へと向かっていく。
周りに見ている人が誰もいないことを確認すると、さも当たり前のように水谷家の敷地内に入っていった。
日頃内向的でおどおどしている晋吾であるが、己の抑えきれない欲求の為には、こうまで豪胆になれるのかと思うほどの大胆不敵さで、開け放たれた窓から、禁断の新婚夫婦の愛の巣へ足を踏み入れた。
「(ああ…ここが、香織と旦那の部屋なのか…)」
初めて目にした、新婚夫婦の甘い香りが漂うリビングルームに、晋吾の胸の高鳴りは、最高潮へと達していった。
しかし、胸の高鳴りとはある程度のところまで達すると、落ち着きを取り戻すものなのか、彼の行動は何の戸惑いも無く、ある部屋を探す行動へと移っていく。そう、水谷夫婦がその愛を育むベッドルームである。
程なくして2階の一室にそのベッドルームを探し当てた。
高級感ある落ち着いた雰囲気のクイーンサイズのダブルベッド…。
その上に、分かってくださいとでも言うかのように、分かりやすくブルーとピンクのカバーに覆われた枕が横並びに置かれている。
晋吾は当然のように、ピンクの枕に思い切り顔を埋め、そして深呼吸を繰り返した。
「(ああ…これが…香織の匂い…なんて甘い匂いなんだ…)」
これまで、ここまで間近に女性の匂いを感じたことも無い童貞青年には毒とでも言えるような、甘く刺激的な成熟した女性の香りが、晋吾の脳髄を貫いていく。
思う存分、香織の匂いを堪能した晋吾は、ベッドルームの一面の壁に設置されているクローゼットに目を向け、その扉を開いた。
もう何度も目にしている香織の衣装が、窮屈そうに掛けられているクローゼット内の下を見ると、丈の低い3段の引き出しがあることに気付いた途端、彼の鼓動はまたヒートアップしはじめた。
震える手でその一番上の引出しを引くと、彼の目に飛び込んで来たのは、眩いばかりに神々しい光を放つ香織の下着類であった。
単なる布切れに過ぎないパンティやストッキング類が、まさか神々しい光を放つ訳も無いが、今の晋吾には、まさに光り輝く宝石のように思える代物なのだ。
綺麗に折り畳まれた宝石の数々…。
ピンク、白、水色、薄いグリーン、黒、はたまた赤いものまで…決して下品ではなく、上品なレース使いが施されているものが多い宝石の数々を、晋吾は一枚一枚丁寧に開いては、光にかざしてみたり、顔を埋めたりの作業を、ただ黙々と繰り返した。
次に彼が向かうべきところは…当然脱衣場であろうか…。このコースは、こういった侵入ではお決まりの観覧コースなのかもしれない。
一階に戻った彼は、玄関近くにそのお目当ての場所を探し当てた。
風呂場に直結しているそこは、先ほどまできっと香織がシャワーを浴びていたのかもしれないと思われるように、湿気を含む空気に包まれていた。
「(ということは…)」
目論見通り!と叫びたくなるような心の内を誰にでも見透かすことができるような、分かりやすく怪しい笑みをその顔に浮かばせながら、傍らに置いてある脱衣カゴに手を伸ばした。
一番上に置かれている、さっきまで香織が身に付けていたワンピースを取り去ると、その下にはやはり白の上下揃いのブラジャー&パンティが隠されていた。
恐る恐るそのパンティを手にした彼は、今度は一気にその小さな布を裏返す。そして、その目をある一点…そう香織の股間が当っていたクロッチ部分に集中させた。
白い布地に浮かび上がっているややクリーム色の分泌物…これまで何度も妄想の中で溢れるほどに分泌させていた、香織の本当の分泌物が、今目の前にある。
そっと鼻に近づける…生々しい酸っぱさと、アンモニア臭と、香織の体臭が入り混じったなんとも言えない芳しい香りに、脳内全体が溶かされるような感覚…。
自然と彼の空いているほうの手は、自身のズボンのフロント部分を前回にし、既に屹立しまくっている一物を顕わにさせて、扱き始めた。
晋吾は途方も無く幸せであった。
しかし…次の瞬間…。
ガチャガチャ…。
「!?」
晋吾の脳内危険信号が最稼動する音が、玄関のドアから響いてきた。
なんと、香織が帰ってきたのだ。彼女は家の前の通りを少しだけ駅方面に歩いていったところにある、小洒落たパン屋に、自分の昼食用のパンを買いに行っていただけなのである。
下半身を剥き出しにした情けない格好の晋吾にとって、予想もしていなかった最大級のピンチ到来に、咄嗟の状況判断に遅れ、その場から身動きが取れなくなってしまっていた。
このまま一気に香織を襲ってしまおうか…などという破滅的な発想も浮かんできたが、そんな度胸など端から持ち合わせている晋吾ではない。かと言って、玄関と言う最も近い脱出ロは塞がれ、侵入口であった庭先の窓に向かう為には、玄関と直結している廊下を通り、リビングを抜けなければならない。
今やお隣同士という距離で、香織と面識が浅くない晋吾のことを、彼女は瞬時に見抜くであろう。まさに、絶体絶命のピンチだった。
「(どうしよう…ここにいても、すぐに見つかってしまう…見つかった時、俺は…)」
自分の人生にとって、破滅的な将来像しか浮かんで来なかった。絶望を確定された時、人は身動きすらできなくなるのであろうか…。現に、晋吾はその場からどうすることもできなくなっていた。
………………。
おかしい…。
玄関とこの脱衣場はほぼ隣り合わせの距離なのだから、玄関を開けた香織は、本来ならすぐにここを通り過ぎなければならないはずである。しかし、それに必要と思われる時間が経過しても、彼女は通り過ぎることはなかった。
「(玄関先で何かしているのか?)」
そうも思って聴覚に全神経を集中させてみたが、まるで人の気配すら感じないようである。
「(誰かが帰ってきたって、俺が間違えて思い込んだだけなのか?)」
自分に都合がいいような解釈も沸き上がってくるが、それでもまだ晋吾は身動きが取れずにいた。
「晋吾さん、大丈夫ですよ。こちらへどうぞー」
ドキリとした。
いきなりリビングの方から、それも自分を名指しで呼ぶ男性の声が聞こえたからだ。何故自分がここにいることを知っているのか。そもそも、聞いたことも無いような音質の不気味な声なのである。
「そこにいても何も出来ないでしょう。安心してどうぞこちらへ」
再びその声の主が語りかけてきた。
確かに…この場にこのままいても何も始まらず、どうすることもできないのだ。それに、相手が名指しで呼んでいる以上、少なくとも相手は自分のことを知っているようなのだ。今は、その声にすがるしか無いようである。
覚悟を決めて、晋吾が廊下に足を踏み入れた時…「!?」
あまりの驚きに、まさに心臓が止まるかと思った。なんと、自分のすぐ側まで香織が歩み寄ってきている状態で静止していたのだ。
「(見つかった!!)」と思わず目を閉じて、首をすぼめてはみたものの、香織の叫び声も、身じろぎする音も聞こえてこない。恐る恐る目を開けてみると、さっきと全く状態が変っていないではないか…。
よく見ると、その静止している香織は、瞬きすらしていないのである。まるで時間が止まっているかのように…。
「ハハハ…安心していいですよ。ご察しの通り、時間が止まってますから」
再び掛けられた怪しい声の方に目を向けると、これまた、一瞬ドキッとした。
そこにはいかにも怪しい、黒装束黒マントに身を包んだ男が立っていたのである。
「驚かせてスミマセンね。いやー間に合ってよかったですねー。危機一髪でしたね」
「ア、アンタは…誰?」
「申し遅れました。私は妄想商会のシルク…と申します。以後お見知り置きを…」
「妄想…商会?」
「ええ。少し私の話をしましょう。私は魔界と人間界を行き来する商人です。いつも魔界から人間界をリサーチしていて、商品になる素材を探し求めているのです」
「魔界?商品?…何のことだか…」
「先ほども言いましたが、私は魔界と人間界を往来する、貿易商人です。私はあなたに、あなたの欲望満たすことのできる品物を提供します。その代価は、人間界の通貨では意味がありません。そう…あなたの欲望エネルギーです」
「俺の欲望?」
「おや…あなたの鬱屈した性への渇望が、私をここに導いたのですが…ずっと思っていたでしょう。そこにいる香織さんを支配したい…と」
「!!…な、なぜそんなことを…」
「何度も言いますが、私は魔界の住人ですから、あなた方が隠したいと思っていることや、考えていることを見透かすくらいのことは、私にとってはごく簡単なことなのですよ」
しばしの間、晋吾も自分と今の状況を納得させる答えを導き出すかのような問答が続き、ようやくに晋吾にも今の状況が理解できたようである。その証拠に、彼の態度にも、かなり落ち着きが戻ってきていた。
「なるほど、それで俺の欲望エネルギーを得るために、時間を止めて俺を助けたってことなんだね」
「その通りです」
「まぁ、今のこの現状を見れば、シルクさんのパワーを認めざるを得ないし、助けてくれた恩もあるし、協力しますよ」
「フフフ…協力…ではなくて、率先してやりたいのでしょ?私は逆にそうでないと困ってしまうのですよ」
「ハハハ…全部お見通しなんだね」
「私に心の内の隠し事は通用しませんよ」
それから二人は、晋吾の歪んだ欲求を満たすための密談を、少しの間交わし、
「分かりました。では、これを使ってください」
そう言って彼が取り出したのは、何の変哲も無い犬の首輪と手綱であった。
「これは?」
「これは元々、魔界の犬を飼いならす為のアイテムなんです。魔界の犬は多分想像つくでしょうが、それは恐ろしい生き物でしてね。この首輪と手綱には強力な支配力が宿っています。なので、これを香織さんに使えば…どうなるかは分かりますよね」
「香織を…支配…」
「ハイハイ」
「思い通りに…」
「ハイハイ」
「但し、完全に服従させるためには、それなりの躾が必要になる時もあります。まぁ、人間界でペットを飼うのと、さほどの違いはありませんね」
「香織が…ペット…」
「飲み込み早いですねー」
「でも、旦那である誠二さんの立場はどうなる?」
「魔界の力を甘く見てもらっちゃ困りますねー。これを付けたが最後、付けられた方のそれまでの存在は全て無に帰します。香織さんのご両親すら、彼女を生んだ覚えもなくるでしょう」
「えっ!?そんなこと…できるの?」
「出来るか出来ないかは、あなたがそれをやるかやらないかで、分かることです。余計な疑心暗鬼よりも、結果だけ見ていきましょうね」
さすがに商人と自称するだけあり、シルクはかなりシンプル且つスマートな思考回路の持ち主のようである。
「香織さんの一生に関わる問題ですから、強要はしませんよ。とりあえずもうあなたはこの危機的状態からは解放される立場な訳で、このままあなたが立ち去った後に、私が時間を元に戻せば、何事もなかった…で決着しますから。どうするかは自分で決めてください」
「うっ……や、やるよ、もちろん…こんなチャンスは二度とないだろうし」
「そうですか、では、今のうちに首輪を付けて上げてください。その後に時間を戻しますから」
「首輪を付けた後でも、俺はここにいても大丈夫なの?」
「あなたが飼い主ですよ。当たり前でしょう」
「う、うん…」
晋吾は、渡された首輪を持ち、恐る恐る香織に近づいて行った…。
晋吾の至近距離に迫る香織の顔…。自分のスイートホーム内にいるはずも無い男を目の当たりにしても、視線すら変らない香織の状態に、安堵感に包まれたいけない興奮が、晋吾の次の行動を駆り立てていく。
これまで何度も挨拶程度の言葉を交わしてきた間柄ではあるが、これほどまでに香織に接近したことはなかった。
鼻腔をくすぐる甘く上品な香織の体臭に、晋吾の脳はそれだけで痺れまくって、疼く下半身の一物は既にズボンの前を大きく張らして、外への圧力を高めていた。
震える手で香織の首に首輪を巻き終えた。
今だ彼女の時間は止まったままなので、これといった変化は確認できない。
「これでいいの?」
「ええ、それだけです」
「これで、時間を戻せば香織は僕の飼犬…。周りの環境も香織の存在を“無かったもの”にしちゃうんだよね?…でもさ、香織自身の記憶はどうなの?」
「周りの人たちは、彼女のことを<ヒト科のヒト>という生物的な捉え方をしますが、これでは晋吾さんと同じ生き物になってしまいますね。でも、ご安心を。<ヒト科のヒト>でも、<ペット用ヒト>なんていう、本来有り得ないカテゴリーとして、きちんと区分け認識してくれますよ。それに、香織さん自身も、自分はペット用ヒトなんだという認識しかなく、それまでの生い立ちについては忘却され、過去のことには一切の関心が無くなります。なので、名前なども今この時点で付け直すことも可能ですよ」
「じゃあ、通常の<ヒト>の文化感とかは、一切なくなっちゃうわけ?」
「ええ、そういうことですね。服飾文化も、食文化も、全て晋吾さん、あなたの価値観が基準となりますよ」
「うわー、すごい効果だね…」
「言ったでしょ、あなたの妄想を叶えるのが私の投資だって。これくらいのことはさせていただきますよ」
「うん、分かった。じゃあ、その投資に敵う様しっかりと香織を飼うことにするよ」
「では、理解を頂いたところで、そろそろ時間を動かしましょうかね」
次の瞬間…。
それまで全くの無音世界から、周囲の僅かな生活音とともに時間が動き出す。
「…あの…私…」
首輪を付けられた香織が、今の状況を理解できずに戸惑いの表情で立ちすくんでいる。
「さぁ、晋吾さん、手綱を付けてあげてくださいな。それで彼女はあなたを飼い主と認識し始めますよ」
「あ、あぁ、分かった」
晋吾は言われるがままに、首輪の金具と手綱を連結させると、
「(コホンッ)…さ、さぁ…か、香織、今日から僕のペットだよ。分かるか?」
「…か・お・り?」
「そ、そうだったね、名前をまだ覚えてないんだったっけ。君の名前は<香織>だよ。そして僕が飼い主の晋吾。しっかり覚えるようにね」
「…私は香織…そしてあなたは晋吾…」
「おっとっと、ペットと飼い主の立場ははっきりと区分けしないとダメだよ。飼い主に対しては<晋吾様>と呼んでほしいね」
「…晋吾様」
「そうそう、これからはそう呼ぶんだよ。いいね?」
「…はい」
「ハハハ、晋吾さん、中々上手ですねー。この調子であれば、ひとまず私は必要なさそうですね。またいずれ顔を出しますよ。それでは」
シルクはそれだけ言い残すと、スーッと空気に溶け込むように消えていった。
と同時に、それまで香織とのやりとりに夢中で気付かなかった周囲の変化に驚いた。
なんと、家の中の風景が一変してしまっているのだ。
それまでの甘い新婚生活を演出していたインテリアは、青を基調とした男性色っぽいインテリアに一新され、そこ彼処に点在していた香織のものと思われる服や小物類も全て姿を消してしまっている。
これがシルクの言っていた<香織の存在を無かったものとする>という効果なのだとすぐに認識し、魔界の恐るべき力に、またまた驚かされていた。
多分、このインテリアは、今や<かつての旦那>となってしまった水谷誠二の好みなのだろう。
ということは、この家の今の設定は、誠二の一人住まい…とうことにでもなったのだろう。
晋吾は目の前のヒト型ペット香織と、それをとりまく環境の変化に感嘆しつつ、これからの異常な生活への興奮で、胸を高鳴らせていた。
(ポチの首輪<第2話>に続く…)
妄想商会(16)~黒水晶〈第7話〉~*特殊アイテム
闇商人シルクと板垣聡史の淫欲で支配された喫茶店がオープンして、数日が経過していた。
「いらっしゃいませー♪」
玲奈のいつもと変らぬ明るいウェルカムコールとともに、2階メンバーフロアのエレベーターの扉が開き、20歳代と見える、紺のタイトスカートがよく似合うスーツ姿の女性が入ってきた。営業の間の空き時間で休憩がてらに立ち寄ったと見えるその女性客は、メンバーになってから初めてこのフロアーに訪れたらしく、あたりをキョロキョロしている。
「お客様、このフロアのご利用方法はご存知ですか?」
「いえ、今日が初めてです」
「そうでしたかー♪では、簡単にご案内させて頂きますね♪」
玲奈は明るく元気に応対しながら、驚くべきことを口にし始めた。
「まず、このフロアにお越し頂きましたら、お召しになっているものを全て脱いで頂いて、私共が毎回お渡しするこのカゴの中に入れて、そちらの棚に置いてくださいませ♪」
「あの、靴もですか?」
「ええ、そうです♪ご覧の通り、このフロアはメンバーのお客様に最高の寛ぎを感じて頂くことをテーマにさせていただいていますので♪」
「そうですね、皆さん気持ちよさそう…」
「はい♪皆様に大変喜んでいただいておりますー♪それと、脱いだショーツだけこちらのブラックボックスの中にお入れください。これは大変ご好評頂いている、お帰りの時の“お楽しみボックス”で、お帰りの際にはこの中身の見えない箱の中から私共が一枚だけ取り出しますので、それを穿いてお帰りいただきます♪“お洒落なショーツ交換”です♪素敵な企画でしょう♪あ、もし生理中の時には、衛生上ショーツのみ穿いたままでのご利用となり、この交換企画にはご参加頂けませんので、ご了承くださいませ」
「それは仕方ないですね、こんな素敵なフロアを汚しては申し訳ないですから」
「ご理解ありがとうございますー♪ではお客様、本日はこちらのカゴをご使用ください♪脱衣がお済みになりましたら、お席にご案内いたします♪」
何と言うやりとりか…。
ただ喫茶店にお茶しに来ただけなのに、店員から『全裸になれ』と言われ、その驚くべき要求に対して何の疑いも持たずに『はい』と受け入れる客。それも、帰る時にはこのフロアーを利用している客の、誰の物かも分からぬパンティを穿いて帰らなければならないのだ。
使用中のパンティを交換して穿くなど、どんなに仲の良い間柄でも憚られることだろうが、これも“お洒落な女性のための素敵な企画”として、嬉々として受け入れる客…。
見渡せば、このフロアーには既に6人ほどの女性客がおり、その誰もがやはり全裸姿で、それぞれが案内された席で、満足そうに寛いでいる。
彼女たちは、この選ばれた者だけが利用できる空間に、各々の脳内で描き出せる限りのステイタス性と憧れを感じているのだ。
先ほどの客も言われた通りの全裸状態になり、どこを隠すでもなく、堂々と玲奈に案内された席へ腰を下ろした。
聡史は自らがチョイスした、この美女の楽園のような光景を、2階にも設置してあるカウンター内から、股間の一物をはちきれんばかりに膨張させながら見入っている。
玲奈が先ほど案内したばかりの客のもとに行き、
「お客様、お決まりですか?」
「えっとぉ…色々あって迷いますね、オススメとかありますか?」
「そうですねー、失礼ですが“フェラチオ”のご経験はありますか?」
「え、あ、はい。ありますよ」
「でしたら、回数限定なんですが、“マスターのチ○ポからお口で生絞りミルク入りコーヒー”は人気ですよー♪」
「へー、まだあるんですか?」
「今日はまだ大丈夫だと思いますよ♪」
「では、それをお願いします。それと…この“玲奈のホットバナナ”も一緒で。これは玲奈さんが作るのですか?」
「はい♪…っていうか、作るというよりは、愛情込めて温めさせていただきますぅ♪」
注文を取り終えた玲奈が聡史のもとに歩み寄り、
「マスター、限定ミルクコーヒーのご注文いただきましたぁ♪3番テーブルのお客様ですー」
「お、そっかぁ、オッケー。じゃあ、コーヒーの準備お願いね」
「はーい♪」
聡史を見送った玲奈は、早速コーヒーを炒れ始めながら、取り出した一本のバナナの皮を剥き、
「はぁぅ…」
なんとそれを自分のオ○ンコにすっぽりと挿入してしまった。“ホットバナナ”を作成中なのである。
聡史は限定ミルクコーヒーの注文を受けた客のもとに赴き、
「お客様、限定ミルクコーヒーのご注文ありがとうございます。では早速お口で搾り出してください」
そう言って、彼女の目の前でズボンのジッパーを下ろし、既に半勃起している一物を取り出した。
「あ、はーい。では…(ハムッ…レロレロ…チュバチュバッ)」
「おぉ…お客様、お上手ですねー、これならすぐに絞れそうですねー、おぉぉ…玲奈ぁ、早くコーヒー頼むー」
その女性客がヨダレを垂れ流し、おいしそうにしゃぶり始めて程なく、
「マスター、コーヒーここに置きますね♪」
玲奈がコーヒーを運んできた。
「お、おぉ…サ、サンキュー、もう、出そうだ…お客様、お待たせしました…じゃあ、たっぷりのミルクをコーヒーに注ぎますね」
言うなり、優しく彼女の口からチ○ポを抜き出し、用意されたコーヒーめがけて“ドピュッ!ドピュッ!”と、勢いよく濃白の飛沫を浴びせかけた。
コーヒーカップの中に収まりきらなかった飛沫は、遠慮なくカップの縁を汚し、カップの中に命中したものは質量のあるドロドロの液体よろしく、コーヒーの中に沈殿し始め、コーヒーの熱で温められたタンパク成分が白い膜のように漂っていた。
「よくかき混ぜてお飲みくださいね」
「わぁ、おいしそうですねー」
横にいた玲奈も、
「はーい、こちらもお待たせしましたぁ♪“玲奈のホットバナナ”ですぅ♪よーく温まってますよー」
玲奈はおもむろに剥き出しになっている股間部分に手をやり、自ら数本の指をオ○ンコに挿入させ、少しこねくり回しながら、ヌルッとした液状の膜に覆われ、全体に光沢を帯びたバナナを取り出して、皿の上に盛り付けた。
「こっちもおいしそうですね!」
その女性客は、こうしたパフォーマンスを“鮮やかなシェフの手並み”的感覚で認識しているのか、目を輝かせてその一部始終に見入っていた。
こんな調子で、続々と破廉恥極まりないオーダーが飛び交い、一階のエコノミーフロアに比べると、このメンバーフロアは、正に異常なインモラル世界と化していた。
しかし、客の女性達にとっては、ここで寛ぐことが彼女達にとっての“最高の癒し空間”になっている。もし万が一、今ここに警察の立ち入り検査が入ったとしても、この結界内で行われている、また起こっていることは、全て世の中の常識の範囲内なのだから、何ら心配する必要もない。
はやり、太古の昔から人間は、魔界の力に抗うことなど出来ないのだろう、ここは正にその事実を具現化していると言えよう。
友達同士で寛いでいる美女二人組の席に、玲奈が届けているメニューなど、それを象徴するような代物である。
「コーヒーとバイブのセット、お待たせいたしましたぁ♪」
そう言って、玲奈はコーヒーの隣に何の憚りもなく、禍々しい男根を象った大型のバイブを添えた。
程なくして、コーヒーを飲みながら股間を開き、その中心にバイブを突き入れ始めた彼女達の口から、
「あぁぁん…はぁう…あぁ…これ、きもちいぃ…」
「あぁ…ホントだね…ぁうっ、…すごい寛ぐぅ…」
などと言う、何とも艶かしい満足に満ちた会話が交わされ始めた。
その二人の下に聡史は歩み寄り、
「お客様、お寛ぎのところ恐れ入りますが、当店のご感想はいかがですか?」
「ええ、とっても居心地がいいお店です…あっ、はぁぁ…」
「それはそれは、誠にありがとうございます。もしよろしければ、ご来店の記念に、ご一緒にお写真を撮らせて頂いても構いませんか?」
「あぁぁう…は、はい…私たちでよろしければ…喜んで…」
「う、うぅぅ…マ、マスターと並んで撮ってもらえるなんて光栄です…あぁ…」
「ありがとうございます。おーい、玲奈、ちょっと写真撮ってくれるかな。あ、お客様達はそのままお寛ぎの格好のままで結構です。そういう寛いで頂いている姿が、またここの評判にもなりますので」
と言うことで、全裸でバイブを股間に差し込んだままの美女二人と聡史の、にこやかな記念写真が撮影されてしまい、それが後にエコノミーフロアの掲示コーナーに、貼り出されることになる。
「マスターさん、ごちそうさまでした♪」
先ほどの聡史の濃厚ミルクコーヒーをきれいに飲み干した、営業途中と思わしき女性客が帰り際に声をかけてくれた。
「ありがとうございます。また是非、ご来店くださいね」
「はい♪ちょくちょく寄らせてもらいます」
「そうそう、お楽しみのショーツ交換しましょうか。では、私が一枚取りますね」
そう言って、聡史は今このフロアにいる8名ほどの女性客のパンティが詰め込まれている、中が見えないようになっている黒い箱に手を入れた。
「はい、ではこちらが当たりました」
聡史が取り出したのは、彼女が穿いてきた黒のパンティではなく、鮮やかなピンク色のパンティであった。
「あ、キレイな色♪何だか気分が変っていいですね!」
まるで当りくじを引き当てたかのような喜び様で、聡史の目の前でそのパンティに足を通し始めた。
誰の物かも分からず、股間部分にはどんな汚れが付いているのかも気にせずに、さっさと自分の股間部分に他人の汚れを押し付けてしまった。
これからのお仕事も、他人の汚れとともに張り切ってこなしていくのだろう。
全ての着替えを終えた彼女は、意気揚揚に店を出て行った。
彼女を見送って再び店内を見渡した聡史は、一番奥の席にいつの間にか座っている闇商人シルクの姿に気付いた。
「今来たんですか?いやーお陰で楽しませてもらってますよ」
「そのようですね。私も投資のし甲斐があったというもので…。お陰さまでこの店から取れる淫欲カプセルは、魔界でも大好評でしてね」
「それはそれは、で…今日は何の用で?」
「はいはい、実は投資者として、新たな提案をお願いしに来ました」
「新たな提案?」
「ええ、黒水晶の暗示力を更に強くしたものに交換していきますので、是非とも一階部分を“カップル専用”にしていただきたいのですよ。聡史さんはこの二階フロアの客で十分楽しめているようなので、一階でもっと強力な淫欲を収穫できるようにしたいのです。もちろん、そのカップルの女性から気に入ったのをこのフロアにお誘いすればいい訳で…」
「ほー、それは別に構わないけど…ははぁ、なるほど、カップルで“やりまくり”ってことでしょ?」
「さすがにスルドイ。その通りですよ」
「でも、それなら今の暗示力でも可能なんじゃないの?」
「確かに…“この店内だけ”という暗示ならこのままでいいでしょう。しかし今回私が提案しているのは、“ここで暗示にかけられた効果が未来永劫的に全世界どこへ行っても、“人間界の常識”として受け入れられる”というものでしてね。例えば、そうすれば今志穂さんに埋め込んでいるアナルプラグも、旦那さんに何の憚りもなく受け入れられるのですよ」
「うわー、それはすごい。是非やりましょう!」
「かしこまりました。では私はこれで…帰り際に水晶を交換しますのでね。後はよろしくお願いしますよ」
言うなり、シルクの姿は壁に溶け込むように消えていった。
数日後…。
店内の雰囲気は一変していた。
比較的ノーマルに近かった一階フロアは、まるでハプニングバーのごとき野獣的性欲を剥き出しにしたカップルで全席埋め尽くされ、コーヒーのほろ苦い香りとともに、そこ彼処から艶っぽい喘ぎ声や嬌声が響き渡っている。
カウンターに目を向けると、カウンター内で忙しなくオーダーに追われている志穂の目の前のカウンター席には、なんと彼女の夫が座っていた。
志穂自身が勧めたらしく、ここ数日、仕事の合間を縫っては足を運ぶようになっていた。
自分の愛妻が、ほぼ全裸に近い格好であるだけでなく、色っぽい豊満な臀部の亀裂の中心部から凶悪な極太のアナルプラグをはみ立たせているような変態的な姿にも、まるでテキパキと働く姿に惚れ込んでいるような優しい眼差しを向けている。
「あなた、今日もいつものでいいの?」
「ああ、“志穂スペシャルアイスコーヒー”を頼むよ」
「はーい♪」
“志穂スペシャルアイスコーヒー”…それの準備に取り掛かった志穂は、まずおもむろに自分のアナルに深く埋め込まれた極太プラグを苦も無く抜き取った。
もう数週間、毎日寝る時も埋め込まれているプラグだけに、抜き取られたアナルは、もうその口を閉める力も失ったように、ぽっかりと暗い洞窟の入口を覗かせたままになっていた。
そこへ、プラグ直径とほぼ同サイズの特注シェーカーの下半分だけを口の方から押し込む。そのシェーカーの中には、事前に用意されたアイスコーヒーが入っている。
そのまま志穂はその場に寝転がり、なんと下半身を天井に向けるように両腕で下半身を押し上げ、「フンッ」という小さいかけ声とともに、一気にそのシェーカー内のコーヒーを、自身の体内に導き入れてしまった。
そしてシェーカーを押し込んだまま、再び立ち上がり、片手でシェーカーが落下しないように押さえたまま、もう一度「フンッ」というかけ声とともに、体内からコーヒーをシェーカー内に戻したのだ。
そして、それを氷の入ったグラスに注ぎ、
「はい、あなた、お待ちどうさま」
そう言って、最愛の夫の前に差し出した。
このスペシャルアイスコーヒーの製造技術は、ここ最近、彼女が身に付けた得意技である。
それから程なくして、カランカランとドアベルを鳴らしながら、
「ただいまー」
という声とともに、マネージャーの綾子が全裸に赤い蝶ネクタイと黒いハイヒールのみという、露出狂同然の格好で、外出から戻ってきた。
「あ、綾子さん、商店会の会合、お疲れ様でした」
「ふぅ…志穂さんもお疲れ様。…まったくもう…、あのオジサマ達ときたら、融通の利かない偏屈ばかりなんだから」
「フフフ、この商店会の集まりは、もういいお歳の頑固な男性ばかりですものね。その中で紅一点の綾子さんはよくやってると思いますよ」
「ありがと…。あのオジサマ達を前に、今度のイベントのプレゼンをしたら疲れちゃった。ちょっと奥でお茶だけ飲ませてね」
「どうぞー」
そう言って奥の部屋に消えた行った綾子は、その会話の通り、定期の商店会の集いに参加し、大勢の年配男性の前で、その見事な肢体を包み隠すことなく披露したままで、近々予定しているイベントのプレゼンテーションをしてきたばかりなのだ。
毎回の商店会の会合は、記録保存という名目で、ビデオ撮影が行われており、後ほどそれが加盟店各店に届けられる仕組みになっていて、その変態的な会議の様子を鑑賞する事が、聡史の楽しみの一つになっていた。
二階VIPフロアでは、相変わらず聡史と玲奈による、異常なサービス世界が繰り広げられており、このお店は、今後益々異常な繁栄を続けていくことになるであろう。
魔界商人のシルクの微笑みとともに…。
(妄想商会~黒水晶~<完>)
「いらっしゃいませー♪」
玲奈のいつもと変らぬ明るいウェルカムコールとともに、2階メンバーフロアのエレベーターの扉が開き、20歳代と見える、紺のタイトスカートがよく似合うスーツ姿の女性が入ってきた。営業の間の空き時間で休憩がてらに立ち寄ったと見えるその女性客は、メンバーになってから初めてこのフロアーに訪れたらしく、あたりをキョロキョロしている。
「お客様、このフロアのご利用方法はご存知ですか?」
「いえ、今日が初めてです」
「そうでしたかー♪では、簡単にご案内させて頂きますね♪」
玲奈は明るく元気に応対しながら、驚くべきことを口にし始めた。
「まず、このフロアにお越し頂きましたら、お召しになっているものを全て脱いで頂いて、私共が毎回お渡しするこのカゴの中に入れて、そちらの棚に置いてくださいませ♪」
「あの、靴もですか?」
「ええ、そうです♪ご覧の通り、このフロアはメンバーのお客様に最高の寛ぎを感じて頂くことをテーマにさせていただいていますので♪」
「そうですね、皆さん気持ちよさそう…」
「はい♪皆様に大変喜んでいただいておりますー♪それと、脱いだショーツだけこちらのブラックボックスの中にお入れください。これは大変ご好評頂いている、お帰りの時の“お楽しみボックス”で、お帰りの際にはこの中身の見えない箱の中から私共が一枚だけ取り出しますので、それを穿いてお帰りいただきます♪“お洒落なショーツ交換”です♪素敵な企画でしょう♪あ、もし生理中の時には、衛生上ショーツのみ穿いたままでのご利用となり、この交換企画にはご参加頂けませんので、ご了承くださいませ」
「それは仕方ないですね、こんな素敵なフロアを汚しては申し訳ないですから」
「ご理解ありがとうございますー♪ではお客様、本日はこちらのカゴをご使用ください♪脱衣がお済みになりましたら、お席にご案内いたします♪」
何と言うやりとりか…。
ただ喫茶店にお茶しに来ただけなのに、店員から『全裸になれ』と言われ、その驚くべき要求に対して何の疑いも持たずに『はい』と受け入れる客。それも、帰る時にはこのフロアーを利用している客の、誰の物かも分からぬパンティを穿いて帰らなければならないのだ。
使用中のパンティを交換して穿くなど、どんなに仲の良い間柄でも憚られることだろうが、これも“お洒落な女性のための素敵な企画”として、嬉々として受け入れる客…。
見渡せば、このフロアーには既に6人ほどの女性客がおり、その誰もがやはり全裸姿で、それぞれが案内された席で、満足そうに寛いでいる。
彼女たちは、この選ばれた者だけが利用できる空間に、各々の脳内で描き出せる限りのステイタス性と憧れを感じているのだ。
先ほどの客も言われた通りの全裸状態になり、どこを隠すでもなく、堂々と玲奈に案内された席へ腰を下ろした。
聡史は自らがチョイスした、この美女の楽園のような光景を、2階にも設置してあるカウンター内から、股間の一物をはちきれんばかりに膨張させながら見入っている。
玲奈が先ほど案内したばかりの客のもとに行き、
「お客様、お決まりですか?」
「えっとぉ…色々あって迷いますね、オススメとかありますか?」
「そうですねー、失礼ですが“フェラチオ”のご経験はありますか?」
「え、あ、はい。ありますよ」
「でしたら、回数限定なんですが、“マスターのチ○ポからお口で生絞りミルク入りコーヒー”は人気ですよー♪」
「へー、まだあるんですか?」
「今日はまだ大丈夫だと思いますよ♪」
「では、それをお願いします。それと…この“玲奈のホットバナナ”も一緒で。これは玲奈さんが作るのですか?」
「はい♪…っていうか、作るというよりは、愛情込めて温めさせていただきますぅ♪」
注文を取り終えた玲奈が聡史のもとに歩み寄り、
「マスター、限定ミルクコーヒーのご注文いただきましたぁ♪3番テーブルのお客様ですー」
「お、そっかぁ、オッケー。じゃあ、コーヒーの準備お願いね」
「はーい♪」
聡史を見送った玲奈は、早速コーヒーを炒れ始めながら、取り出した一本のバナナの皮を剥き、
「はぁぅ…」
なんとそれを自分のオ○ンコにすっぽりと挿入してしまった。“ホットバナナ”を作成中なのである。
聡史は限定ミルクコーヒーの注文を受けた客のもとに赴き、
「お客様、限定ミルクコーヒーのご注文ありがとうございます。では早速お口で搾り出してください」
そう言って、彼女の目の前でズボンのジッパーを下ろし、既に半勃起している一物を取り出した。
「あ、はーい。では…(ハムッ…レロレロ…チュバチュバッ)」
「おぉ…お客様、お上手ですねー、これならすぐに絞れそうですねー、おぉぉ…玲奈ぁ、早くコーヒー頼むー」
その女性客がヨダレを垂れ流し、おいしそうにしゃぶり始めて程なく、
「マスター、コーヒーここに置きますね♪」
玲奈がコーヒーを運んできた。
「お、おぉ…サ、サンキュー、もう、出そうだ…お客様、お待たせしました…じゃあ、たっぷりのミルクをコーヒーに注ぎますね」
言うなり、優しく彼女の口からチ○ポを抜き出し、用意されたコーヒーめがけて“ドピュッ!ドピュッ!”と、勢いよく濃白の飛沫を浴びせかけた。
コーヒーカップの中に収まりきらなかった飛沫は、遠慮なくカップの縁を汚し、カップの中に命中したものは質量のあるドロドロの液体よろしく、コーヒーの中に沈殿し始め、コーヒーの熱で温められたタンパク成分が白い膜のように漂っていた。
「よくかき混ぜてお飲みくださいね」
「わぁ、おいしそうですねー」
横にいた玲奈も、
「はーい、こちらもお待たせしましたぁ♪“玲奈のホットバナナ”ですぅ♪よーく温まってますよー」
玲奈はおもむろに剥き出しになっている股間部分に手をやり、自ら数本の指をオ○ンコに挿入させ、少しこねくり回しながら、ヌルッとした液状の膜に覆われ、全体に光沢を帯びたバナナを取り出して、皿の上に盛り付けた。
「こっちもおいしそうですね!」
その女性客は、こうしたパフォーマンスを“鮮やかなシェフの手並み”的感覚で認識しているのか、目を輝かせてその一部始終に見入っていた。
こんな調子で、続々と破廉恥極まりないオーダーが飛び交い、一階のエコノミーフロアに比べると、このメンバーフロアは、正に異常なインモラル世界と化していた。
しかし、客の女性達にとっては、ここで寛ぐことが彼女達にとっての“最高の癒し空間”になっている。もし万が一、今ここに警察の立ち入り検査が入ったとしても、この結界内で行われている、また起こっていることは、全て世の中の常識の範囲内なのだから、何ら心配する必要もない。
はやり、太古の昔から人間は、魔界の力に抗うことなど出来ないのだろう、ここは正にその事実を具現化していると言えよう。
友達同士で寛いでいる美女二人組の席に、玲奈が届けているメニューなど、それを象徴するような代物である。
「コーヒーとバイブのセット、お待たせいたしましたぁ♪」
そう言って、玲奈はコーヒーの隣に何の憚りもなく、禍々しい男根を象った大型のバイブを添えた。
程なくして、コーヒーを飲みながら股間を開き、その中心にバイブを突き入れ始めた彼女達の口から、
「あぁぁん…はぁう…あぁ…これ、きもちいぃ…」
「あぁ…ホントだね…ぁうっ、…すごい寛ぐぅ…」
などと言う、何とも艶かしい満足に満ちた会話が交わされ始めた。
その二人の下に聡史は歩み寄り、
「お客様、お寛ぎのところ恐れ入りますが、当店のご感想はいかがですか?」
「ええ、とっても居心地がいいお店です…あっ、はぁぁ…」
「それはそれは、誠にありがとうございます。もしよろしければ、ご来店の記念に、ご一緒にお写真を撮らせて頂いても構いませんか?」
「あぁぁう…は、はい…私たちでよろしければ…喜んで…」
「う、うぅぅ…マ、マスターと並んで撮ってもらえるなんて光栄です…あぁ…」
「ありがとうございます。おーい、玲奈、ちょっと写真撮ってくれるかな。あ、お客様達はそのままお寛ぎの格好のままで結構です。そういう寛いで頂いている姿が、またここの評判にもなりますので」
と言うことで、全裸でバイブを股間に差し込んだままの美女二人と聡史の、にこやかな記念写真が撮影されてしまい、それが後にエコノミーフロアの掲示コーナーに、貼り出されることになる。
「マスターさん、ごちそうさまでした♪」
先ほどの聡史の濃厚ミルクコーヒーをきれいに飲み干した、営業途中と思わしき女性客が帰り際に声をかけてくれた。
「ありがとうございます。また是非、ご来店くださいね」
「はい♪ちょくちょく寄らせてもらいます」
「そうそう、お楽しみのショーツ交換しましょうか。では、私が一枚取りますね」
そう言って、聡史は今このフロアにいる8名ほどの女性客のパンティが詰め込まれている、中が見えないようになっている黒い箱に手を入れた。
「はい、ではこちらが当たりました」
聡史が取り出したのは、彼女が穿いてきた黒のパンティではなく、鮮やかなピンク色のパンティであった。
「あ、キレイな色♪何だか気分が変っていいですね!」
まるで当りくじを引き当てたかのような喜び様で、聡史の目の前でそのパンティに足を通し始めた。
誰の物かも分からず、股間部分にはどんな汚れが付いているのかも気にせずに、さっさと自分の股間部分に他人の汚れを押し付けてしまった。
これからのお仕事も、他人の汚れとともに張り切ってこなしていくのだろう。
全ての着替えを終えた彼女は、意気揚揚に店を出て行った。
彼女を見送って再び店内を見渡した聡史は、一番奥の席にいつの間にか座っている闇商人シルクの姿に気付いた。
「今来たんですか?いやーお陰で楽しませてもらってますよ」
「そのようですね。私も投資のし甲斐があったというもので…。お陰さまでこの店から取れる淫欲カプセルは、魔界でも大好評でしてね」
「それはそれは、で…今日は何の用で?」
「はいはい、実は投資者として、新たな提案をお願いしに来ました」
「新たな提案?」
「ええ、黒水晶の暗示力を更に強くしたものに交換していきますので、是非とも一階部分を“カップル専用”にしていただきたいのですよ。聡史さんはこの二階フロアの客で十分楽しめているようなので、一階でもっと強力な淫欲を収穫できるようにしたいのです。もちろん、そのカップルの女性から気に入ったのをこのフロアにお誘いすればいい訳で…」
「ほー、それは別に構わないけど…ははぁ、なるほど、カップルで“やりまくり”ってことでしょ?」
「さすがにスルドイ。その通りですよ」
「でも、それなら今の暗示力でも可能なんじゃないの?」
「確かに…“この店内だけ”という暗示ならこのままでいいでしょう。しかし今回私が提案しているのは、“ここで暗示にかけられた効果が未来永劫的に全世界どこへ行っても、“人間界の常識”として受け入れられる”というものでしてね。例えば、そうすれば今志穂さんに埋め込んでいるアナルプラグも、旦那さんに何の憚りもなく受け入れられるのですよ」
「うわー、それはすごい。是非やりましょう!」
「かしこまりました。では私はこれで…帰り際に水晶を交換しますのでね。後はよろしくお願いしますよ」
言うなり、シルクの姿は壁に溶け込むように消えていった。
数日後…。
店内の雰囲気は一変していた。
比較的ノーマルに近かった一階フロアは、まるでハプニングバーのごとき野獣的性欲を剥き出しにしたカップルで全席埋め尽くされ、コーヒーのほろ苦い香りとともに、そこ彼処から艶っぽい喘ぎ声や嬌声が響き渡っている。
カウンターに目を向けると、カウンター内で忙しなくオーダーに追われている志穂の目の前のカウンター席には、なんと彼女の夫が座っていた。
志穂自身が勧めたらしく、ここ数日、仕事の合間を縫っては足を運ぶようになっていた。
自分の愛妻が、ほぼ全裸に近い格好であるだけでなく、色っぽい豊満な臀部の亀裂の中心部から凶悪な極太のアナルプラグをはみ立たせているような変態的な姿にも、まるでテキパキと働く姿に惚れ込んでいるような優しい眼差しを向けている。
「あなた、今日もいつものでいいの?」
「ああ、“志穂スペシャルアイスコーヒー”を頼むよ」
「はーい♪」
“志穂スペシャルアイスコーヒー”…それの準備に取り掛かった志穂は、まずおもむろに自分のアナルに深く埋め込まれた極太プラグを苦も無く抜き取った。
もう数週間、毎日寝る時も埋め込まれているプラグだけに、抜き取られたアナルは、もうその口を閉める力も失ったように、ぽっかりと暗い洞窟の入口を覗かせたままになっていた。
そこへ、プラグ直径とほぼ同サイズの特注シェーカーの下半分だけを口の方から押し込む。そのシェーカーの中には、事前に用意されたアイスコーヒーが入っている。
そのまま志穂はその場に寝転がり、なんと下半身を天井に向けるように両腕で下半身を押し上げ、「フンッ」という小さいかけ声とともに、一気にそのシェーカー内のコーヒーを、自身の体内に導き入れてしまった。
そしてシェーカーを押し込んだまま、再び立ち上がり、片手でシェーカーが落下しないように押さえたまま、もう一度「フンッ」というかけ声とともに、体内からコーヒーをシェーカー内に戻したのだ。
そして、それを氷の入ったグラスに注ぎ、
「はい、あなた、お待ちどうさま」
そう言って、最愛の夫の前に差し出した。
このスペシャルアイスコーヒーの製造技術は、ここ最近、彼女が身に付けた得意技である。
それから程なくして、カランカランとドアベルを鳴らしながら、
「ただいまー」
という声とともに、マネージャーの綾子が全裸に赤い蝶ネクタイと黒いハイヒールのみという、露出狂同然の格好で、外出から戻ってきた。
「あ、綾子さん、商店会の会合、お疲れ様でした」
「ふぅ…志穂さんもお疲れ様。…まったくもう…、あのオジサマ達ときたら、融通の利かない偏屈ばかりなんだから」
「フフフ、この商店会の集まりは、もういいお歳の頑固な男性ばかりですものね。その中で紅一点の綾子さんはよくやってると思いますよ」
「ありがと…。あのオジサマ達を前に、今度のイベントのプレゼンをしたら疲れちゃった。ちょっと奥でお茶だけ飲ませてね」
「どうぞー」
そう言って奥の部屋に消えた行った綾子は、その会話の通り、定期の商店会の集いに参加し、大勢の年配男性の前で、その見事な肢体を包み隠すことなく披露したままで、近々予定しているイベントのプレゼンテーションをしてきたばかりなのだ。
毎回の商店会の会合は、記録保存という名目で、ビデオ撮影が行われており、後ほどそれが加盟店各店に届けられる仕組みになっていて、その変態的な会議の様子を鑑賞する事が、聡史の楽しみの一つになっていた。
二階VIPフロアでは、相変わらず聡史と玲奈による、異常なサービス世界が繰り広げられており、このお店は、今後益々異常な繁栄を続けていくことになるであろう。
魔界商人のシルクの微笑みとともに…。
(妄想商会~黒水晶~<完>)
妄想商会(15)~黒水晶〈第6話〉~*特殊アイテム
闇商人シルクと聡史の淫らな邪心によって改築された喫茶店の新装オープンが、いよいよ明日に迫った。
上質な従業員もとりあえず揃い、一安心である。
その組織構成は以下の通りで、
マネージャー:加賀谷 綾子 25歳
若くして某有名大型エステチェーンの本店店長職を務めていた、かなりの美貌と知性を兼ね揃える“デキるキャリアウーマン”だったのを、ヘッドハンティングした。
使用制服:全裸に赤い蝶ネクタイのみ
チーフ:杉崎 玲奈 23歳
改装前の前店舗時代から継続採用。弁護士の父と、女流画家の母を持つお嬢様。自身もデザイナーを目指し、目下勉強中。
使用制服:白の薄手競泳水着(股間露呈用の切り込み&乳房露呈用のゴム穴付き)
赤の蝶ネクタイ
一般店員:澤野 志穂 30歳
音大卒業後、音楽講師として働いていたが、一流商社勤務の男性との結婚を期に、セレブ系専業主婦に転身。都内一等地に建つ高級マンションで、夫婦二人の優雅な生活を送っている。
使用制服:白のスケスケパンティ(クロッチ無し)
白の膝上までのタイツ
赤の蝶ネクタイ
アナルプラグ(太さは暫時変更)
そして、マスターの板垣聡史の4人である。
店内の装飾やその他の内装工事も終了し、いよいよお客様を待つだけとなった。
今回の改装で最大の改良点は、これまでワンフロアーのみの店舗だったものを、2階部分も買い取り、2階建て店舗にした点である。
もちろんこれには、“ただ広くしただけ…”ということではなく、ちゃんと理由がある。
2階部分は『メンバーフロア』ということで、メンバーとして登録されたお客様のみが利用できるのだ。
そのため、エレベーターにはメンバーカードを差し込み式の認証システムまで付いている。
メンバーフロアーの内装は、『空間デザイナー 板垣聡史』としてのプロフェッショナルな感性が最大限に発揮された造りになっており、高級家具やオリジナルデザインの家具をふんだんに取り入れ、今時のセレブ&ハイソ嗜好の女性陣が憧れを持つにふさわしいものとなっていた。
もちろん、メンバー資格は女性にだけ付与される。
その選考は、お客様側からの申込み制ではなく、“マスターからの推薦状”を受け取ることが出来たお客様のみが、メンバーになるか否かを判断できるのである。
あまりにも公平さに欠ける選考方法で、普通のお店ならばクレームの嵐になるか、客離れを引き起こしかねないであろうが、ここは『黒水晶の結界』すなわち聡史の決めたルールが絶対であり、それが当たり前のこととして、常識内で受け止められてしまうのだ。
「おーい、みんな、よく聞いておくように。明日からいよいよオープンです。それで、とりあえずはこの4人で回していくわけだけど、見ての通りこのお店は2階建てになってるから、各フロアーの担当を決めるね。
一階のエコノミーフロアは、マネージャーの綾子と、それから志穂に担当してもらうね。二階のメンバーフロアーは、俺と玲奈ね。但し、まだメンバーはいないので、明日は全員でこの一階を盛り上げていこう。いいね?」
「はーい!」
3人のスタッフが声を合わせて、やる気に満ちた元気な声を出していた。
3人とも自分の腹部に白のガムテープを貼り、それぞれ自分の字で『今日はキレイなマ○コです』と表示している。志穂のみ、それとは別に『私のウ○コはもの凄くクサイです』という“衛生管理上”の表示も貼られていた。
玲奈は可愛い丸文字風で、綾子と志穂はそれぞれ“デキる”女性らしく流暢な書体で、自分の痴態を曝け出しているのだが、本人達はそれを当然の“衛生管理”としか認識できないのだから滑稽である。
「じゃあ、玲奈と綾子は2階の最終清掃を頼むね。志穂は新しく届いた食器類を箱から出して洗うところからスタートしよう」
各担当に分かれての作業が開始され、一階には志穂と聡史のみが残る形となった。
今志穂は、箱から出したプレートやカップをシンクに入れて、洗い始めたところである。
「志穂、まだウ○コ表示を貼ってるけど、便秘はそのままかな?」
「…はい、すみません…少しずつは出やすくなってるようなんですが…」
志穂のアナルには、この数日間の間に既に直径3cm弱のプラグが常時装着できるまでになっていたが、それでも出にくいとは、中々頑固な腸である。
「仕方ないなー、じゃあいつもの洗浄しておくか」
そういって、聡史はもう一つのシンクの蛇口にホースを取り付け、そのもう一端を志穂のアナルプラグに直接繋いだ。
実は彼女に装着しているアナルプラグは、特注品で中心に管が通してあり、プラグの底にはネジ蓋付きのノズルが飛び出ている。そのノズルにホースを繋げば、そのまま一気に直腸内に水道水を注入できる仕組みになっていた。
「志穂、ちょっとキツイけど、いつもの…いくからね」
「あ、はい…お願い…します」
志穂はこの洗浄を既に経験済みである。なのでその辛さも承知しているし、その恥ずかしさも承知しているが、“衛生管理上”致し方ない、当然だ…という雰囲気で、受ける体勢をとっていた。
聡史は緩く蛇口を解放し、志穂の直腸内に水道水を注入し始めた。
「はぅぅっ!……」
水道水の冷たさと迫りくる腸内の圧迫感に、苦悶の表情を浮かべる志穂。
彼女のアナルが咥えているプラグは、先端部分が傘のように太くなっているので、自力のイキミではまず抜くことが出来ない。
「志穂、今日は開店前だから頑張ってもらわないとね。3人の中で一番年長なのに、なんで一番下のタイトルかは、自分が一番よく理解しているだろう。そう、身体の中が一番汚いからだよ。だから早くいつもキレイにいれるようにしようね」
「あっ、あぅぅ…は、はいぃ…が、がんばり…ます…はぁぁぅぅっ…」
志穂の表情が益々険しくなり、洗物などしていられる状態ではなくなっていた。シンクに手を付き、両膝をギュッと閉じて、必死にお腹の膨張感と迫りくる排泄感に堪えているが、聡史の方は一向に注水を止める気配を見せない。
「今日はいつも以上に入れるよ。お腹の中に溜まっているものが、全て流れ出るようにね」
「はぁぁぁぁっ…も、もう…ダ、ダメ…です…」
今や息も絶え絶えの様子であるが、聡史の方は徐々に膨らみを増しタプタプになりつつある下腹部に手を当てながら、
「もう少し奥の方までお水を流し込まないとね。いつもはこれくらいだけど、今日はもう少し頑張らなきゃ。志穂が働きたがっていたお店が、とうとう明日オープンするんだから、その前に…どうしておかなきゃならないんだっけ?」
「…うぅぅあぁぁっ!はっ、はいぃぃっ!!…からだ…身体のな、中をーっ!…き、きれ…い…にぃぃ…して…しておき…ますぅぅぅっ!!あぁぁぁぁぁっ!も、もうっ!!」
いよいよ腸風船も限界が近づいているようで、先ほどまでの通常の下腹部からは想像もつかないほど床に向かって風船が垂れ下がっている。
「よーし、じゃあこの辺でいいかな」
ようやく聡史は蛇口の栓を閉めた。
異常に下腹部を膨らませた志穂は、シンクにもたれかかっていないと、もう自力では動けない状態のようで、
「じゃあ、今準備してくるから、そのまま待っててね」
苦しむ志穂をそのままにして、聡史は何やら準備をし始めた。
奥の倉庫から、大きめの寸胴鍋を取り出してきて、店の玄関先のテラス席に置き、その鍋を挟むように両側にテラス席のイスをセットした。
そして、その横に『只今、スタッフ体内下水管清掃中。多少の異臭につき、通行の方々にはご迷惑をおかけいたします』と大きな文字で書かれた、立て看板を設置した。
「さてと、いつもの準備ができたよ。さすがにその“汚いモノ”を店内で吐き出してもらうわけにはいかないからね。さぁ、行くよ」
なんと、志穂の排泄を店先の往来の前で行わせようというのである。
改装後新たに設けたテラス席まで黒水晶の結界を張っているので、通行人からは『あぁ、下水管の清掃なんだ…じゃあ、臭くても仕方ない』という認識しか持たれない。
もう聡史に身を預けないと歩けない志穂は、ヨチヨチ歩きのまま聡史に連れられて店先に出された。
既にホースを取り付ける際に、白のスケスケパンティは脱がされているので、首に巻いた赤い蝶ネクタイのみの全裸姿で、聡史に導かれるままイスの上に足を乗せ、真下に寸胴鍋を置いた形でしゃがみ込まされた。
「じゃあ、抜くよ。しっかりとお腹に圧を加えて、高圧で腸内を洗浄するようにね。分かったかい?」
「…は、はぃぃ…」
もう声を出すのも辛い…といった様子である。
次の瞬間、聡史が志穂のアナルプラグを一気に引き抜いた。
「!!!ひゃうっ!!」
ブシャーッ!!!
一瞬の叫び声の後、異様な破裂音と共に、滝のような爆流が寸胴鍋の底に叩きつけられていった。
最初透明だった爆流は、その水流の勢いの低下と共に濁り始め、徐々に黄土色から茶褐色の液体へと変化していき、ブリッ!ブシュッ!という鈍い破裂音と共に、時には太く、時には長い茶色の固形物を同時に噴出させ始めた。
こうなると、辺り一面に異様な異臭が立ち込め始める。
平日の午前中、駅から少し離れたこの通りも、駅に向かう人やこの店の先の大型スーパーに向かう人たちなどで、それなりの往来はある。
道行く人たちはその立て看板を見て、下水管の清掃と知りつつも、志穂を見やりながら中にはハンカチを鼻に当てて、距離を置いて通り過ぎていく人もいた。
こんな惨め且つ破廉恥な姿を晒している志穂は、この結界から一歩でも外に出れば、人も羨むセレブ奥様なのだ。そんなセレブ奥様が、今や大衆の面前で最も恥ずべきであろう、便秘で溜め込んだ排泄物の排泄ショーをさせられている現実…。
それも、本人も見ている人たちも、それが“異常な行為”とは認識していない世界。
これが闇商人シルクと、板垣聡史の作り上げた驚異のインモラル世界なのだ。
そして、いよいよ待ちに待ったオープン初日…。
綾子、玲奈、志穂の3名の極上女性スタッフも、朝から張り切って開店準備に取り掛かっていた。
「おはようございます!間もなくオープンですので、もう少しだけお待ちくださいませ!」
澄んだよく通る声で、開店を待つお客様に案内しているのは、綾子である。
綾子の制服は、白のパンプスに赤い蝶ネクタイのみ…という全裸状態なのだが、そんな破廉恥極まりない格好を、肩書きを重んじる綾子は『マネージャー専用制服』と認識して、むしろ誇らしげにテラス席のテーブルを拭いたり、ドアを磨いたりしていた。
噂の喫茶店の新装オープンを聞きつけて、開店前にも関わらず、既に20名ほどのお客様が開店時間を待っているが、その前で誇らしげに全裸を露呈している綾子…。
その度プルンプルンと揺れる、程よいボリュームの両乳房が、彼女の張り切り具合を現しているかのようでもあった。
「皆様、お待たせいたしました!さぁ、オープンいたします。どうぞお入りくださいませ!」
聡史のオープンコールの後、待ちに待ったお客様達が、どっと店内に流れ込む。
「いらっしゃいませー♪」
3人の美女達によるウェルカムコールが、店内に華やかに響き渡る。
いよいよ淫欲渦巻く変態喫茶店が、街中に誕生してしまったことを、聡史を除いてここにいる誰もが全く認識していないことが、聡史の欲望の火を益々盛んにしていく。
思えば、セコセコとトイレ盗撮などをしていた自分が、非常に小さく思えた。これからはどんな淫欲も、この結界内であれば全てまかり通るのであるのだから…。
「ケーキとコーヒーのセットですね♪かしこまりましたぁ♪」
23歳の張りのある乳房と、可愛らしい顔つきからは想像もつかないくらいな剛毛ジャングルのデルタ地帯を剥き出しにした玲奈の声が、心地よく響き渡る。
「玲奈さん、3番テーブルのお客様のコーヒーお願いします」
エロ清楚な純白スケスケパンティの中に、凶悪なくらい大きいサイズのアナルプラグを潜ませた志穂のテキパキとした仕事振りが、眩しく輝いている。
「マスター、外でお待ちのお客様用に、取り急ぎですが、メニューを作成しました。お渡ししてよろしいですか?」
「ああ、急ぎで作ったわりにはいい出来だねー。よろしく頼むよ」
さすがは元キレモノ本店店長だけに、全裸制服姿になっても卒のない心配りで、店内を切り盛りする綾子。
そんな3人の活躍振りと、お客様の喜ぶ顔を見ながら満足を感じている聡史であったが、彼にはこの店のマスターとして“やらなければならない”大事な仕事のために、入退場を繰り返す全てのお客様に目を配っていた。
「玲奈、2番テーブルのあの女性に、これをお渡ししてくれ」
「あ、はーい♪きっと喜びますよぉ♪」
玲奈に手渡したものは“メンバーへの推薦状”である。
聡史の独断と偏見で、彼の目に適った女性のみに贈られる推薦状であり、晴れてメンバーになれば、いよいよ“誰もが憧れる2階メンバーフロア”の利用が出来るようになるのだ。
「うわぁ!きゃー!嬉しい♪ホントですかぁ!?」
聡史の思惑通り、推薦状を受け取った女性客から歓喜の声が上がっている。
こんな独断と偏見に満ちた行為は、本来であれば“差別行為”として、社会的にも受け入れられることのない所業であるが、この店内はそんな一般社会的通念から隔絶された、言わば“治外法権”的な空間であり、聡史の価値観念が絶対の領域であり、そこに足を踏み入れた全ての者は、その歪んだ観念を自らの脳内で勝手に“憧れ”や“ステイタス”として偶像化してくれるので、ありがたいことこの上ないのである。
こうして聡史はマスターとしての最初の大仕事に熱心に取り組み、今日一日で50名程の女性に推薦状を配りまくり、その全ての女性から、自ら進んでの“承諾”の返事を取り付け、専用のメンバーカードを手渡した。
どの女性も聡史の好みに適った“いい獲物”揃いであった。
明日あたりから、彼女達が我先にと“特別待遇”を求めて、このお店に足を運ぶことになるだろう。
そして、大忙しの内にオープン初日が幕を閉じた…。
(黒水晶〈第7話〉につづく…)
上質な従業員もとりあえず揃い、一安心である。
その組織構成は以下の通りで、
マネージャー:加賀谷 綾子 25歳
若くして某有名大型エステチェーンの本店店長職を務めていた、かなりの美貌と知性を兼ね揃える“デキるキャリアウーマン”だったのを、ヘッドハンティングした。
使用制服:全裸に赤い蝶ネクタイのみ
チーフ:杉崎 玲奈 23歳
改装前の前店舗時代から継続採用。弁護士の父と、女流画家の母を持つお嬢様。自身もデザイナーを目指し、目下勉強中。
使用制服:白の薄手競泳水着(股間露呈用の切り込み&乳房露呈用のゴム穴付き)
赤の蝶ネクタイ
一般店員:澤野 志穂 30歳
音大卒業後、音楽講師として働いていたが、一流商社勤務の男性との結婚を期に、セレブ系専業主婦に転身。都内一等地に建つ高級マンションで、夫婦二人の優雅な生活を送っている。
使用制服:白のスケスケパンティ(クロッチ無し)
白の膝上までのタイツ
赤の蝶ネクタイ
アナルプラグ(太さは暫時変更)
そして、マスターの板垣聡史の4人である。
店内の装飾やその他の内装工事も終了し、いよいよお客様を待つだけとなった。
今回の改装で最大の改良点は、これまでワンフロアーのみの店舗だったものを、2階部分も買い取り、2階建て店舗にした点である。
もちろんこれには、“ただ広くしただけ…”ということではなく、ちゃんと理由がある。
2階部分は『メンバーフロア』ということで、メンバーとして登録されたお客様のみが利用できるのだ。
そのため、エレベーターにはメンバーカードを差し込み式の認証システムまで付いている。
メンバーフロアーの内装は、『空間デザイナー 板垣聡史』としてのプロフェッショナルな感性が最大限に発揮された造りになっており、高級家具やオリジナルデザインの家具をふんだんに取り入れ、今時のセレブ&ハイソ嗜好の女性陣が憧れを持つにふさわしいものとなっていた。
もちろん、メンバー資格は女性にだけ付与される。
その選考は、お客様側からの申込み制ではなく、“マスターからの推薦状”を受け取ることが出来たお客様のみが、メンバーになるか否かを判断できるのである。
あまりにも公平さに欠ける選考方法で、普通のお店ならばクレームの嵐になるか、客離れを引き起こしかねないであろうが、ここは『黒水晶の結界』すなわち聡史の決めたルールが絶対であり、それが当たり前のこととして、常識内で受け止められてしまうのだ。
「おーい、みんな、よく聞いておくように。明日からいよいよオープンです。それで、とりあえずはこの4人で回していくわけだけど、見ての通りこのお店は2階建てになってるから、各フロアーの担当を決めるね。
一階のエコノミーフロアは、マネージャーの綾子と、それから志穂に担当してもらうね。二階のメンバーフロアーは、俺と玲奈ね。但し、まだメンバーはいないので、明日は全員でこの一階を盛り上げていこう。いいね?」
「はーい!」
3人のスタッフが声を合わせて、やる気に満ちた元気な声を出していた。
3人とも自分の腹部に白のガムテープを貼り、それぞれ自分の字で『今日はキレイなマ○コです』と表示している。志穂のみ、それとは別に『私のウ○コはもの凄くクサイです』という“衛生管理上”の表示も貼られていた。
玲奈は可愛い丸文字風で、綾子と志穂はそれぞれ“デキる”女性らしく流暢な書体で、自分の痴態を曝け出しているのだが、本人達はそれを当然の“衛生管理”としか認識できないのだから滑稽である。
「じゃあ、玲奈と綾子は2階の最終清掃を頼むね。志穂は新しく届いた食器類を箱から出して洗うところからスタートしよう」
各担当に分かれての作業が開始され、一階には志穂と聡史のみが残る形となった。
今志穂は、箱から出したプレートやカップをシンクに入れて、洗い始めたところである。
「志穂、まだウ○コ表示を貼ってるけど、便秘はそのままかな?」
「…はい、すみません…少しずつは出やすくなってるようなんですが…」
志穂のアナルには、この数日間の間に既に直径3cm弱のプラグが常時装着できるまでになっていたが、それでも出にくいとは、中々頑固な腸である。
「仕方ないなー、じゃあいつもの洗浄しておくか」
そういって、聡史はもう一つのシンクの蛇口にホースを取り付け、そのもう一端を志穂のアナルプラグに直接繋いだ。
実は彼女に装着しているアナルプラグは、特注品で中心に管が通してあり、プラグの底にはネジ蓋付きのノズルが飛び出ている。そのノズルにホースを繋げば、そのまま一気に直腸内に水道水を注入できる仕組みになっていた。
「志穂、ちょっとキツイけど、いつもの…いくからね」
「あ、はい…お願い…します」
志穂はこの洗浄を既に経験済みである。なのでその辛さも承知しているし、その恥ずかしさも承知しているが、“衛生管理上”致し方ない、当然だ…という雰囲気で、受ける体勢をとっていた。
聡史は緩く蛇口を解放し、志穂の直腸内に水道水を注入し始めた。
「はぅぅっ!……」
水道水の冷たさと迫りくる腸内の圧迫感に、苦悶の表情を浮かべる志穂。
彼女のアナルが咥えているプラグは、先端部分が傘のように太くなっているので、自力のイキミではまず抜くことが出来ない。
「志穂、今日は開店前だから頑張ってもらわないとね。3人の中で一番年長なのに、なんで一番下のタイトルかは、自分が一番よく理解しているだろう。そう、身体の中が一番汚いからだよ。だから早くいつもキレイにいれるようにしようね」
「あっ、あぅぅ…は、はいぃ…が、がんばり…ます…はぁぁぅぅっ…」
志穂の表情が益々険しくなり、洗物などしていられる状態ではなくなっていた。シンクに手を付き、両膝をギュッと閉じて、必死にお腹の膨張感と迫りくる排泄感に堪えているが、聡史の方は一向に注水を止める気配を見せない。
「今日はいつも以上に入れるよ。お腹の中に溜まっているものが、全て流れ出るようにね」
「はぁぁぁぁっ…も、もう…ダ、ダメ…です…」
今や息も絶え絶えの様子であるが、聡史の方は徐々に膨らみを増しタプタプになりつつある下腹部に手を当てながら、
「もう少し奥の方までお水を流し込まないとね。いつもはこれくらいだけど、今日はもう少し頑張らなきゃ。志穂が働きたがっていたお店が、とうとう明日オープンするんだから、その前に…どうしておかなきゃならないんだっけ?」
「…うぅぅあぁぁっ!はっ、はいぃぃっ!!…からだ…身体のな、中をーっ!…き、きれ…い…にぃぃ…して…しておき…ますぅぅぅっ!!あぁぁぁぁぁっ!も、もうっ!!」
いよいよ腸風船も限界が近づいているようで、先ほどまでの通常の下腹部からは想像もつかないほど床に向かって風船が垂れ下がっている。
「よーし、じゃあこの辺でいいかな」
ようやく聡史は蛇口の栓を閉めた。
異常に下腹部を膨らませた志穂は、シンクにもたれかかっていないと、もう自力では動けない状態のようで、
「じゃあ、今準備してくるから、そのまま待っててね」
苦しむ志穂をそのままにして、聡史は何やら準備をし始めた。
奥の倉庫から、大きめの寸胴鍋を取り出してきて、店の玄関先のテラス席に置き、その鍋を挟むように両側にテラス席のイスをセットした。
そして、その横に『只今、スタッフ体内下水管清掃中。多少の異臭につき、通行の方々にはご迷惑をおかけいたします』と大きな文字で書かれた、立て看板を設置した。
「さてと、いつもの準備ができたよ。さすがにその“汚いモノ”を店内で吐き出してもらうわけにはいかないからね。さぁ、行くよ」
なんと、志穂の排泄を店先の往来の前で行わせようというのである。
改装後新たに設けたテラス席まで黒水晶の結界を張っているので、通行人からは『あぁ、下水管の清掃なんだ…じゃあ、臭くても仕方ない』という認識しか持たれない。
もう聡史に身を預けないと歩けない志穂は、ヨチヨチ歩きのまま聡史に連れられて店先に出された。
既にホースを取り付ける際に、白のスケスケパンティは脱がされているので、首に巻いた赤い蝶ネクタイのみの全裸姿で、聡史に導かれるままイスの上に足を乗せ、真下に寸胴鍋を置いた形でしゃがみ込まされた。
「じゃあ、抜くよ。しっかりとお腹に圧を加えて、高圧で腸内を洗浄するようにね。分かったかい?」
「…は、はぃぃ…」
もう声を出すのも辛い…といった様子である。
次の瞬間、聡史が志穂のアナルプラグを一気に引き抜いた。
「!!!ひゃうっ!!」
ブシャーッ!!!
一瞬の叫び声の後、異様な破裂音と共に、滝のような爆流が寸胴鍋の底に叩きつけられていった。
最初透明だった爆流は、その水流の勢いの低下と共に濁り始め、徐々に黄土色から茶褐色の液体へと変化していき、ブリッ!ブシュッ!という鈍い破裂音と共に、時には太く、時には長い茶色の固形物を同時に噴出させ始めた。
こうなると、辺り一面に異様な異臭が立ち込め始める。
平日の午前中、駅から少し離れたこの通りも、駅に向かう人やこの店の先の大型スーパーに向かう人たちなどで、それなりの往来はある。
道行く人たちはその立て看板を見て、下水管の清掃と知りつつも、志穂を見やりながら中にはハンカチを鼻に当てて、距離を置いて通り過ぎていく人もいた。
こんな惨め且つ破廉恥な姿を晒している志穂は、この結界から一歩でも外に出れば、人も羨むセレブ奥様なのだ。そんなセレブ奥様が、今や大衆の面前で最も恥ずべきであろう、便秘で溜め込んだ排泄物の排泄ショーをさせられている現実…。
それも、本人も見ている人たちも、それが“異常な行為”とは認識していない世界。
これが闇商人シルクと、板垣聡史の作り上げた驚異のインモラル世界なのだ。
そして、いよいよ待ちに待ったオープン初日…。
綾子、玲奈、志穂の3名の極上女性スタッフも、朝から張り切って開店準備に取り掛かっていた。
「おはようございます!間もなくオープンですので、もう少しだけお待ちくださいませ!」
澄んだよく通る声で、開店を待つお客様に案内しているのは、綾子である。
綾子の制服は、白のパンプスに赤い蝶ネクタイのみ…という全裸状態なのだが、そんな破廉恥極まりない格好を、肩書きを重んじる綾子は『マネージャー専用制服』と認識して、むしろ誇らしげにテラス席のテーブルを拭いたり、ドアを磨いたりしていた。
噂の喫茶店の新装オープンを聞きつけて、開店前にも関わらず、既に20名ほどのお客様が開店時間を待っているが、その前で誇らしげに全裸を露呈している綾子…。
その度プルンプルンと揺れる、程よいボリュームの両乳房が、彼女の張り切り具合を現しているかのようでもあった。
「皆様、お待たせいたしました!さぁ、オープンいたします。どうぞお入りくださいませ!」
聡史のオープンコールの後、待ちに待ったお客様達が、どっと店内に流れ込む。
「いらっしゃいませー♪」
3人の美女達によるウェルカムコールが、店内に華やかに響き渡る。
いよいよ淫欲渦巻く変態喫茶店が、街中に誕生してしまったことを、聡史を除いてここにいる誰もが全く認識していないことが、聡史の欲望の火を益々盛んにしていく。
思えば、セコセコとトイレ盗撮などをしていた自分が、非常に小さく思えた。これからはどんな淫欲も、この結界内であれば全てまかり通るのであるのだから…。
「ケーキとコーヒーのセットですね♪かしこまりましたぁ♪」
23歳の張りのある乳房と、可愛らしい顔つきからは想像もつかないくらいな剛毛ジャングルのデルタ地帯を剥き出しにした玲奈の声が、心地よく響き渡る。
「玲奈さん、3番テーブルのお客様のコーヒーお願いします」
エロ清楚な純白スケスケパンティの中に、凶悪なくらい大きいサイズのアナルプラグを潜ませた志穂のテキパキとした仕事振りが、眩しく輝いている。
「マスター、外でお待ちのお客様用に、取り急ぎですが、メニューを作成しました。お渡ししてよろしいですか?」
「ああ、急ぎで作ったわりにはいい出来だねー。よろしく頼むよ」
さすがは元キレモノ本店店長だけに、全裸制服姿になっても卒のない心配りで、店内を切り盛りする綾子。
そんな3人の活躍振りと、お客様の喜ぶ顔を見ながら満足を感じている聡史であったが、彼にはこの店のマスターとして“やらなければならない”大事な仕事のために、入退場を繰り返す全てのお客様に目を配っていた。
「玲奈、2番テーブルのあの女性に、これをお渡ししてくれ」
「あ、はーい♪きっと喜びますよぉ♪」
玲奈に手渡したものは“メンバーへの推薦状”である。
聡史の独断と偏見で、彼の目に適った女性のみに贈られる推薦状であり、晴れてメンバーになれば、いよいよ“誰もが憧れる2階メンバーフロア”の利用が出来るようになるのだ。
「うわぁ!きゃー!嬉しい♪ホントですかぁ!?」
聡史の思惑通り、推薦状を受け取った女性客から歓喜の声が上がっている。
こんな独断と偏見に満ちた行為は、本来であれば“差別行為”として、社会的にも受け入れられることのない所業であるが、この店内はそんな一般社会的通念から隔絶された、言わば“治外法権”的な空間であり、聡史の価値観念が絶対の領域であり、そこに足を踏み入れた全ての者は、その歪んだ観念を自らの脳内で勝手に“憧れ”や“ステイタス”として偶像化してくれるので、ありがたいことこの上ないのである。
こうして聡史はマスターとしての最初の大仕事に熱心に取り組み、今日一日で50名程の女性に推薦状を配りまくり、その全ての女性から、自ら進んでの“承諾”の返事を取り付け、専用のメンバーカードを手渡した。
どの女性も聡史の好みに適った“いい獲物”揃いであった。
明日あたりから、彼女達が我先にと“特別待遇”を求めて、このお店に足を運ぶことになるだろう。
そして、大忙しの内にオープン初日が幕を閉じた…。
(黒水晶〈第7話〉につづく…)
妄想商会(14)~黒水晶〈第5話〉~*特殊アイテム
「志穂さん、お疲れ様。出したもの見せてもらったけど、やはり相当中は汚れているね。これではせっかくの美貌が台無しだし、何より接客業には問題あるのは分かりますよね?」
「は、はい…そうですよね。しっかりケア出来ていなくて恥ずかしいです」
「玲奈はチーフだけに、そのあたりはしっかりしてるんだけど…便秘症だけは絶対に治そう。いいですね?」
「はい!頑張ります」
「ということで、これからは常にこれをケツ穴に差し込んでおいてください」
そう言って聡史が志穂の前に差し出したものは、直径2cmほどのアナルプラグであった。
「あの…これをどうすれば…」
「こうするんですよ。ほら、オシリをこっちに向けてください」
志穂が聡史の方にオシリを向けた途端に、何の躊躇もなしに彼女のアナルにプラグを押し込んだ。オイルも何も付けていないのだから、かなり強引な挿入である。
「アウッ!!!痛っ!!!痛いっ!!!」
「ハハハ、最初は痛いでしょう。でもケツ穴がキツイから便が出てこないんですよ。 だからこれは志穂さんの穴には絶対に必要な処置です。ちょっと息んでみてください」
「は、はい…フンッ…ンッ…(!?抜けない!?)」
「先が太くなっているプラグだから抜けないんですよ。明日ここに出勤してくるまではそれを差し込んだままにしましょう。 いいですね? くれぐれも旦那さんに見つからないようにしなくてはダメですよ。便秘治療なんて知られたら恥ずかしいでしょうし…。なので、直るまでは旦那さんに裸を見られないように!これ、マスターからの言い付けです。守れますね?」
「はい。分かりました」
このときから志穂のアナル拡張訓練がスタートした。
聡史はこの清楚な奥様を、淫らなアナル奴隷にするつもりなのである。ノーマルなセックスなど与えてやらない。清楚な上辺とは全く正反対な変態行為を当たり前のように受け入れる女性に仕立て上げてやる…そんな邪心が今の聡史を支配していた。
それから二日後…。新装オープンを3日後に控えた午後、ようやく3人目の従業員が見つかった。
「アッ…アフン…アッ、アッ、アゥンッ!…」
今目の前で紺色の上等なスーツ姿のまま大股を広げて、聡史の一物を体内に咥え込んでいるのがその女性である。
彼女の名前は加賀谷 綾子(かがや あやこ) 25歳。
実は彼女はここから数駅先の街にある大型エステチェーン店の店長だったのだ。店長職だけにいつもスーツに身を包んでの仕事らしく、毎日その姿で出勤していた。
一人住まいのマンションがこの店の近くらしく、聡史は以前から駅に向かう彼女や帰宅途中の彼女を、店の前で見かけており、その“デキる女性”“キャリアウーマン”的な眩いばかりの美貌に目を奪われていたのだ。そこで彼女は予定していた3人枠の最後の一人に、応募者の中から…ではなく、こちらから彼女をスカウトすることにしたのである。
引き抜くのは簡単であった。
昨日店の前をいつものように仕事を終えて通りかかった彼女に、
「いつもお会いしますね、もうじき新装オープンなんですよ。よろしければオープン前のお店で休憩がてら新しく用意したコーヒーを試飲していきませんか?もちろんケーキも添えますよ」
などと声をかけたものである。
こういう時は、普段からのキチンとしたセンスの良い店構えによる信頼がものを言う。
綾子の方も一流建築家がデザインしたこのセンスの良い店を以前から気に入っており、過去に何度か立ち寄ったこともあったので、聡史の誘いに気軽に応じてきた。
こうなればクモの巣にかかった蝶である。まんまと結界内に入った綾子は、「明日からここで働きましょう」と切り出した聡史の言葉を受け入れるしかない。
というわけで、午前中に突然の退社希望を提出して、午後にこの店に来たのである。先方のエステサロンには多大な迷惑をかけるが、しばらくは転職のための業務整理で先方とこちらを行ったり来たりしてもらいながら働いてもらうことにした。
もちろん、報酬面も前職より多く設定してある。資金はシルクがいくらでも用立ててくるのだから。
「綾子、従業員5ヶ条の第4条を諳んじてごらん」
「は、はぃぃ…アゥッ…私たちの身体はマスターの所有物。いつでもどこでもお触りもOK、犯すもOK、安全日は中出しOK…で、です…アァ…」
「さすが頭脳明晰の元店長だね。もう覚えてる。そうだよ、これがその第4条。大事な仕事っていうことは理解しているね?」
「はぃ…アッ、アッ!」
エステサロンから直行してきたスーツ姿のままの綾子を犯しながら、聡史は綾子の誤認度を弄んでいる。
綾子は黒いロングヘアーがよく似合う美形であるが、キレ者キャリアウーマンの凛としたオーラと、女性専用エステサロンという女社会の中でその束ねをしていたこともあり、どことなく男を寄せ付けない隙のなさを持っている。
聡史はそんな女性をこうもいとも簡単に手中にでき、自分の思うように操れる快感に酔い痴れていた。
「綾子、君の立場はこれまでの経験を活かしてもらって“店長候補”だ。玲奈がマネージャーで志穂が一般従業員。自分の立場が分かるね?」
「アッ…ァアア…はい、ありがとう…ございます…」
「だから他の二人よりも報酬も多くしている。その分、5ヶ条に書いてあることは他の二人以上に意識して働いてもらわないとね。第5条も諳んじてごらん」
「はい…マスターのオチ○チンは常にキレイにフェ○チオで舐め上げておくこと。特にマスターのトイレ後には率先して行うこと!出てくる精液は心を込めて飲み下すこと…です」
「そうだね、でも店長候補としてはそれだけでは不十分。こういった行為の後、自分の体液で汚してしまったときもきれいにしてもらわないとね。お店はいつも清潔に!そうだろ?」
「はい…アゥッ!…その通りです…」
「ところで、今日は安全日なのかな?」
「はい…もちろん…大丈夫です…」
「では遠慮なくこのまま出させてもらうね。いい仕事をするためにも、しっかりと受け入れるんだよ」
「はぃいっ!…アァァァッ!すご…い…アッ!アァァァッ!!」
ドピュッ!ドピュッ!ドピュッ!
聡史は欲望の滾りの全てを綾子の体内に注ぎ込んだ。しかし、その張り詰めた肉棒の硬度はさして変らず、その後も執拗にピストンを繰り返す。綾子の股間の接合部では白い泡が立ち込め始めていた。
しばらくして、気が済んだのかようやく綾子の体内から引き出した一物には、自らの精液と綾子の愛液とが絡まり、それが白い泡となって絡み付いていた。
「では綾子、きれいにしてくれるかな」
「はい…」
綾子はいたって事務的に速やかにその汚れた一物を口に含み、器用に動く舌で汚れを拭っていった。
本来であれば、自分の体液も混ざっている混合液を舌で拭うことには、多少は抵抗感を感じてもおかしくないのであろうが、今の綾子にはこれが店長候補として課せられたこなさなければならない誇りある仕事と認識しているので、抵抗感など微塵もなかった。
(黒水晶〈第6話〉につづく…)
「は、はい…そうですよね。しっかりケア出来ていなくて恥ずかしいです」
「玲奈はチーフだけに、そのあたりはしっかりしてるんだけど…便秘症だけは絶対に治そう。いいですね?」
「はい!頑張ります」
「ということで、これからは常にこれをケツ穴に差し込んでおいてください」
そう言って聡史が志穂の前に差し出したものは、直径2cmほどのアナルプラグであった。
「あの…これをどうすれば…」
「こうするんですよ。ほら、オシリをこっちに向けてください」
志穂が聡史の方にオシリを向けた途端に、何の躊躇もなしに彼女のアナルにプラグを押し込んだ。オイルも何も付けていないのだから、かなり強引な挿入である。
「アウッ!!!痛っ!!!痛いっ!!!」
「ハハハ、最初は痛いでしょう。でもケツ穴がキツイから便が出てこないんですよ。 だからこれは志穂さんの穴には絶対に必要な処置です。ちょっと息んでみてください」
「は、はい…フンッ…ンッ…(!?抜けない!?)」
「先が太くなっているプラグだから抜けないんですよ。明日ここに出勤してくるまではそれを差し込んだままにしましょう。 いいですね? くれぐれも旦那さんに見つからないようにしなくてはダメですよ。便秘治療なんて知られたら恥ずかしいでしょうし…。なので、直るまでは旦那さんに裸を見られないように!これ、マスターからの言い付けです。守れますね?」
「はい。分かりました」
このときから志穂のアナル拡張訓練がスタートした。
聡史はこの清楚な奥様を、淫らなアナル奴隷にするつもりなのである。ノーマルなセックスなど与えてやらない。清楚な上辺とは全く正反対な変態行為を当たり前のように受け入れる女性に仕立て上げてやる…そんな邪心が今の聡史を支配していた。
それから二日後…。新装オープンを3日後に控えた午後、ようやく3人目の従業員が見つかった。
「アッ…アフン…アッ、アッ、アゥンッ!…」
今目の前で紺色の上等なスーツ姿のまま大股を広げて、聡史の一物を体内に咥え込んでいるのがその女性である。
彼女の名前は加賀谷 綾子(かがや あやこ) 25歳。
実は彼女はここから数駅先の街にある大型エステチェーン店の店長だったのだ。店長職だけにいつもスーツに身を包んでの仕事らしく、毎日その姿で出勤していた。
一人住まいのマンションがこの店の近くらしく、聡史は以前から駅に向かう彼女や帰宅途中の彼女を、店の前で見かけており、その“デキる女性”“キャリアウーマン”的な眩いばかりの美貌に目を奪われていたのだ。そこで彼女は予定していた3人枠の最後の一人に、応募者の中から…ではなく、こちらから彼女をスカウトすることにしたのである。
引き抜くのは簡単であった。
昨日店の前をいつものように仕事を終えて通りかかった彼女に、
「いつもお会いしますね、もうじき新装オープンなんですよ。よろしければオープン前のお店で休憩がてら新しく用意したコーヒーを試飲していきませんか?もちろんケーキも添えますよ」
などと声をかけたものである。
こういう時は、普段からのキチンとしたセンスの良い店構えによる信頼がものを言う。
綾子の方も一流建築家がデザインしたこのセンスの良い店を以前から気に入っており、過去に何度か立ち寄ったこともあったので、聡史の誘いに気軽に応じてきた。
こうなればクモの巣にかかった蝶である。まんまと結界内に入った綾子は、「明日からここで働きましょう」と切り出した聡史の言葉を受け入れるしかない。
というわけで、午前中に突然の退社希望を提出して、午後にこの店に来たのである。先方のエステサロンには多大な迷惑をかけるが、しばらくは転職のための業務整理で先方とこちらを行ったり来たりしてもらいながら働いてもらうことにした。
もちろん、報酬面も前職より多く設定してある。資金はシルクがいくらでも用立ててくるのだから。
「綾子、従業員5ヶ条の第4条を諳んじてごらん」
「は、はぃぃ…アゥッ…私たちの身体はマスターの所有物。いつでもどこでもお触りもOK、犯すもOK、安全日は中出しOK…で、です…アァ…」
「さすが頭脳明晰の元店長だね。もう覚えてる。そうだよ、これがその第4条。大事な仕事っていうことは理解しているね?」
「はぃ…アッ、アッ!」
エステサロンから直行してきたスーツ姿のままの綾子を犯しながら、聡史は綾子の誤認度を弄んでいる。
綾子は黒いロングヘアーがよく似合う美形であるが、キレ者キャリアウーマンの凛としたオーラと、女性専用エステサロンという女社会の中でその束ねをしていたこともあり、どことなく男を寄せ付けない隙のなさを持っている。
聡史はそんな女性をこうもいとも簡単に手中にでき、自分の思うように操れる快感に酔い痴れていた。
「綾子、君の立場はこれまでの経験を活かしてもらって“店長候補”だ。玲奈がマネージャーで志穂が一般従業員。自分の立場が分かるね?」
「アッ…ァアア…はい、ありがとう…ございます…」
「だから他の二人よりも報酬も多くしている。その分、5ヶ条に書いてあることは他の二人以上に意識して働いてもらわないとね。第5条も諳んじてごらん」
「はい…マスターのオチ○チンは常にキレイにフェ○チオで舐め上げておくこと。特にマスターのトイレ後には率先して行うこと!出てくる精液は心を込めて飲み下すこと…です」
「そうだね、でも店長候補としてはそれだけでは不十分。こういった行為の後、自分の体液で汚してしまったときもきれいにしてもらわないとね。お店はいつも清潔に!そうだろ?」
「はい…アゥッ!…その通りです…」
「ところで、今日は安全日なのかな?」
「はい…もちろん…大丈夫です…」
「では遠慮なくこのまま出させてもらうね。いい仕事をするためにも、しっかりと受け入れるんだよ」
「はぃいっ!…アァァァッ!すご…い…アッ!アァァァッ!!」
ドピュッ!ドピュッ!ドピュッ!
聡史は欲望の滾りの全てを綾子の体内に注ぎ込んだ。しかし、その張り詰めた肉棒の硬度はさして変らず、その後も執拗にピストンを繰り返す。綾子の股間の接合部では白い泡が立ち込め始めていた。
しばらくして、気が済んだのかようやく綾子の体内から引き出した一物には、自らの精液と綾子の愛液とが絡まり、それが白い泡となって絡み付いていた。
「では綾子、きれいにしてくれるかな」
「はい…」
綾子はいたって事務的に速やかにその汚れた一物を口に含み、器用に動く舌で汚れを拭っていった。
本来であれば、自分の体液も混ざっている混合液を舌で拭うことには、多少は抵抗感を感じてもおかしくないのであろうが、今の綾子にはこれが店長候補として課せられたこなさなければならない誇りある仕事と認識しているので、抵抗感など微塵もなかった。
(黒水晶〈第6話〉につづく…)
妄想商会(13)~黒水晶〈第4話〉~*特殊アイテム
今、新装オープン直前の喫茶店のオフィス内で、新規採用者の澤野志穂が白いスケスケパンティと首に巻いた真っ赤なリボンのみというほぼ全裸状態で、大股開きの状態で椅子の肘掛に両脚を乗せた格好で座っている。そして、マスターの板垣聡史から手渡された変態行為の承諾を含む就労5ヶ条を、澱みなく読み終えたところであった。
誤解しないでいただきたいが、志穂は決して娼婦でも露出癖があるわけではない。某有名音大を卒業し、その後も有名音楽教室で講師業を営み、やり手商社マンの男性と結婚し、一等地に建つ高級マンションで夫婦二人きりの優雅な生活を送っている30歳の若妻なのだ。
普段は高級感あるシックなファッションに身を包み、旦那以外の男性の前では貞操をしっかりと保っている良妻でもある。
そんな彼女が、何故初対面の聡史の前でこんな破廉恥な行為をしているのか…。その理由は、彼女自身がその行為を全く破廉恥なことと認識していないからである。彼女の思考では、シックでセンスのいい制服に身を包み、この店の流儀に適ったきちんとした座り方で椅子に座り、“やって当たり前”のどこの喫茶店やお店にもある約束事の確認をしていることになっている。尚続ければ、無理やりそれを演じているわけではなく、本心でそう捉えているのだ。
しかし本人はどうであれ、こんな姿を旦那が見たらさぞ驚くことであろうことは間違いない光景が、聡史の目の前で繰り広げられている。この姿を志穂にとって最愛の旦那に見せてみたいものだ…そんな歪んだ征服感に満足を感じながら、聡史は志穂の読み上げる変態5ヶ条を聞いていた。
「読み上げていただいて、ありがとうございます。それがこのお店の基本理念です。それを毎回仕事に入る前にここで読み上げていただき、読むだけではなくきちんと実践していただくことになりますが、大丈夫ですか?」
「はい、もちろんです。講師業をしていた時も挨拶やお礼の言葉などに対してもかなり意識しておりました」
「そうですか。まぁ、その辺りは今の志穂さんを見ていても、何ら問題はありませんしね。…それと、店主と従業員の関係として、今後このお店の中では志穂さんの身体は私の所有物となり、触るも舐めるも嗅ぐも犯すもやりたい放題になりますが、それも問題ありませんか?」
ここまでこの魔界の結界の効果が立証されていることに、聡史は完全に安心しきっている。そんな彼から発せられた大胆極まりない問い掛けに、
「はい、それももちろんです。私たちは雇われている立場ですから、当然のことだと思います」
傍から聞いていれば、ものすごいことを承諾しているとも気付かずに、志穂は平然と肯定の返事を返した。
「ご理解いただいて、ありがとうございます。これでお互いにいい関係が作れそうですねー」
「はい。こちらこそよろしくお願いいたします」
「では、店主としてまた、志穂さんの身体の所有者として、知っておかなければならないことばかりを質問しますから、しっかりと答えてくださいね。これは従業員の職場環境や衛生環境をいい状態に保つ上で、大切なことばかりですからね」
「はい、わかりました」
「結婚はいつしました?」
「ちょっと遅めで…2年前です…」
「28歳の時ですね。ずっと仕事で頑張っていたんですから、遅くはなかったでしょう。旦那さんのお名前と年齢は?」
「澤野敏明、32歳です」
「敏明さんのことは愛していますか?」
「はい、とても愛しています」
「ということは、セックスもまだ盛んで?週にどれくらいしてます?これは健康管理上必要な質問ですよ」
「はい…仕事が忙しく、疲れているときが多いので、週に…ということではないのですが…月に3~4回程度です」
「へぇ…まだ結婚2年目なのに、意外と少ないですねー。セックスは嫌いですか?」
「いえ、嫌いという訳では…」
「自分から誘ったりはしないんですか?」
「いえ…ほとんど私からです。…主人が疲れてなさそうなときに…ですね」
「(それも以外だな…こんな貞淑そうな奥様が自分からとはねぇ…これは意外とスキモノかも…)」
「その時はどんな風に?キスを求めたり、抱きついたり…ですか?こういうことは仕事に対する積極性を知る上で大切ですからね。出来るだけ具体的に答えてくださいね」
「はい…大体背中の方からそっと抱きついていって、着ているものをめくって背中を舐めたりして反応を見ます…それで応えてくれそうなら、下のほうにいって、その…」
「あぁ、言っておきますが、身体の各部はハッキリと言ってください。男性器は“チ○ポ”、女性器は“マ○コ”、オシリの穴は“ケツ穴”この3つはこの店での決まり呼称です。それにセックスやフェ○チオなどの行為名称も同じです。こういう練習をしておかないと、お客様からのオーダーをハッキリと言えなかったりしますからね。大事なことですよ」
「あ…そうですよね。こういうことも練習材料になっているんですね。やはりこのお店を選んでよかったです」
「でしょう。しっかりした従業員教育環境があってこそ、最高のサービスが出来る…これが私のモットーですからね。…では先ほどの続きをどうぞ」
「はい…それで主人が応えてくれそうなら、チ○ポを舐めにいきます」
「ほほう。(…やはり、これは相当なスキモノだな。上品そうな顔立ちしていても、そっちは別なのね…それにしても、大股開きのその格好で、その上品なお口から“チ○ポ”などという言葉を平気で口にして…はしたないですよー、志穂さん…それにしてもこうまで素直に答えてくれると面白いな…)」
志穂の普段のハイスラスな生活振りとその上品な容姿に対して、今現在裸同然の格好のまま大股開きで椅子に座りながら、淫らな淫語を並べ立てているというギャップに異常な興奮を覚えた聡史の執拗な質問責めは、尚も続き、
「フェ○チオだけで旦那さんが射精してしまうこともありますか?」
「はい。時々あります」
「その時は、どうするんですか?飲み込むこともあるんですか?」
「はい…大抵口の中にそのまま出されますので…」
「いい奥様ですねー。もちろんここでも仕事の一環として、私のものもしゃぶってもらいますが、私のも飲めますか?」
「もちろんです。それはお仕事のスキルとして大切なことだと思っています」
「その節はよろしくお願いしますね。…話は変りますが、そんなにセックスがお好きなのに回数が少ないということは、欲求不満の時はオナニーなんかして紛らわせているんですか?」
「えーと…」
「あ、これは精神衛生上必要な質問ですよ」
「あ、はい…生理前とかに時々…」
「なるほどー、まぁ、自然なことですからね。その欲求は、職場で我慢されるとものすごく支障があるのは分かりますね?」
「はい…そうだと思います」
「なので、ここでは絶対に我慢しないでください。それは約束してくださいね。お客様に最高のサービスをするためには、そんなことで鬱憤を溜めてもらっては困りますから。だから、オナニーがしたくなったら、必ずしてください。私がここで仕事をしていても構いませんから。いいですね」
「はい。わかりました」
「その時は今座っている椅子に腰掛けてしてもらっていいですが、やはりマナーは守ってもらわないとね。なので、今のような姿勢で座って上品にオナニーしてくださいね」
「そうですね。マスターのお仕事の邪魔にならないように、そうさせていただきます」
「では最後の質問ですが、志穂さんのアナル…すなわちケツ穴は、敏明さんに使ってもらってますか?」
「えっと…あの…質問の意味が…」
「おっと、ちょっと抽象的な言い方になってしまいましたね。すみません。具体的に言えば、敏明さんは志穂さんのケツ穴に指を入れたり、アナルセックスしたりはしていますか?という質問です」
「あ…いえ、そこは主人にも触ってもらいたくない場所ですから…」
「なるほど、それは恥ずかしいからですか?それとも自分で汚い部分だと思っているからですか?」
「はい…やっぱり…汚いと思いますから…主人にもそこは恥ずかしいので触ってもらいたくはないです」
「ほほう、でもそれは問題ですね。ここは食品を扱うお店ですし、また志穂さんの身体の所有者としては、汚い部分をそのままに…って言うわけにはいかないですからねー」
「あ、すみません…でもちゃんと毎日朝と夜にシャワーは浴びてます…」
「でも、汚いと思っているのは中が…ってことでしょ?まさかそこまでは自分で洗えませんよね」
「は、はい…」
「私が何で従業員の身体の所有者になって、全ての穴を使わせてもらうかわかりますか?…それは、徹底した衛生管理のためなんですよ。私が時折舌や指やチ○ポを入れることで、閉鎖された部分の風通しも良くなりますし、何しろそれでキレイになるじゃないですか。そう思いませんか?」
「あ、はい…その通りだと思います」
こんな屁理屈を押し通している自分自身に対するおかしさを堪えながら、聡史はそれでも真剣に受け止めてくれる志穂の謙虚さと素直さに感心し、またより愛しく思えた。“こんな女性と結婚できたら…”と、旦那である敏明に少しジェラシーを感じたりもしたが、もともと独身貴族を信条としてきた彼が、今更結婚などという不自由な束縛の中で生活していく…などということにその内満足もいかなくなるな…と思い直し、しかしこのジェラシーによる鬱憤は、その内旦那の目の前で晴らさせてもらおうという歪んだ攻撃心も芽生えさせることとなった。
「よし、では質問はここまで!次は店内に張り出すスタッフ紹介写真を撮りますから、そのままの姿勢で
両手を頭の後ろに回してください。そう、そんな感じで。で、顔を正面から少しずらして、目線をこっちに。
それでそのまま敏明さんを誘惑するようなときの表情してくださいね。その方がお客様も喜ぶでしょうから…」
志穂はそれがきちんとしたスタッフ紹介写真の撮影だと思い込んでいるのだろう。言われたまま妖しい娼婦のような表情になり、大股開きのまま淫らな写真を撮られてしまった。その写真が大きく引き伸ばされ、近日中に店内に掲示されることとなる。
「ご苦労様。では次に、身体検査と衛生検査に入りますね。明日から実際働いていただくには、どうしてもこの検査を受けてもらわなくてはなりませんから。いいですね?」
「はい。よろしくお願いいたします」
「では立って頂いて、制服を全部脱いでしまってください」
「はい…」
制服を脱ぐ…と言っても、パンティを脱いでリボンを外すだけなので、数十秒の作業である。すぐに全裸になった。
「では、今座っていた椅子に額を付けて、膝をしっかりと伸ばしてください」
言われるがままにその態勢をとると、腰の位置よりも頭が低くなり、聡史に向けて自分の秘所をどうぞ見てくださいと言わんばかりの、恥ずかしいポーズになった。
色素があまり沈着していない淡い茶色がかった二つの恥丘も、小さくすぼまったアナルも全てが聡史の目の前に顕わに晒されている状態である。
「ではまず匂い検査しますね。接客業としては当然の検査ですから、そのままじっとしていてくださいね」
「はい…お願いします」
言うなり、聡史は志穂のオシリを鷲掴みにして大きく開き、その中心部に一気に鼻を押し付け、まるで犬が人間の股間の匂いに興味を示している時のように、激しく嗅ぎまくった。
「ひゃぅっ!」
「うーん…上品な顔立ちとは裏腹に、やっぱりオ○ンコは生臭いですね。さっき玲奈の制服見ましたでしょ。志穂さんも同じように、“今日は臭いオ○ンコです”と明記しないと、衛生基準に引っ掛かりますからね。毎回私が確認しますから、その結果をちゃんとお客様に表示してくださいね」
「はい…わかりました」
「ただ、アナルはさほど匂いませんねー。今日はちゃんとウ○チしました?」
「あ、いえ…実は少し便秘気味で…」
「どれくらい?」
「いつも3日くらいは出ません…」
「それは食品を扱うお店としてはいけませんねー。分かりますよね?お腹にそんなものたくさん溜め込まれてては、いつ食中毒が発生するか分からないでしょう」
「は、はい…すみません…」
「志穂さんは外面は綺麗でも、内面はものすごく汚いということですよ。そんな評価は嫌でしょう」
「は、はい…」
「ちょっと検査しますね。痛いかもしれないけど、このままでは仕事に出すわけにいかないので、我慢してくださいね」
「はい…」
聡史は、こういうときのために既に用意してあったローションを取り出し、志穂のアナル周りと自分の指に薄らと塗りこんで、半ば強引に括約筋の抵抗などお構いなしに一気に人差し指を根本まで沈み込ませた。
「アウッ!ッウゥゥッ…い、痛っ…痛い…です…」
一際高い悲鳴を上げて、志穂は迫り来る痛みに耐えている。こんな経験はこれまでの人生の中で初めてである。出るものを出す専用の穴に、今は聡史の指が逆流してきているのだ。
「我慢、我慢。それに、ここをどう使うかは、所有者である私が決めますからね。これくらいの刺激は慣れてもらわないと。何しろここには私のチ○ポも入るわけですから」
「は、はいぃぃ…アグゥゥ…そ、それって…ハァァァ…も、もっと痛い…ってことで…アゥッ!…すか・・」
聡史は志穂の痛がっている様子など一向に構う様子もなく、指のピストン運動や内部のまさぐり動作を止めることなく、
「ハハハ、慣れれば何てことないですよ。この穴が徐々に弛みっぱなしになってくれるでしょうから。ほら、こんな感じで、もう一本の指も…」
「アッ!アッ!ハァウッ!!」
人差し指と中指、合わせて2本の指が志穂のアナルに埋没した。それだけではなく、中をこねくり回したり、押し広げたり、2本同時にピストンさせたりとかなり激しくその指を運動させていた。
そうなると、その刺激になれていなければ特に生理現象として排泄感がこみ上げてくるもので、志穂も例外なくその感覚が身体の奥の方から急速にこみ上がってくるのを感じていた。
「マ、マスター…で、出そう…です」
「ん?何が?」
「ウ…ウ○チ…です」
「ハハハ、当然の生理現象でしょうね。でもよかったでしょう。これでお腹の中がキレイになるんだから。…丁度いい、ここで検便もしちゃいましょうね。…おーい玲奈!」
大きな声で外にいる玲奈を呼ぶと、すぐに玲奈が入ってきた。
「マスター、何ですか?あれ?志穂さん、ずいぶん痛そう」
「ああ、そうなんだよ。志穂さん、便秘気味でこの中に一杯汚いもの溜め込んでるようなんだ。やっぱりそれは飲食業としてはダメだろ?だから検便も兼ねてスッキリキレイにさせてあげようと思ってね」
「うんうん♪それは絶対その方がいいですよぉ♪マスター優しい~♪」
「だろっ、ということで、ちょっとバケツ持ってきてよ」
「はーい♪志穂さんも頑張ってくださいねっ♪」
「あ…あり…がとう…」
今や息も絶え絶えかのような様子でありながらも、しっかりと玲奈の励ましに答えるあたりに、志穂の人間としての出来具合が窺え、聡史はそんな上等な女性がこれから自分の目の前で最も恥ずかしい瞬間を披露してくれることに、異常な興奮を覚えていた。
「ハウゥッ…アゥッ!…も、もうダメ…です…我慢できない…です…ウゥゥ…」
聡史の執拗な2本指の攻撃に、志穂の排泄欲求の我慢も限界に達してきたようで、先程から聡史の指先にも中から下ってきた何かが当たるようになってきていた。ようやく指を抜いて、少し茶色く染められた指先を鼻に近づけてみる…。ものすごく刺激的な異臭が鼻を突いた。それを今度は志穂の鼻で汚れを拭うかのように押し付けると、
「キャッ、キャアッ!!嫌っ!臭いっ!!」
「でしょ?こんなの溜め込んでたら、仕事にならないことを分かってもらえますか?」
「…は、はいぃ…」
あまりの衝撃的な臭さに、思わず涙ぐむような表情の志穂。
「便秘は表には出なくても、中でこれだけウ○チが腐敗してることですから、飲食業では要注意なんですよ。一緒に治しましょうね。便秘症。その方が志穂さんの普段の生活でもいいことでしょ?」
「は、はい…治したいです…」
「便秘が治るまでは、これも表示義務がありますから、“私のウ○チはものすごく臭いです”と身体に表示してもらいますよ。そうしておけば衛生上の問題にはならないでしょうからね」
「は、はいぃ…あぁ…」
いよいよ限界に達したようである。そこで、玲奈が持ってきたバケツを志穂の股間に置き、それを跨ぐような格好でしゃがませ、
「じゃあ、一気に出しちゃってください。出してる最中の模様は、後々保健所の提出要請があった時に備えて、このビデオで撮影しておきますからね」
先程から、聡史の言っていることは滅茶苦茶なことばかりである。何の根拠も必要性もありはしないことを、さも都合のいいように言い立てているだけなのだが、志穂や玲奈にとっては、ことごとく説得力のある理路整然とした内容として受け取られるらしく、
「はい…お願いします…では…」
素直に肯定の返事をしながら、何のためらいもなくお腹に力を入れると、鈍い破裂音とともに太く濃茶褐色の物体が、数本に分かれてバケツの中に落下していった。
30歳の分別がしっかりとついている女性で、それもハイソサエティな生活を送っているうら若きマダムにとって、他の何よりも憚りたがり、そして絶対に他人が立ち入ることを許したくない領域が今この瞬間に破られている。それも彼女自身の自発的な行動によってである。彼女自身はマスターである聡史の言うがままに、ここで頑張って仕事をする為に必要な“飲食業としてごく当たり前”の準備をしているだけ…という認識のもとだからこそ、こんな破廉恥で変態的な行為も自然に行えているのである。
(黒水晶<第5話>に続く…。)
誤解しないでいただきたいが、志穂は決して娼婦でも露出癖があるわけではない。某有名音大を卒業し、その後も有名音楽教室で講師業を営み、やり手商社マンの男性と結婚し、一等地に建つ高級マンションで夫婦二人きりの優雅な生活を送っている30歳の若妻なのだ。
普段は高級感あるシックなファッションに身を包み、旦那以外の男性の前では貞操をしっかりと保っている良妻でもある。
そんな彼女が、何故初対面の聡史の前でこんな破廉恥な行為をしているのか…。その理由は、彼女自身がその行為を全く破廉恥なことと認識していないからである。彼女の思考では、シックでセンスのいい制服に身を包み、この店の流儀に適ったきちんとした座り方で椅子に座り、“やって当たり前”のどこの喫茶店やお店にもある約束事の確認をしていることになっている。尚続ければ、無理やりそれを演じているわけではなく、本心でそう捉えているのだ。
しかし本人はどうであれ、こんな姿を旦那が見たらさぞ驚くことであろうことは間違いない光景が、聡史の目の前で繰り広げられている。この姿を志穂にとって最愛の旦那に見せてみたいものだ…そんな歪んだ征服感に満足を感じながら、聡史は志穂の読み上げる変態5ヶ条を聞いていた。
「読み上げていただいて、ありがとうございます。それがこのお店の基本理念です。それを毎回仕事に入る前にここで読み上げていただき、読むだけではなくきちんと実践していただくことになりますが、大丈夫ですか?」
「はい、もちろんです。講師業をしていた時も挨拶やお礼の言葉などに対してもかなり意識しておりました」
「そうですか。まぁ、その辺りは今の志穂さんを見ていても、何ら問題はありませんしね。…それと、店主と従業員の関係として、今後このお店の中では志穂さんの身体は私の所有物となり、触るも舐めるも嗅ぐも犯すもやりたい放題になりますが、それも問題ありませんか?」
ここまでこの魔界の結界の効果が立証されていることに、聡史は完全に安心しきっている。そんな彼から発せられた大胆極まりない問い掛けに、
「はい、それももちろんです。私たちは雇われている立場ですから、当然のことだと思います」
傍から聞いていれば、ものすごいことを承諾しているとも気付かずに、志穂は平然と肯定の返事を返した。
「ご理解いただいて、ありがとうございます。これでお互いにいい関係が作れそうですねー」
「はい。こちらこそよろしくお願いいたします」
「では、店主としてまた、志穂さんの身体の所有者として、知っておかなければならないことばかりを質問しますから、しっかりと答えてくださいね。これは従業員の職場環境や衛生環境をいい状態に保つ上で、大切なことばかりですからね」
「はい、わかりました」
「結婚はいつしました?」
「ちょっと遅めで…2年前です…」
「28歳の時ですね。ずっと仕事で頑張っていたんですから、遅くはなかったでしょう。旦那さんのお名前と年齢は?」
「澤野敏明、32歳です」
「敏明さんのことは愛していますか?」
「はい、とても愛しています」
「ということは、セックスもまだ盛んで?週にどれくらいしてます?これは健康管理上必要な質問ですよ」
「はい…仕事が忙しく、疲れているときが多いので、週に…ということではないのですが…月に3~4回程度です」
「へぇ…まだ結婚2年目なのに、意外と少ないですねー。セックスは嫌いですか?」
「いえ、嫌いという訳では…」
「自分から誘ったりはしないんですか?」
「いえ…ほとんど私からです。…主人が疲れてなさそうなときに…ですね」
「(それも以外だな…こんな貞淑そうな奥様が自分からとはねぇ…これは意外とスキモノかも…)」
「その時はどんな風に?キスを求めたり、抱きついたり…ですか?こういうことは仕事に対する積極性を知る上で大切ですからね。出来るだけ具体的に答えてくださいね」
「はい…大体背中の方からそっと抱きついていって、着ているものをめくって背中を舐めたりして反応を見ます…それで応えてくれそうなら、下のほうにいって、その…」
「あぁ、言っておきますが、身体の各部はハッキリと言ってください。男性器は“チ○ポ”、女性器は“マ○コ”、オシリの穴は“ケツ穴”この3つはこの店での決まり呼称です。それにセックスやフェ○チオなどの行為名称も同じです。こういう練習をしておかないと、お客様からのオーダーをハッキリと言えなかったりしますからね。大事なことですよ」
「あ…そうですよね。こういうことも練習材料になっているんですね。やはりこのお店を選んでよかったです」
「でしょう。しっかりした従業員教育環境があってこそ、最高のサービスが出来る…これが私のモットーですからね。…では先ほどの続きをどうぞ」
「はい…それで主人が応えてくれそうなら、チ○ポを舐めにいきます」
「ほほう。(…やはり、これは相当なスキモノだな。上品そうな顔立ちしていても、そっちは別なのね…それにしても、大股開きのその格好で、その上品なお口から“チ○ポ”などという言葉を平気で口にして…はしたないですよー、志穂さん…それにしてもこうまで素直に答えてくれると面白いな…)」
志穂の普段のハイスラスな生活振りとその上品な容姿に対して、今現在裸同然の格好のまま大股開きで椅子に座りながら、淫らな淫語を並べ立てているというギャップに異常な興奮を覚えた聡史の執拗な質問責めは、尚も続き、
「フェ○チオだけで旦那さんが射精してしまうこともありますか?」
「はい。時々あります」
「その時は、どうするんですか?飲み込むこともあるんですか?」
「はい…大抵口の中にそのまま出されますので…」
「いい奥様ですねー。もちろんここでも仕事の一環として、私のものもしゃぶってもらいますが、私のも飲めますか?」
「もちろんです。それはお仕事のスキルとして大切なことだと思っています」
「その節はよろしくお願いしますね。…話は変りますが、そんなにセックスがお好きなのに回数が少ないということは、欲求不満の時はオナニーなんかして紛らわせているんですか?」
「えーと…」
「あ、これは精神衛生上必要な質問ですよ」
「あ、はい…生理前とかに時々…」
「なるほどー、まぁ、自然なことですからね。その欲求は、職場で我慢されるとものすごく支障があるのは分かりますね?」
「はい…そうだと思います」
「なので、ここでは絶対に我慢しないでください。それは約束してくださいね。お客様に最高のサービスをするためには、そんなことで鬱憤を溜めてもらっては困りますから。だから、オナニーがしたくなったら、必ずしてください。私がここで仕事をしていても構いませんから。いいですね」
「はい。わかりました」
「その時は今座っている椅子に腰掛けてしてもらっていいですが、やはりマナーは守ってもらわないとね。なので、今のような姿勢で座って上品にオナニーしてくださいね」
「そうですね。マスターのお仕事の邪魔にならないように、そうさせていただきます」
「では最後の質問ですが、志穂さんのアナル…すなわちケツ穴は、敏明さんに使ってもらってますか?」
「えっと…あの…質問の意味が…」
「おっと、ちょっと抽象的な言い方になってしまいましたね。すみません。具体的に言えば、敏明さんは志穂さんのケツ穴に指を入れたり、アナルセックスしたりはしていますか?という質問です」
「あ…いえ、そこは主人にも触ってもらいたくない場所ですから…」
「なるほど、それは恥ずかしいからですか?それとも自分で汚い部分だと思っているからですか?」
「はい…やっぱり…汚いと思いますから…主人にもそこは恥ずかしいので触ってもらいたくはないです」
「ほほう、でもそれは問題ですね。ここは食品を扱うお店ですし、また志穂さんの身体の所有者としては、汚い部分をそのままに…って言うわけにはいかないですからねー」
「あ、すみません…でもちゃんと毎日朝と夜にシャワーは浴びてます…」
「でも、汚いと思っているのは中が…ってことでしょ?まさかそこまでは自分で洗えませんよね」
「は、はい…」
「私が何で従業員の身体の所有者になって、全ての穴を使わせてもらうかわかりますか?…それは、徹底した衛生管理のためなんですよ。私が時折舌や指やチ○ポを入れることで、閉鎖された部分の風通しも良くなりますし、何しろそれでキレイになるじゃないですか。そう思いませんか?」
「あ、はい…その通りだと思います」
こんな屁理屈を押し通している自分自身に対するおかしさを堪えながら、聡史はそれでも真剣に受け止めてくれる志穂の謙虚さと素直さに感心し、またより愛しく思えた。“こんな女性と結婚できたら…”と、旦那である敏明に少しジェラシーを感じたりもしたが、もともと独身貴族を信条としてきた彼が、今更結婚などという不自由な束縛の中で生活していく…などということにその内満足もいかなくなるな…と思い直し、しかしこのジェラシーによる鬱憤は、その内旦那の目の前で晴らさせてもらおうという歪んだ攻撃心も芽生えさせることとなった。
「よし、では質問はここまで!次は店内に張り出すスタッフ紹介写真を撮りますから、そのままの姿勢で
両手を頭の後ろに回してください。そう、そんな感じで。で、顔を正面から少しずらして、目線をこっちに。
それでそのまま敏明さんを誘惑するようなときの表情してくださいね。その方がお客様も喜ぶでしょうから…」
志穂はそれがきちんとしたスタッフ紹介写真の撮影だと思い込んでいるのだろう。言われたまま妖しい娼婦のような表情になり、大股開きのまま淫らな写真を撮られてしまった。その写真が大きく引き伸ばされ、近日中に店内に掲示されることとなる。
「ご苦労様。では次に、身体検査と衛生検査に入りますね。明日から実際働いていただくには、どうしてもこの検査を受けてもらわなくてはなりませんから。いいですね?」
「はい。よろしくお願いいたします」
「では立って頂いて、制服を全部脱いでしまってください」
「はい…」
制服を脱ぐ…と言っても、パンティを脱いでリボンを外すだけなので、数十秒の作業である。すぐに全裸になった。
「では、今座っていた椅子に額を付けて、膝をしっかりと伸ばしてください」
言われるがままにその態勢をとると、腰の位置よりも頭が低くなり、聡史に向けて自分の秘所をどうぞ見てくださいと言わんばかりの、恥ずかしいポーズになった。
色素があまり沈着していない淡い茶色がかった二つの恥丘も、小さくすぼまったアナルも全てが聡史の目の前に顕わに晒されている状態である。
「ではまず匂い検査しますね。接客業としては当然の検査ですから、そのままじっとしていてくださいね」
「はい…お願いします」
言うなり、聡史は志穂のオシリを鷲掴みにして大きく開き、その中心部に一気に鼻を押し付け、まるで犬が人間の股間の匂いに興味を示している時のように、激しく嗅ぎまくった。
「ひゃぅっ!」
「うーん…上品な顔立ちとは裏腹に、やっぱりオ○ンコは生臭いですね。さっき玲奈の制服見ましたでしょ。志穂さんも同じように、“今日は臭いオ○ンコです”と明記しないと、衛生基準に引っ掛かりますからね。毎回私が確認しますから、その結果をちゃんとお客様に表示してくださいね」
「はい…わかりました」
「ただ、アナルはさほど匂いませんねー。今日はちゃんとウ○チしました?」
「あ、いえ…実は少し便秘気味で…」
「どれくらい?」
「いつも3日くらいは出ません…」
「それは食品を扱うお店としてはいけませんねー。分かりますよね?お腹にそんなものたくさん溜め込まれてては、いつ食中毒が発生するか分からないでしょう」
「は、はい…すみません…」
「志穂さんは外面は綺麗でも、内面はものすごく汚いということですよ。そんな評価は嫌でしょう」
「は、はい…」
「ちょっと検査しますね。痛いかもしれないけど、このままでは仕事に出すわけにいかないので、我慢してくださいね」
「はい…」
聡史は、こういうときのために既に用意してあったローションを取り出し、志穂のアナル周りと自分の指に薄らと塗りこんで、半ば強引に括約筋の抵抗などお構いなしに一気に人差し指を根本まで沈み込ませた。
「アウッ!ッウゥゥッ…い、痛っ…痛い…です…」
一際高い悲鳴を上げて、志穂は迫り来る痛みに耐えている。こんな経験はこれまでの人生の中で初めてである。出るものを出す専用の穴に、今は聡史の指が逆流してきているのだ。
「我慢、我慢。それに、ここをどう使うかは、所有者である私が決めますからね。これくらいの刺激は慣れてもらわないと。何しろここには私のチ○ポも入るわけですから」
「は、はいぃぃ…アグゥゥ…そ、それって…ハァァァ…も、もっと痛い…ってことで…アゥッ!…すか・・」
聡史は志穂の痛がっている様子など一向に構う様子もなく、指のピストン運動や内部のまさぐり動作を止めることなく、
「ハハハ、慣れれば何てことないですよ。この穴が徐々に弛みっぱなしになってくれるでしょうから。ほら、こんな感じで、もう一本の指も…」
「アッ!アッ!ハァウッ!!」
人差し指と中指、合わせて2本の指が志穂のアナルに埋没した。それだけではなく、中をこねくり回したり、押し広げたり、2本同時にピストンさせたりとかなり激しくその指を運動させていた。
そうなると、その刺激になれていなければ特に生理現象として排泄感がこみ上げてくるもので、志穂も例外なくその感覚が身体の奥の方から急速にこみ上がってくるのを感じていた。
「マ、マスター…で、出そう…です」
「ん?何が?」
「ウ…ウ○チ…です」
「ハハハ、当然の生理現象でしょうね。でもよかったでしょう。これでお腹の中がキレイになるんだから。…丁度いい、ここで検便もしちゃいましょうね。…おーい玲奈!」
大きな声で外にいる玲奈を呼ぶと、すぐに玲奈が入ってきた。
「マスター、何ですか?あれ?志穂さん、ずいぶん痛そう」
「ああ、そうなんだよ。志穂さん、便秘気味でこの中に一杯汚いもの溜め込んでるようなんだ。やっぱりそれは飲食業としてはダメだろ?だから検便も兼ねてスッキリキレイにさせてあげようと思ってね」
「うんうん♪それは絶対その方がいいですよぉ♪マスター優しい~♪」
「だろっ、ということで、ちょっとバケツ持ってきてよ」
「はーい♪志穂さんも頑張ってくださいねっ♪」
「あ…あり…がとう…」
今や息も絶え絶えかのような様子でありながらも、しっかりと玲奈の励ましに答えるあたりに、志穂の人間としての出来具合が窺え、聡史はそんな上等な女性がこれから自分の目の前で最も恥ずかしい瞬間を披露してくれることに、異常な興奮を覚えていた。
「ハウゥッ…アゥッ!…も、もうダメ…です…我慢できない…です…ウゥゥ…」
聡史の執拗な2本指の攻撃に、志穂の排泄欲求の我慢も限界に達してきたようで、先程から聡史の指先にも中から下ってきた何かが当たるようになってきていた。ようやく指を抜いて、少し茶色く染められた指先を鼻に近づけてみる…。ものすごく刺激的な異臭が鼻を突いた。それを今度は志穂の鼻で汚れを拭うかのように押し付けると、
「キャッ、キャアッ!!嫌っ!臭いっ!!」
「でしょ?こんなの溜め込んでたら、仕事にならないことを分かってもらえますか?」
「…は、はいぃ…」
あまりの衝撃的な臭さに、思わず涙ぐむような表情の志穂。
「便秘は表には出なくても、中でこれだけウ○チが腐敗してることですから、飲食業では要注意なんですよ。一緒に治しましょうね。便秘症。その方が志穂さんの普段の生活でもいいことでしょ?」
「は、はい…治したいです…」
「便秘が治るまでは、これも表示義務がありますから、“私のウ○チはものすごく臭いです”と身体に表示してもらいますよ。そうしておけば衛生上の問題にはならないでしょうからね」
「は、はいぃ…あぁ…」
いよいよ限界に達したようである。そこで、玲奈が持ってきたバケツを志穂の股間に置き、それを跨ぐような格好でしゃがませ、
「じゃあ、一気に出しちゃってください。出してる最中の模様は、後々保健所の提出要請があった時に備えて、このビデオで撮影しておきますからね」
先程から、聡史の言っていることは滅茶苦茶なことばかりである。何の根拠も必要性もありはしないことを、さも都合のいいように言い立てているだけなのだが、志穂や玲奈にとっては、ことごとく説得力のある理路整然とした内容として受け取られるらしく、
「はい…お願いします…では…」
素直に肯定の返事をしながら、何のためらいもなくお腹に力を入れると、鈍い破裂音とともに太く濃茶褐色の物体が、数本に分かれてバケツの中に落下していった。
30歳の分別がしっかりとついている女性で、それもハイソサエティな生活を送っているうら若きマダムにとって、他の何よりも憚りたがり、そして絶対に他人が立ち入ることを許したくない領域が今この瞬間に破られている。それも彼女自身の自発的な行動によってである。彼女自身はマスターである聡史の言うがままに、ここで頑張って仕事をする為に必要な“飲食業としてごく当たり前”の準備をしているだけ…という認識のもとだからこそ、こんな破廉恥で変態的な行為も自然に行えているのである。
(黒水晶<第5話>に続く…。)